今週はタブラ奏者のユザーンさんをお招きして、7拍子の魅力について教えていただきました。以前にもユザーンさんをゲストにお招きして5拍子を特集しましたが、今回は7拍子。5拍子以上になじみの薄い拍子だと思います。
拍子は強弱を伴う拍の周期的な連なりから生まれます。多くの曲は2拍子、3拍子、4拍子といった拍子で書かれているのですが、まれに5拍子や7拍子で書かれた曲があります。5拍子の有名曲といえば「テイク・ファイブ」や「ミッション・インポッシブル」(スパイ大作戦)のテーマ。それに比べると、7拍子でだれもが知っている曲はなかなか見当たりません。
「7拍子を使った世界でいちばん有名かもしれない曲」とU-zhaanさんが語るのは、ビートルズ「愛こそはすべて」。前に「つんのめる」ような感覚があって、おもしろいですよね。スピッツの「美しい鰭」でも、7拍子の部分は「つんのめる」ようになっています。7拍目の後に1拍休符が入れば普通の曲になるのでしょうが、そこで休みが入らずに次に進むことで、背中を押されているような気分になります。ちなみにクラシックでは、プロコフィエフのピアノ・ソナタ第7番の終楽章が7拍子で書かれた曲として知られています。楽章の頭からおしまいまで、ずっと7拍子が続くのですが、尋常ではない緊迫感があります。
U-zhaanさんのお話で驚いたのは、7拍子の裏拍(バックビート)でノるというお話。7拍子の裏拍と言われても、いったいどこなのかと思いますよね。2拍目、4拍目、6拍目、7拍目で手を打てばいいのだとか。6拍と7拍で連続するところで、すっきりした気分になれます。
おしまいの「ラーガ・ヤマン」は、インド伝統音楽における7拍子の定番曲なのだとか。ゆったりと、たゆたうように始まって、次第に熱を帯びて高揚していく様子がすばらしいと思いました。
飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)
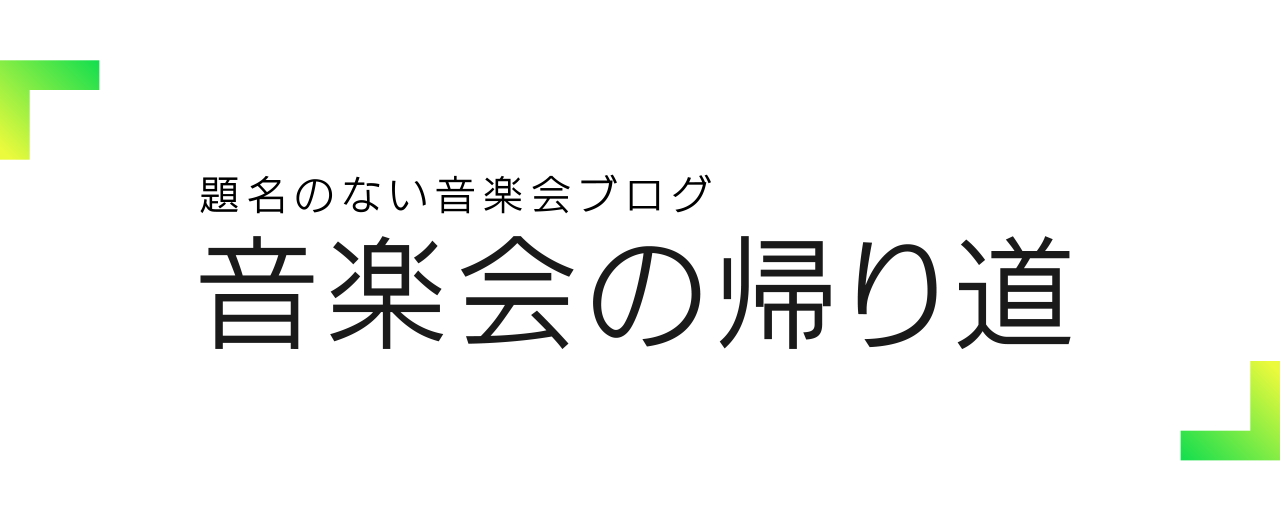
 公式サイト
公式サイト