今週は吹奏楽部の高校生たちが日本を代表するスター奏者たちから直接指導を受けるという夢の企画。全日本吹奏楽コンクールで2年連続金賞を受賞した東海大学菅生高等学校吹奏楽部のみなさんが、モーション・ブルー・ヨコハマに来てくれました。「小曽根真 featuring No Name Horses」のサウンドを間近で聴く高校生たち。うらやましい光景です。
「小曽根真 featuring No Name Horses」は総勢15名からなるビッグバンド。エリック・ミヤシロさんのトランペットの抜けるようなハイトーンはなんど聴いても快感です。小曽根さんも最高に音楽を楽しんでいる様子が伝わってきました。
高校生たちから寄せられた質問はどれも具体的。「トロンボーンで小さな音をきれいに出すには?」「トランペットの高音がキツい音になってしまう」。そして、質問に対するプロの教え方は、細かな奏法を手取り足取り教えるのではなく、音のイメージを共有するような教え方だったのが興味深いと思いました。高校生たちがアドバイスを即座に吸収して、自分の音に反映させていたのには驚くばかり。こんなにうまくいくものなのかなと思ってしまうほどで、おそらく教える側も何度となく同様の質問に向き合ってきたのでしょう。演奏もすごいけれども、教え方もすごい!
「パプリカ」で高校生がプロと共演する場面もおもしろかったですよね。おなじみの「パプリカ」がジャズに生まれ変わっている新鮮さもさることながら、神のような人たちと共演して力を出し切った高校生には心からの拍手を送るほかありません。そして、小曽根さんのアドバイスが秀逸です。「怖がっていると絶対に音楽にのまれてしまう。思い切り演奏する」。これはジャズに限らず、ほかの音楽でも、あるいはスポーツなどの世界でも通用する言葉かもしれませんね。
飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)
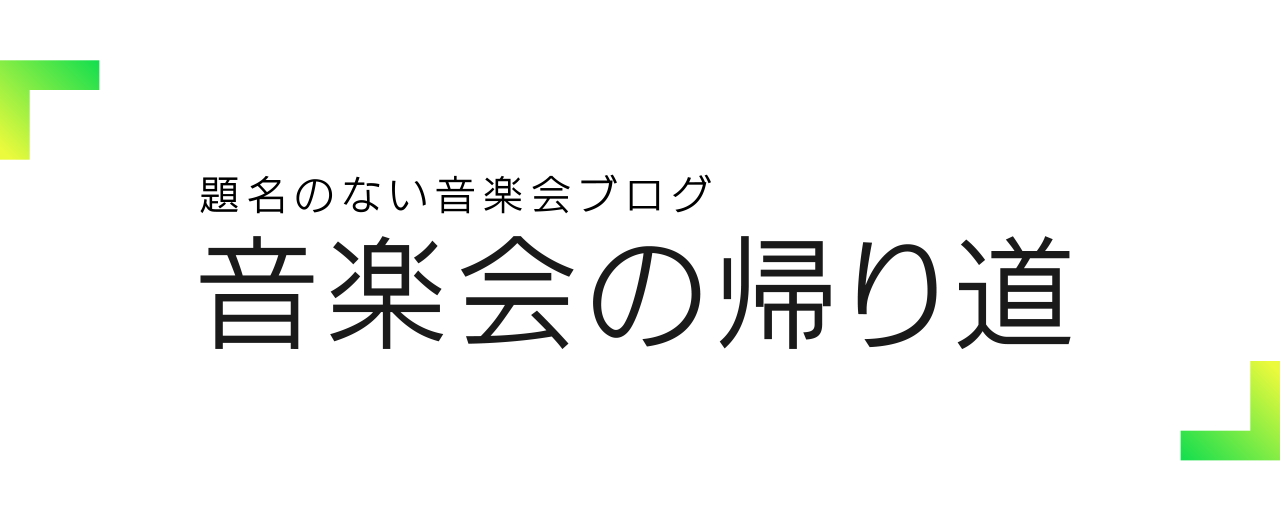
 公式サイト
公式サイト