今週はハンドサインで即興演奏をするel tempo(エル・テンポ)のみなさんをお招きしました。昨年、一昨年にもシシド・カフカさんとel tempoの演奏をお楽しみいただきましたが、今回はシシドさんに加えてハンドサイン「リズム・ウィズ・サインズ」の考案者であるサンティアゴ・バスケスさんが参加してくれました。ふたりのコンダクターが同じel tempoからまったく違った音楽を引き出してくれたおかげで、いっそうハンドサインのおもしろさが伝わってきたように思います。
コンダクターという言葉が示すように、メンバーに次々と指示を出すシシドさんやサンティアゴさんの姿は、オーケストラの指揮者を連想させます。でも、オーケストラと根本的に違うのは、これが即興演奏であること。ハンドサインのコンダクターは、指揮者であると同時に作曲家でもあると言えるでしょう。
el tempoのメンバーの芳垣安洋さんが、シシドさんとサンティアゴさんの違いについて、「シシドさんははっきりしたベクトルを持って力強く進む。サンティアゴさんはハーモニーを自由にいつでもギアチェンジできる」と話していましたが、これには納得。これまでの2回でも、シシドさんはパワフルで推進力のある音楽を生み出していましたが、今回初めて聴いたサンティアゴさんの音楽はとても変化に富んでいて、意外性に満ちていました。カラフルな音色を次々と引き出しながら、遊び心あふれる音楽をくりひろげます。コンダクターが変われば、ぜんぜん違った音楽が生まれるということがよくわかりました。
ふたりのコンダクターが交代する即興演奏も楽しかったですよね。途中からシシドさん、さらにはサンティアゴさんが会場に向かってサインを出して、全員が参加する場面がありました。聴くだけではなく参加できるのはハンドサインの大きな魅力。客席のみなさんがちゃんとハンドサインを理解していて、すごい!と感心しました。
飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)
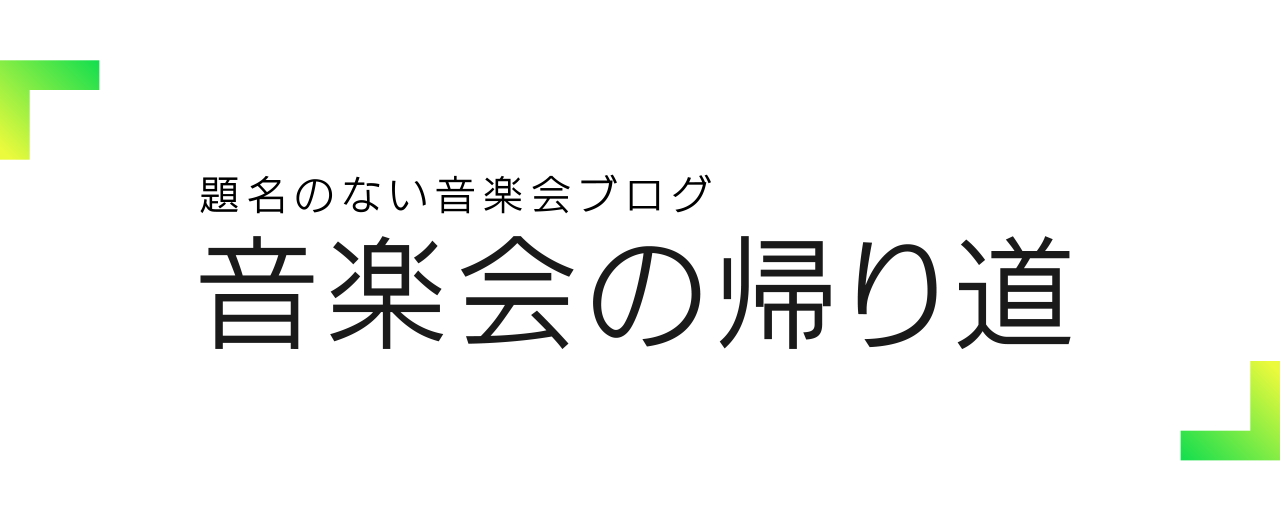
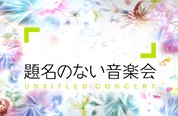 公式サイト
公式サイト