今回は、東京オペラシティ・コンサートホールで開催された第28回出光音楽賞受賞者ガラコンサートの模様をお届けしました。受賞者はサクソフォンの上野耕平さん、ヴァイオリンの辻彩奈さん、チェロの岡本侑也さんの3名です。
「もっと多くの人にクラシックのサクソフォンを聴いてほしい」と語るのは、すでに多方面で活躍中の上野さん。サクソフォンはクラシック音楽の世界では比較的新しい楽器です。モーツァルトやベートーヴェンの時代にはこの楽器はまだありませんでした。サクソフォンの作品が盛んに書かれるようになったのは20世紀に入ってから。イベールの「アルト・サクソフォーンと11の楽器のための室内小協奏曲」はその先駆けともいえる存在です。上野さんの軽快なソロが、機知に富んだ多彩な楽想を表現してくれました。まだまだこの楽器のレパートリーはこれから広がっていくのでしょうし、そのためには上野さんのような若くて意欲的な奏者の存在が欠かせません。
ヴァイオリンの辻彩奈さんはまだ20歳という若さ。とてもそんな年齢とは思えないようなスケールの大きな表現が印象に残りました。オーケストラとの共演でも不足を感じさせない芯の強い音も魅力。ショーソンの「詩情」に込められた豊かな情熱と幻想味が存分に伝わってきます。この曲はクライマックスの後に訪れる最後の余韻がいいんですよね。
チェリストの岡本侑也さんは、チャイコフスキーの「ロココの主題による変奏曲」を演奏してくれました。チェリストにとってはオーケストラと共演する際の貴重なレパートリー。のびやかな音色で、洗練された端正なチャイコフスキーを披露してくれました。爽快でしたよね。
毎年、この受賞者ガラコンサートを聴くと、日本の若手演奏家のレベルの高さを感じずにはいられません。3人ともまちがいなく、今後ますます大きな舞台で活躍してくれることでしょう。
新着記事
月別アーカイブ
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
出光音楽賞 受賞者ガラコンサート
天才による前代未聞の音楽会
今週はストラヴィンスキーの「兵士の物語」をお楽しみいただきました。石丸幹二さんがこれまでになんども朗読で上演に参加している作品です。
ストラヴィンスキーといえば20世紀音楽に革命をもたらした真の天才作曲家。バレエ音楽の「春の祭典」「火の鳥」「ペトルーシュカ」といった革新的作品でヨーロッパの楽壇にセンセーションを巻き起こし、時代の寵児となりました。これらはいずれも大編成のオーケストラを用いた作品です。
ところが第一次世界大戦が本格化すると、これまでのような大規模な作品を上演することは困難になります。しかも、ロシア十月革命の影響で祖国からの収入も途絶え、ストラヴィンスキーは窮地に立たされました。
そこで、少人数で演奏できて、各地を巡業できるようなタイプの作品を書けないかと考えて作られたのが「兵士の物語」。7人の奏者に朗読やパントマイムが加わるなど、さまざまな上演形態が可能です。器楽のみによる組曲版も盛んに演奏されています。
「兵士の物語」は音楽的にも斬新ですが、ストーリーもよくできています。休暇中の兵士が故郷への帰り道でヴァイオリンを弾いていると、老人に化けた悪魔が「富を得る本」とヴァイオリンの交換を持ちかけます。兵士が老人の家で三日間を過ごすと、その間に三年の月日が流れていました。兵士が故郷に帰ると、婚約者はすでに別の男と結婚し、子供をもうけています。兵士は本を使って金持ちになりますが、心は満たされません。旅に出た兵士は病に伏せる王女に出会います。兵士は悪魔と賭けで勝負してヴァイオリンを取り戻すと、ヴァイオリンを王女に聴かせて病を治します。ふたりは結婚するのですが、兵士は故郷が忘れられません。「国の外に出てはならない」と悪魔から警告されたにもかかわらず、兵士は国境を越えてしまい、魂を悪魔に奪われてしまいます。
凡庸な男の成功と破滅の物語。なんとも示唆的です。
ダンス・ダンス・ダンスの音楽会
今回はバラエティに富んだダンス・ミュージックの数々をテレビ朝日夏祭りサマーステーションのステージよりお届けいたしました。暑さを吹き飛ばすような迫力満点のステージでした。
どんなジャンルの音楽でもそうだと思うのですが、ダンスと音楽は切っても切れない関係にあります。民謡やポップ・ミュージックだけではなく、クラシック音楽でも名曲と呼ばれる音楽のほとんどはダンスのリズムと密接に結び付いています。バレエ音楽や舞曲はダンスそのものですし、交響曲にもメヌエットのようなダンスに由来する楽章が入っていたりします。バレエの分野で目にした言葉で「踊れない音楽はない」という一言がありますが、至言ではないでしょうか。
今回はエリック・ミヤシロさんがトランペットにアレンジにと大活躍でした。あの抜けるようなハイトーンは本当に爽快ですよね。
「南中ソーラン」と「エビカニクス」は今の子供たちにとっては大定番のダンス・ナンバー。「南中ソーラン」は小中学校を中心に、最近では保育園や幼稚園でも盛んに踊られています。ソーラン節がこんな形で子供たちの世界に定着するとは。世代を超えるって、こういうことなんでしょうね。「エビカニクス」はもっと下の年齢のお子さんの人気曲。年少さんでも踊れるシンプルで楽しい振付が人気の秘密でしょうか。もしかすると今の子供たちが最初に覚えるダンスが、この「エビカニクス」かもしれません。会場でもお子さんたちがいっしょに踊ってくれました。
西城秀樹さんが歌った「ヤングマン」は、1979年に社会現象といってもいいほどの大ヒットを記録しました。あの名曲を石丸さんが歌ってくれたことに感激です。この曲のヒットも「YMCA」の振付があってこそ。歌とダンスが一体になったときのパワーを改めて感じました。
オーケストラの打楽器奏者を知る休日
今週はオーケストラの打楽器奏者に焦点を当てて、その奥深い世界をご紹介しました。奏者それぞれの工夫やこだわりが垣間見えて、新鮮な驚きがありましたよね。
打楽器奏者がほかの奏者と異なるのは、ひとりでたくさんの種類の楽器を演奏しなければならないところ。小太鼓や大太鼓、シンバル、マリンバなど、いろいろな楽器を演奏できなければいけません。しかも、福島喜裕さんが披露してくださったように、シンバルひとつとっても楽器によって特徴がさまざまに異なるというのですから驚きます。
さらに打楽器奏者は「なぜこれが打楽器なのか?」と思うような楽器まで受け持ちます。レスピーギの交響詩「ローマの松」における鳥笛をはじめ、ホイッスルやホースのように、叩かないタイプの楽器であっても、打楽器奏者が担当します。ルロイ・アンダーソンの「タイプライター」に登場する機械式タイプライターや、ガーシュウィンの「パリのアメリカ人」で使われる車のクラクションのように、本来は実用品だったものが特定の名曲のおかげで楽器になったという例もあります。
特定の曲との結びつきが強い打楽器といえば、マーラーの交響曲第6番「悲劇的」の終楽章で登場するハンマーを挙げないわけにはいきません。大きな槌を振り下ろす様子は視覚的にも迫力満点。舞台に近い客席にはかなりの衝撃が伝わります。特に舞台奥側にも座席があるタイプのコンサートホールでは、ハンマーのすぐそばで聴いているお客さんが思わず身構えてしまうこともしばしば。知らずに聴いて、こんなにびっくりする交響曲もないでしょうね。
ちなみにこのマーラーの「悲劇的」ではハンマー以外にもグロッケンシュピール、カウベル、むち、鐘、シロフォン、シンバル、タムタム他の打楽器が用いられます。20世紀以降、オーケストラで使用される楽器の種類はぐんと増えました。打楽器奏者の役割は広がるばかりです。
変幻自在な作曲家サン=サーンスの音楽会
今週はフランスの作曲家サン=サーンスのバラエティに富んだ名曲をお楽しみいただきました。のびやかなメロディが心地よい「白鳥」から、エキゾチックな「バッカナール」まで、サン=サーンスの多面的な魅力が伝わったのではないでしょうか。
たいていの大作曲家は幼少時から並外れた楽才を示すものですが、3歳で作曲したというサン=サーンスの神童ぶりは際立っています。わずか10歳でピアノ協奏曲を演奏してデビューを果たし、アンコールには「ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲のうちからどれでも一曲を暗譜で演奏しましょう」と申し出たといいます。少しイヤミなくらいの才能ですよね。
これだけ才能に恵まれていたのですから、サン=サーンスがフランスの音楽界をリードする存在になったのは必然です。当時、フランスで交響曲や協奏曲といえば、もっぱらベートーヴェンなどドイツ音楽が演奏されていたのに対し、サン=サーンスは自ら交響曲や協奏曲を書いて、この分野にフランスの伝統を築きあげました。交響曲第3番「オルガン付き」を聴いた作曲家グノーは、サン=サーンスを「フランスのベートーヴェン」と呼びました。
幼い頃から神童と騒がれたのはモーツァルトと同じですが、サン=サーンスとモーツァルトには一点、大きな違いがあります。モーツァルトは35歳で人生を終えたのに対して、サン=サーンスは86歳まで長生きをしました。
おかげで、若い頃は時代をリードする存在だったサン=サーンスも、晩年には保守派の代表とみなされるようになります。サン=サーンス自身、若い世代の音楽には共感できなかったようで、新時代の旗手ドビュッシーを敵視したり、ストラヴィンスキーの「春の祭典」の初演に立ち会って作品を酷評したり。天才の割に神格化されなかったのは、そんな晩年のふるまいが影響したのかもしれません。
指揮者が愛する「新世界より」の音楽会
今週は気鋭の若手指揮者、川瀬賢太郎さんの大切な一曲、ドヴォルザークの「新世界より」をお届けいたしました。
新世界、すなわちアメリカへとドヴォルザークが旅立ったのは1892年のこと。アメリカにも本格的な音楽院が必要だと考えた富豪の夫人ジャネット・サーバーが、ニューヨークに音楽院を設立し、その院長にドヴォルザークを招いたのです。当初、ドヴォルザークはこの話には乗り気ではなかったようです。しかし、サーバー夫人が破格の報酬を申し出たこともあり、交渉を重ねた末にドヴォルザークはアメリカ行きを決意しました。
なにしろ19世紀のことですので、現代のようにジェット機で飛んでいくことはできません。ヨーロッパからアメリカへ、船で12日間を要する船旅でした。
アメリカに渡ったドヴォルザークは、黒人霊歌や先住民の音楽に出会い、大きな関心を寄せました。そんな音楽的な刺激から誕生したのが「新世界より」。第2楽章のノスタルジックなメロディはよく知られています。まるで民謡のように自然で滑らかなメロディですよね。これがアメリカ風と言われればそんな気もしますし、一方でドヴォルザークの故郷であるチェコ風と言われればそうなのかなとも思えます。日本では「遠き山に日は落ちて」(家路)といった歌詞で唱歌として愛唱されているように、日本語ともよくなじみます。アメリカでもGoin’ Homeの題で歌詞付きで出版されています。望郷の音楽というものは全世界共通なのかも?
ドヴォルザークは鉄道マニアとしても知られていました。蒸気機関車に魅せられて、駅を訪ねてはその様子を何時間も眺めたり、列車の時刻表や運転手の名前まで暗記していたといいます。川瀬さんが第4楽章冒頭を蒸気機関車が発進する音楽とおっしゃっていましたが、これには納得。徐々にスピード感を増していく様子が実にスリリングです。当時の最新テクノロジーへの憧れが反映されているのでしょうか。
高嶋ちさ子と7人のチェリストの音楽会
今週はヴァイオリニストの高嶋ちさ子さんとスーパーチェロ7のみなさんにご登場いただきました。独奏ヴァイオリンとチェロ・アンサンブルという組合せは珍しいですよね。
高嶋さんがチェロを「万能楽器」を呼んでいたように、チェロは一人で何役もできてしまう楽器です。あるときはソリストとして主役になり、あるときは低音楽器として縁の下の力持ちにもなれます。幅広い音域を生かして朗々とメロディを歌い上げるのもチェロの魅力なら、オーケストラでコントラバスとともにブン!と唸るような重低音を聴かせるのもチェロの魅力。
チェロ・アンサンブルという演奏形態が成立するのも、万能楽器だからこそ。普通は同じ楽器のみでアンサンブルを組むことはめったにありませんが、チェロであれば無理なく同種楽器で役割分担ができてしまいます。「ベルリン・フィルの12人のチェリストたち」のようにチェロだけで多彩な音楽を演奏する人気アンサンブルも存在します。
スーパーチェロ7は、東京都交響楽団首席チェロ奏者古川展生さんを中心に、日本のトップレベルで活躍するチェロ奏者たちによるアンサンブルです。名手ぞろいとあって、超絶技巧もお手のもの。小林幸太郎さんがワンボウ・スタッカートを披露してくれましたが、実に鮮やかでした。あまりに軽々と弾いてしまうので、なにが難しいのかわからないほど。でも音楽のテクニックとは本来そうあるべきですよね。江口心一さんはリムスキー=コルサコフの「熊蜂の飛行」を速弾きしてくれました。この曲、もともとはオペラのなかの一場面で登場する曲で、速弾きのための曲というわけではないのですが、熊蜂の羽音の描写がコミカルなこともあって、よくヴァイオリンの速弾きなどで用いられるようになりました。しかし、この曲をチェロで速弾きする人がいるとは! まるで熊蜂がヒュンヒュンと超高速で飛び回っているかのようでした。
クラシックの音楽祭を知る休日
クラシック音楽の世界にもスポーツ界などと同じように「シーズン」という考え方があります。ヨーロッパの伝統に従って、秋から春までがレギュラー・シーズンで、夏はシーズンオフという区切り方が一般的。では、夏はコンサートがないのかといえばそうではなく、この期間に各地で音楽祭が盛んに開かれます。夏は都会の喧騒を離れて、豊かな自然に囲まれた土地で開放的な気分で音楽に浸ろうという発想です。
ただし、近年は大都市で開くタイプの音楽祭もたくさんありますし、「ラ・フォル・ジュルネ」のようにあえて夏以外の季節に開催する音楽祭も増えています。日本でも番組内でご紹介したように、実に多彩な音楽祭が開かれるようになりました。
音楽祭での公演はコンサートホールで開かれるとは限りません。ときには野外だったり、お寺だったり、日本家屋だったり、美術館だったりと、さまざまな場所が活用されています。大都市以外でも集中的にコンサートを開くとなれば、いろいろな会場が使われることになります。そんないつもとは違った環境も音楽祭の魅力のひとつといえるでしょう。
また、音楽祭では普段のシーズンではなかなか聴けないような珍しいレパートリー、貴重なアーティストの共演、意欲的な企画に出会うことができます。吉野直子さんが武生国際音楽祭で即興演奏と生け花のコラボレーションに挑んだといったお話がありましたが、音楽と他のアートを組み合わせるような試みも盛んに行われています。
夏の音楽祭は旅行と組み合わせて楽しむこともできます。たとえばセイジ・オザワ松本フェスティバルだったら、コンサートのついでに評判のお蕎麦屋さんに立ち寄ったり、松本市美術館に行ったり。日程が合えばサッカーの松本山雅FCの試合を観戦するのも一手。大人の夏休みを存分に満喫することができるでしょう。
王道のピアノ協奏曲に熱くなる音楽会
今週は1990年モスクワ生まれの気鋭のピアニスト、ルーカス・ゲニューシャスの独奏で、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番をお聴きいただきました。
ゲニューシャスはこれまでにたびたび来日公演を行なっておりますので、日本の聴衆にとってはなじみのあるピアニストです。今年開催されたラ・フォル・ジュルネTOKYO2018では、ショパンのピアノ協奏曲第1番やピアノ・ソナタ第3番、ヒンデミットの「ルードゥス・トナリス」といった曲を披露してくれました。
ゲニューシャスの魅力は、なんといっても磨き抜かれたテクニック。ショパン・コンクールとチャイコフスキー・コンクールという二大コンクールで2位入賞を果たしただけあって、技巧を技巧と感じさせないような洗練された技術の持ち主だと思います。パワーも十分でオーケストラと共演しても聴き映えがしますが、決して自己顕示欲の強い演奏ではなく、作品の本質に迫ろうとする姿勢が伝わってきます。今回のチャイコフスキーも、改めて作品の雄大さや情感の豊かさに気づかせてくれるような秀演だったのではないでしょうか。
ゲニューシャスのおもしろいところは、チャイコフスキーやショパン、ベートーヴェンといった中心的なレパートリーに取り組む一方で、ヒンデミットの「ルードゥス・トナリス」を十八番にしていたり、現代作曲家のデシャトニコフの作品を広めることに尽力したりといったように、レパートリーに対して強い探求心を持っている点です。お祖母さんが名教師ヴェーラ・ゴルノスターエワということで、音楽一家出身のサラブレッドという印象が強いのですが、活動ぶりは決して保守的ではありません。
ちなみにラ・フォル・ジュルネでヒンデミットを演奏した際、ゲニューシャスは譜面台にタブレットPCを置いて、フットスイッチで楽譜をめくりながら演奏していました。このあたりは若い世代ならではですね。
世界を魅了するイル・ディーヴォの音楽会
今週は世界的なスーパースター、イル・ディーヴォのみなさんをお招きしました。イル・ディーヴォは2004年のデビュー以来、全世界で3000万枚以上のアルバムセールスを記録した男声ヴォーカル・グループ。日本での人気もすさまじく、客席には歓声が盛んに飛び交い、普段の収録とは会場の雰囲気がずいぶん違っていました。格調高い東京オペラシティ・コンサートホールの空間に、いっそうの華やかさが加わったように感じます。
イル・ディーヴォの4人の声が調和して生み出す輝かしさ、情感の豊かさは他に類を見ないものだと思います。そして、4人それぞれが異なる声のキャラクターを持っているところも大きな特徴といえるでしょう。デイヴィッドの軽やかで伸びのある高音、カルロスの深みのある力強いバリトン、セバスチャンの表現力豊かで甘い声質、ウルスのリリカルで端整な歌唱スタイル。それぞれのソロの部分も大変聴きごたえがあります。
イル・ディーヴォのようなオペラ的な歌唱をベースとした男声ヴォーカル・グループの先駆けとなったのは、1990年のワールドカップ・イタリア大会を機に結成された三大テノールだと思います。プラシド・ドミンゴ、ルチアーノ・パヴァロッティ、ホセ・カレーラスというオペラ界のビッグスターが一堂に会してコンサートを開くという革新的なアイディアは、音楽界に大きな驚きをもたらしました。本来オペラにはテノールの三重唱などという場面はめったにありませんが、彼らは男声ソリストによる重唱がどれほどゴージャスでリッチな響きを生み出すかを教えてくれました。イル・ディーヴォはそんな三大テノールを、よりポップな傾向に発展させたアンサンブル重視のヴォーカル・グループだと言えるでしょう。
それにしても、石丸さんとイル・ディーヴォの共演が実現するとは! あまりにも違和感がなさすぎてびっくりしました。
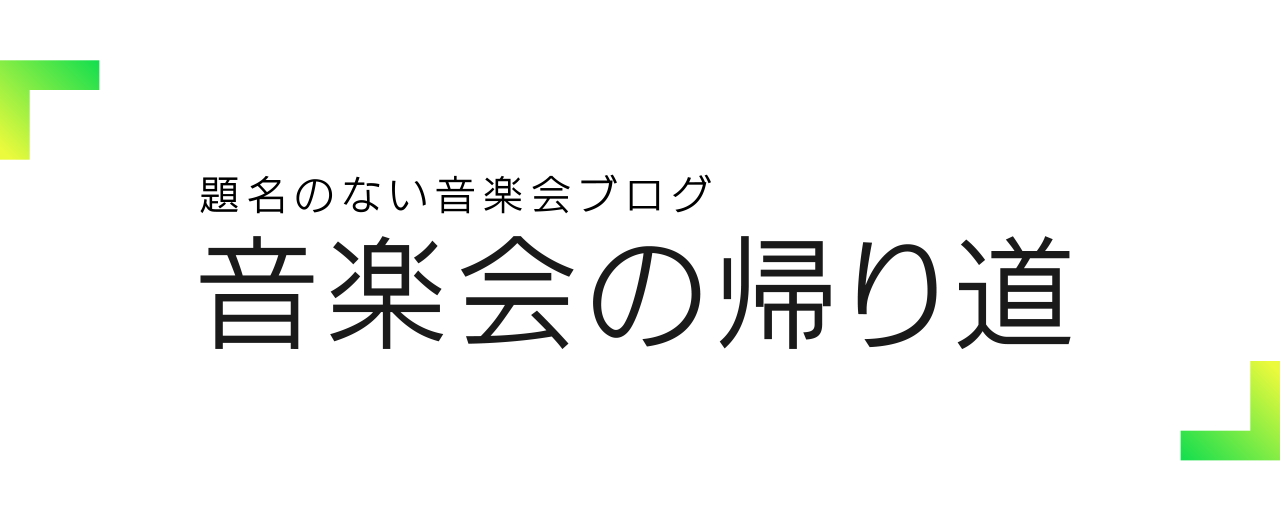
 公式サイト
公式サイト