今週は世界二大オーケストラの精鋭たちによる凄腕アンサンブル、フィルハーモニクス ウィーン=ベルリンの演奏をお届けしました。いやー、本当に楽しかったですよね。なによりプレーヤーたちが自ら楽しんでいる様子がよく伝わってきました。
フィルハーモニクス ウィーン=ベルリンの特徴のひとつはジャンルにこだわらないこと。彼らは普段、ウィーン・フィルやベルリン・フィルで正統派のクラシックの演奏をしているのですが、このアンサンブルではいろいろな音楽に挑戦します。
もうひとつの特徴はオリジナルのアレンジを聴かせてくれること。これが実に遊び心にあふれているんですよね。とりわけ「ボヘミアン・ラプソディ」は彼らの面目躍如。クイーンの原曲自体にバラードやオペラ、ハードロックなどの融合といったコンセプトがあるのですが、フィルハーモニクス ウィーン=ベルリンはこれをバッハ/グノー編曲の「アヴェ・マリア」で始めて、レゲエ風、アイリッシュ風とスタイルを変遷させてゆきました。アイディアがおもしろくて、しかも演奏のクォリティは抜群。最上質のエンタテインメントといっていいでしょう。
ウィーン・フィルとベルリン・フィルは同じドイツ語圏のオーケストラでありながら、対照的な性格を持っています。両方に所属したコンツさんの「ベルリン・フィルは短距離走者、ウィーン・フィルは長距離奏者」というたとえには、なるほどと膝を打ちました。ベルリン・フィルはコンサートのためのオーケストラですので、一回の公演は2時間前後。しっかりリハーサルをして、緻密な音楽を作りあげるのが得意なオーケストラです。一方、ウィーン・フィルのメンバーはウィーン国立歌劇場で連日長時間のオペラを演奏しなければいけません。歌手に合わせて、その場その場で臨機応変に音楽を作りあげる柔軟さが持ち味。フィルハーモニクス ウィーン=ベルリンはそんな両者の「いいとこどり」をしたアンサンブルといえるかもしれません。
新着記事
月別アーカイブ
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
ウィーン&ベルリン・フィル! スーパースター軍団の音楽会
映画音楽の巨匠 ジョン・ウィリアムズの音楽会
今週はジョン・ウィリアムズ作曲の映画音楽の名曲をたっぷりお楽しみいただきました。原田慶太楼さん指揮東京フィルの演奏、本当にすばらしかったですよね。明るく華やかなサウンドで、なかなかこれだけ見事な演奏は聴けるものではありません。
特に最後の「スター・ウォーズのテーマ」はまれに聴く快演だったのでは。映画「スター・ウォーズ」の第1作が1978年に日本で公開された際、この曲は大ブームを巻き起こしました。以来、名曲コンサートやファミリー向けコンサートでしばしば演奏される人気曲になりました。でも、意外とこの曲の演奏って難しいんですよね。ブラス・セクションの輝かしさやキレのあるリズム感がなければ、作品本来の高揚感が伝わってきません。
その点、原田慶太楼さんの指揮はジョン・ウィリアムズ本人にお墨付きをもらっているだけあって、「本物感」がちがいます。パワフルでゴージャス。これぞ、ジョン・ウィリアムズのサウンドです。
原田さんによれば、ジョン・ウィリアムズの音楽では指揮棒に即座に反応してオーケストラが音を出すことが大切なのだとか。指揮棒から少し遅れてズシンと音が出てくるようなクラシック音楽の重厚なサウンドではなく、棒の打点とジャストのタイミングで音が鳴るような鋭敏さが欲しいといいます。やはり切れ味が大事なのでしょう。
「シンドラーのリスト」の解説もとても興味深いものでした。ただ流れるような美しいメロディを作るのではなく、メロディの合間に低音をさしはさんで、引きずられるような表現を加える。これで曲にぐっと奥行きが感じられるようになります。アルトフルートの深みのある音色を活用したオーケストレーションも効果的。巨匠ならではの工夫があちこちに凝らされていることがわかります。
高嶋ちさ子のわがまま音楽会~粘着質な作曲家にダメ出し編
今週は高嶋ちさ子さんが、大作曲家たちに次々と「ダメ出し」をしてくれました。高嶋さんによれば、作曲家は「ダメ男だらけ」。いやー、これには参りました。
まず、やり玉に挙げられたのはベートーヴェン。コーヒーを入れるためにいちいち豆の数をきちんと数えていたという逸話は、当時の資料にも記録されています。コーヒー好きなら気持ちがわかる!? でも、これを「粘着質」とズバッと切るのが高嶋さん。
あの有名な「運命」のエンディングも「しつこすぎる」ということで、大幅にカットされてしまいました。そう、「運命」って、なかなか終わらない曲なんですよね。「そろそろ、終わるのかな?」と思わせておいて、また盛り上げる。「今度こそ、終わるかな?」と思うと、やっぱり終わらない。そうやって何段階もクライマックスを積み上げていくところがこの曲の魅力だと思うのですが、「昔の人はヒマだったから」と一刀両断されてしまいました。笑。
ドイツ音楽におけるベートーヴェンの後継者ブラームスも、高嶋さんによれば「粘着質なところも受け継いでしまった」。クララへの想いを曲に込めたり、作品完成に時間がかかったりしてしまったり、ブラームスって純粋さゆえに決して器用な人ではなかったんでしょうね。交響曲第1番にひそかに込められた「クララへのあいさつ」、すごく素敵な着想だと思うのですが、こういうのって女性の側から見ると、ドン引きしたりするんでしょうか……。
最後はチャイコフスキーも「ダメ出し」されてしまいました。チャイコフスキーが自由に作曲活動に打ち込めたのは、大金持ちのメック夫人に長年経済的に援助してもらったおかげ。しかしメック夫人が資産の一部を失って援助を打ち切ると告げると、チャイコフスキーはすっかり失望し、ふたりの信頼関係は壊れてしまいます。お金でつながる人の縁って、難しいものですね。
JUJUと幹二のおしゃべり音楽会
今週はJUJUさんの歌、そして石丸さんのサックスをたっぷりとお楽しみいただきました。おふたりの共演、とてもいい雰囲気がありました。声とサックスの音色の融け合いがなんとも言えません。
JUJUさんのニューヨーク話もおもしろかったですよね。18歳で単身渡米する大胆さにも感心させられますが、そこで怖さや不安を感じるよりも、ワクワクしたというのがすごい! 「ニューヨークに行けばなんとかなる」という気持ちを若気の至りとおっしゃっていましたが、こうして実際に道を切り開くことができたのですから、非凡というほかありません。
JUJUというお名前の由来が、ウェイン・ショーターのアルバム「JUJU」にあったというお話も印象的でした。「JUJU」を一日中聴いていた時期に、たまたま街でおじさんが売っていたカセットが「JUJU」だった。そんな運命的な出会いがあるんですね。もしそこでこのカセットに出会っていなかったら、どうなっていたのでしょう。
4曲とも名曲でしたが、やはり最後の My Favorite Things は耳に残ります。ジャズのスタンダードとしてさまざまなアーティストによってカバーされてきた曲ですが、もともとはミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」のなかの一曲。ミュージカル映画「サウンド・オブ・ミュージック」では、ジュリー・アンドリュース演じるマリア先生が、雷を怖がる子供たちに向けて、この曲を歌います。だから歌詞で歌われるフェイヴァリット・シングスは「子猫のひげ」だったり「ポカポカの手袋」だったり「リンゴのパイ」だったり、子供たちが好きそうなものが並んでいます。でも、こうしてJUJUさんの歌で聴くと、同じ歌詞からまったく違った情景を想像しませんでしたか。まるで、若い女性が気持ちが落ち込んだときに自分を励ましている歌のように聞こえてきます。
歌声の秘密を知る休日
今週はまったくジャンルの異なる3人の歌手、平原綾香さん、岡本知高さん、木津かおりさんをお招きして、発声法やトレーニングについて語っていただきました。
ポップス、クラシック、民謡。最初のメドレーで、三者三様の歌い方の違いがよく伝わってきました。よく「人間の声は最高の楽器」といいますが、声は使い方によって、まったく違った音色や表現を生み出すことができます。クラシックだけをとっても、声域や声質で、声の種類は何種類にも細分化されています。岡本知高さんはソプラニスタ(男性ソプラノ)と呼ばれる稀有な存在ですので、いっそうその違いが際立っていました。
また、歌唱法をどう習得するかについても大きな違いがあります。平原綾香さんが独学だというのはびっくり。まねをするところからスタートしたといいますが、並外れた研究熱心さがあってこそでしょう。木津かおりさんのように、楽譜を使わずに口伝で学ぶというのは民謡ならでは。一見、非効率にも感じますが、よく考えてみれば楽譜に記したところで、同じ楽譜からさまざまな解釈が生まれるもの。「書き記せないことまで伝達できる」という点で、口伝には口伝の利点があるのでしょう。「こぶしのコツは咳をするみたいな感じで」という説明がおもしろかったですね。やってみると、わかるような、わからないような!?
岡本知高さんが歌った「誰も寝てはならぬ」は、プッチーニのオペラ「トゥーランドット」の名アリア。本来は王子カラフ役のテノールが歌います。男性ソプラノによる歌唱をはじめて聴きましたが、意外と違和感がありません。王子というよりはまるで王女の歌。ドラマティックでした。
「Love Never Dies ~愛は死なず~」はミュージカルの巨匠ロイド=ウェバーの作曲です。平原さんの伸びやかな声、そして声の表現力の多彩さに圧倒されました。
クリスマスソングを楽しむ音楽会
いよいよクリスマスですね。今週は1980年代から90年代に流行したクリスマスソングを、趣向を凝らしたアレンジでお楽しみいただきました。
石丸さんが「私の青春です」と語る「ラスト・クリスマス」は、1984年にリリースされたワム!の大ヒット曲。石丸さんのサクソフォンがカッコよかったですね。「きよしこの夜」や「ジングル・ベル」「もろびとこぞりて」も聞こえてくるという、クリスマス感たっぷりのアレンジでした。
金ピカの衣装が眩しすぎる松永貴志さんが選んだのは、マライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス」。1994年にリリースされて大ヒットを記録し、今やすっかり定番のクリスマスソングになっています。松永さんによるジャズ・バージョンのアレンジで、一段と楽しいクリスマスが訪れたように感じました。
上野耕平さんが選んだのは、1983年にリリースされた山下達郎「クリスマス・イブ」。鉄道会社CMとして広く親しまれた曲だけに、これには納得。ご本人のTwitterなどからも伝わってきますが、上野さんの熱心な鉄道ファンぶりは半端ではありません。なにしろ「生きているうちに日本全国の路線に乗りたい」というほどで、「乗り鉄」必携の「乗りつぶし地図帳」も活用しているのだとか。今回のアレンジでは、途中でパッヘルベルのカノンを交えながら、ザ・レヴ・サクソフォン・クヮルテットの一員として、しっとりとして情感豊かな演奏を披露してくれました。
最後の「恋人がサンタクロース」は、松永さん、上野さん、石丸さんが加わって、ぐっと華やかに。松任谷由実さんがこの曲を発表したのは1980年のこと。懐かしさを感じる一方で、曲そのものは今聴いてもまったく古びておらず、とても40年近くも昔の曲だとは思えません。時代を超える名曲です。
和楽器プリンスの音楽会
今週は箏曲プレイヤーのLEO(今野玲央)さん、三味線プレイヤーの上妻宏光さん、おふたりの和楽器界のプリンスにご出演いただきました。
LEOさんはアメリカ人の父と日本人の母を持つ20歳。スラリとした演奏姿がカッコよかったですよね。現在、東京藝大邦楽科に在学しています。東京藝大といえばクラシック音楽の世界ではだれもが知る日本を代表する芸術大学ですが、国立大学だけあって、この大学には邦楽科も設置されています。しかも、一昨年には邦楽器の可能性を開拓するために、現代箏曲専攻分野が新設されました。伝統音楽の楽器というイメージが強い箏ですが、LEOさんのような現代箏曲に取り組む若いプレーヤーが登場することで、また新たな伝統が築かれていくのでしょう。
LEOさんがいろいろな奏法をデモンストレーションしてくれたように、現代箏曲では楽器の使い方も本当に自由で多彩です。このあたりは現代音楽における西洋の伝統楽器の使い方と同様ですね。箏は音を発した後に音程に変化をつけられるところがおもしろいところ。また、無調側を使ったサウンドも印象的でした。不気味なサウンドで、ホラー映画なんかの効果音にも使えるかも!?
上妻宏光さんの津軽三味線もとても現代的で、独創性にあふれています。朝倉さやさんの歌唱、ゆよゆっぺさんのDJとともに、山形民謡「最上川舟唄」を MOGAMIGAWA へとアップデイトしてくれました。これはもう日本や西洋といった区切りを超越した世界音楽といった感があります。最後のAKATSUKI はダンスカンパニーのDAZZLEが加わって、まさに踊るための音楽になっていました。
三味線がアンプやチューナーにつながった「エレキ三味線」になっているのにはびっくりしました。エフェクターを使うと、まるでエレキギター。楽器の見た目とのミスマッチがなんとも言えません。
才色兼備の女性トリオと楽しむ休日
今週はヴァイオリンの川久保賜紀さん、チェロの遠藤真理さん、ピアノの三浦友理枝さんをゲストにお招きしました。それぞれソロやオーケストラで活躍するみなさんですが、その合間を縫ってトリオを組んで、まもなく10周年を迎えます。音楽祭などでソリストが集まった際に臨時のトリオを組むことはよくありますが、このように10年間にわたって続くトリオは決して多くありません。多忙であっても続けられるのは、やはりお互いの相性の良さがあってこそなのでしょう。
3人の共通点は、音楽家ではなく、一般家庭の出身であること。クラシック音楽の世界には、音楽一家に生まれたという方がとても多いように思います。これはバッハやモーツァルトの時代から現代まで変わらない点ですが、どうしても早期教育が求められますので、本人の意思というよりは親の意向で第一歩がスタートします。教育環境や人と人のつながりという面でも、音楽家の家庭に生まれた子が恵まれているのはたしか。しかし、一方で両親ともまったく音楽の世界に縁がなくとも、一流の音楽家へと育っていく例もたくさんあります。遠藤さんが「見知らぬおばあさんから褒められた」ことがプロを目指すきっかけになったとおっしゃっていたように、思わぬ出来事が背中を押してくれることも。人の運命はわからないものです。
「トリオ」とは広く3人のグループを指す言葉ですが、クラシック音楽では今回のような通称「ピアノ・トリオ」と呼ばれる編成、つまりピアノ、ヴァイオリン、チェロの3人の組合せが一般的です。ブラームスのハンガリー舞曲第6番とラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」を演奏していただきました。ラヴェルの作品の原曲はピアノ曲。作曲者自身によりオーケストラ用にも編曲されています。今回の山田武彦さん編曲のトリオ・バージョンでは、トリオならではの豊かな色彩感と透明感をお楽しみいただけたのではないでしょうか。
フィギュアスケートの音楽会2018
今週は恒例の「フィギュアスケートの音楽会2018」。本来であれば録音に合わせて選手が演技するところを、逆に選手が演技する映像に合わせて生演奏をするというのが、この音楽会のおもしろさ。音楽にクローズアップすることで、フィギュアスケートの演技が一段とドラマティックに感じられたのではないでしょうか。選手の動きと音楽の表情がどんなふうに結びついているのか、といったことをつい考えながら見てしまいます。
羽生結弦選手によるショパンのバラード第1番を演奏したのは関本昌平さん。2005年のショパン国際ピアノコンクールで第4位を獲得するなど、輝かしいコンクール歴を誇る実力者です。生演奏であるにもかかわらず、映像に音楽を同期させなければならないという特殊な条件での演奏でしたが、関本さんはこれを「他の楽器とアンサンブルをしている感覚」と表現してくれました。これには納得。しかも音楽の流れに無理がないのはさすが。脱帽するほかありません。
ザギトワ選手の「ドン・キホーテ」はバレエの定番曲。作曲者のミンクスはこの「ドン・キホーテ」をはじめ、「ラ・バヤデール」などバレエ音楽の名曲で知られています。これらは演奏会用のレパートリーというよりは、実際に劇場で踊るための音楽といっていいでしょう。そんな踊りのための音楽と、フィギュアスケートの相性はばっちり。あらためて、バレエとフィギュアスケートの親和性を強く感じました。
ゲストの村上佳菜子さんが演技した映画「マスク・オブ・ゾロ」の音楽は、ジェームズ・ホーナーの作曲。ジェームズ・ホーナーは映画「タイタニック」の音楽でアカデミー賞を受賞するなど、数多くのハリウッド映画で活躍しました。村上さんののびやかで躍動感あふれる演技と、ダイナミックで雄大な音楽が見事に調和していたと思います。
映画黄金期の名曲を楽しむ音楽会
今週は映画音楽の名曲をたっぷりとお楽しみいただきました。いずれも1960年代までの往年の名画ばかり。懐かしさで胸がいっぱいになったという方も多かったことでしょう。若い方であれば「昔の映画にこんな名曲があったのか!」と驚いた方もいらっしゃるかもしれません。
かつて映画音楽にはオーケストラは必須の存在だったといっても過言ではありません。シンセサイザーなど電子楽器が広まる以前の時代に、物語の壮大さや奥深さを伝えるためには、オーケストラのゴージャスなサウンドが最適。名曲は一瞬で観客をドラマティックな世界へと引き込んでくれます。
指揮の原田慶太楼さんがおっしゃっていたように、アメリカにはヨーロッパから渡ってきた作曲家がたくさんいました。『風と共に去りぬ』の「タラのテーマ」で知られる作曲家、マックス・スタイナーもそのひとり。彼は1888年にウィーンで生まれ、音楽の神童として名を馳せ、10代からすでに自作のオペレッタを作曲していました。ウィーンの音楽院ではあのマーラーにも師事しています。しかし、1914年にアメリカへ渡ると、ブロードウェイやハリウッドで活躍して名声を築きます。
「ハリウッド映画以前の最大のエンタテインメントはオペラだった」という考え方からすると、このあたりが、まさにオペラ界からハリウッド映画へと時代が移り行く過渡期だったといえるでしょう。『風とともに去りぬ』の「タラのテーマ」には、どこかオペラの序曲や前奏曲の名残りが感じられます。そもそもオーケストラの音楽で物語の幕を開けるという考え方自体がオペラ的とも言えます。
オーケストラによる壮大なテーマ曲という伝統は、後に「スター・ウォーズ」をヒットさせるジョン・ウィリアムズへと受け継がれます。そのジョン・ウィリアムズのアシスタントを務めたのが原田慶太楼さん。東京交響楽団とともに、豊麗なサウンドを聴かせてくれました。
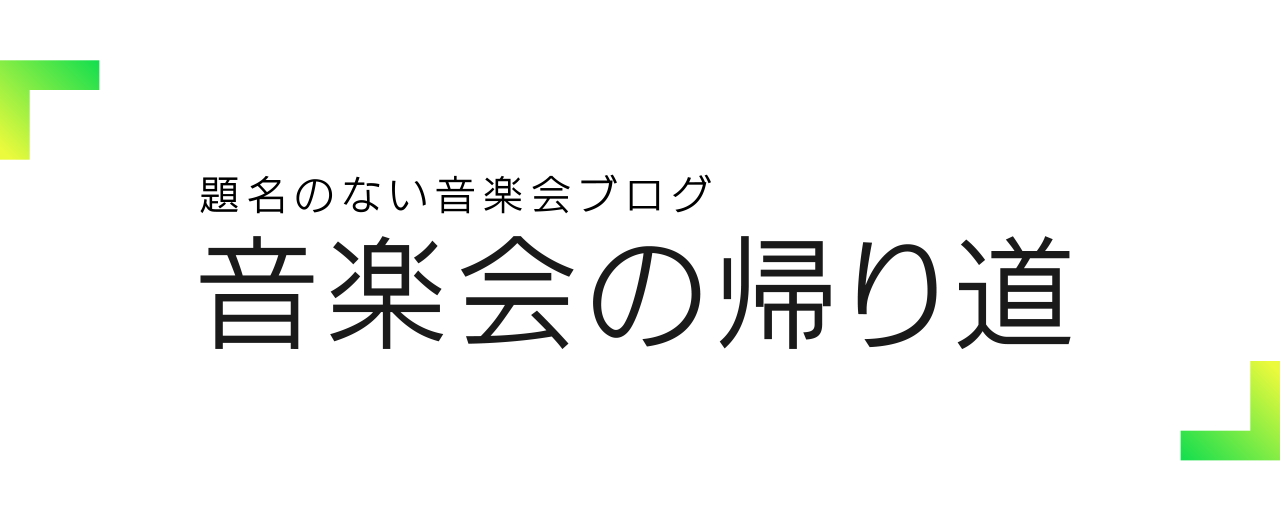
 公式サイト
公式サイト