音楽を聴いていて、ふと「もしこんなことをやってみたらどうなるのかな……」という素朴な疑問が浮かぶことがあります。そんな疑問に日本のトップレベルの音楽家たちが本気でこたえてくれたのが今回の企画。これはびっくりしましたよね。
「もしもボレロの小太鼓を他の打楽器で演奏してみたら」には意表を突かれました。本来、ラヴェルのボレロはずっと小太鼓が同じリズムを刻む曲。そこにいろんな楽器が交代で同じメロディを奏でて、どんどん音色が移り変わるのが聴きどころ。だったら小太鼓が別の打楽器に変わったらどんな曲になるのか。ドラムセット、カスタネット、アゴゴベル、銅鑼、しまいには相撲太鼓まで登場して超ジャンル横断的「ボレロ」が誕生しました。
「もしもメチャクチャ細かい指示が書いてある楽譜を演奏したら?」では、古今の作曲家たちがくりかえし変奏曲の題材にとりあげてきたパガニーニの主題をもとに、川島素晴さんが変奏曲を作曲。「甘く歌うように」とか「とても表情豊かに」というのはわかるのですが、「キュンです ♡ 」とは? 服部百音さんの熱演がすごい! おしまいに登場する蚊が痒そうでした。
圧巻は「もしも漫才の掛け合いを音楽にしたら」。こちらも川島さんの作曲です。サンドウィッチマンの漫才と音楽がぴたりと合致しているのも驚きですが、漫才抜きで聴いてもちゃんと曲に聞こえるんですよね。もともとの漫才にある対話性が音楽として転写されている、ということなのでしょうか。楽器と楽器の対話から音楽が生まれると思えばこれも納得!?
「もしも名曲を逆さまに演奏したら」では、有名な「乙女の祈り」が登場。これを上下反転してみると、すっかり乙女感はなくなり、別の音楽に。まるで乙女が勇敢な戦士に変身したかのよう。意外といい曲になったと思いませんでしたか。
飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)
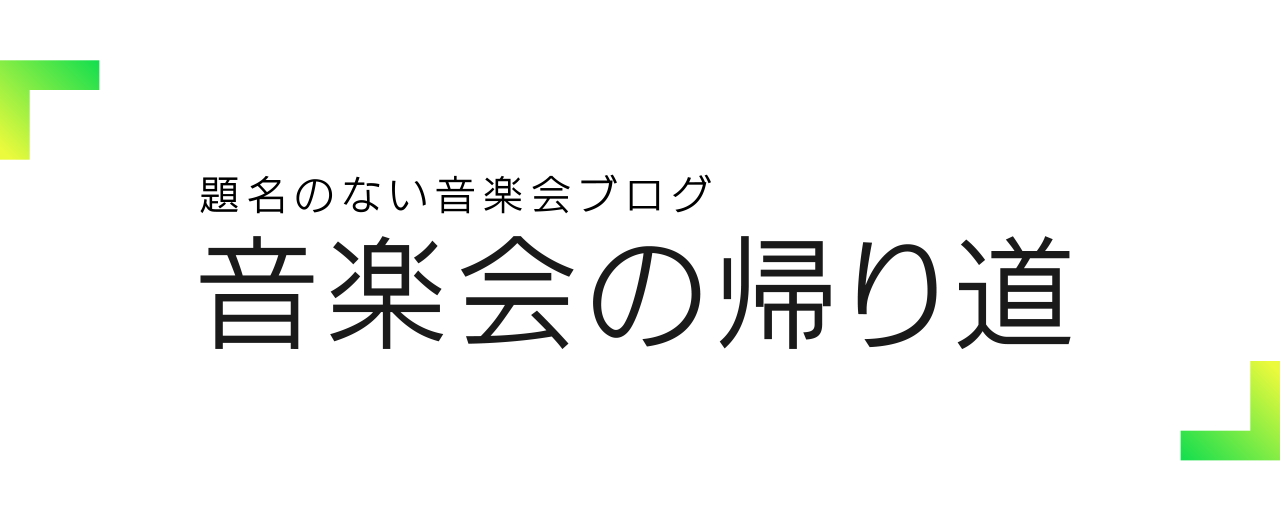
 公式サイト
公式サイト