今週はベートーヴェンとシューマンによる2曲のヴァイオリン・ソナタを、それぞれ三浦文彰さん、五嶋龍さんのふたりのヴァイオリニストの演奏でお聴きいただきました。
「ソナタ」という言葉は、クラシック音楽の世界では最頻出ワードのひとつ。でもその意味はなかなか難しい! 同じ「ソナタ」という言葉でも、時代によって意味が違っていたりするので、わかりづらいんですよね。
ベートーヴェンやシューマンの時代では、「ソナタ」という言葉は、ヴァイオリン・ソナタとか、ピアノ・ソナタといったように、主にソナタ形式で書かれた多楽章の器楽曲に使われます。ソナタ形式については番組内でも説明がありましたが、典型的には提示部、展開部、再現部の3部構成からなる形式で、ときには冒頭に序奏が添えられたり(シューマンのソナタがそうでした)、末尾に終結部(コーダ)が付いたりします。このソナタ形式は古典派やロマン派の時代には大いに重用された形式で、実は交響曲や協奏曲でもこのソナタ形式が採用されています。
なぜ、そんな形式が必要なのか。作曲家は芸術家なんだから、既存の形式なんかに束縛されずに、思ったままに曲を書けばいいじゃないか。そんなふうに感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ヴァイオリン・ソナタや交響曲など、ある程度長さを持った楽曲は、いわば長編小説のようなもの。起承転結があります。定まった形式があると、聴く側はたとえその形式を意識せずに聴いているとしても(ふつうはそうだと思いますが)、音楽が持つストーリー性を耳で追いやすくなります。起承転結を伝えるための、ひとつの有力な方法がソナタ形式といえるのではないでしょうか。
新着記事
月別アーカイブ
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
ヴァイオリン・ソナタの音楽会
旅の思い出の音楽会
音楽家と旅は切っても切れない関係にあります。モーツァルトはその生涯の約3分の1を旅先で過ごしたといいます。旅先で人と出会ったり、見聞を広めることが、新たな創作意欲の源泉となっていたことはまちがいありません。
現代の音楽家にとっても旅は欠かすことのできないもの。人気演奏家ともなれば各地を転々としながら、そこで演奏会に出演することが日常となっています。本日の「旅の思い出の音楽会」では、そんな旅する音楽家たちが、それぞれの思い出の一曲を披露してくれました。
とりわけ興味深かったのがピアニストの金子三勇士さんのお話です。日本人のお父さんとハンガリー人のお母さんの間に生まれ、6歳から単身でハンガリーに渡り、おばあさんの家に住んだという金子さんは、日本語とハンガリー語、そして英語を使い分けることができます。その金子さんはフランスで聴いたドビュッシーの「月の光」の演奏に、「フランス語の発音のような解釈」を感じたといいます。音楽は言葉の壁を超えて伝わる芸術ではありますが、それでもフランス語を話すから表現できるフランス音楽、ドイツ語を話すから表現できるドイツ音楽、日本語を話すから表現できる日本音楽といった領域が、たしかにあるのでしょう。
三浦文彰さん本人の演奏で「真田丸」メインテーマを聴けたのも嬉しかったですね。作曲は服部隆之さん。これは名曲だと思います。大河ドラマにヴァイオリン協奏曲スタイルの作品は意外な感もありましたが、ヴァイオリンの鋭く切れ込むような音色は、どこか凛然とたたずむ武士を連想させるようにも感じます。ピアノ伴奏版で聴くと、原曲のオーケストラ版とはまた一味違ったクールな雰囲気があって、新鮮な感動がありました。
スポーツの祭典の音楽会
いよいよリオデジャネイロ・オリンピックが始まりますね。今週は「スポーツの祭典の音楽会」。オリンピックやワールドカップを彩る名曲が演奏されました。
オリンピックでは毎回独自のファンファーレが作られていますが、まっさきに思い出されるのが、ジョン・ウィリアムズ作曲によるロサンゼルス・オリンピックのための「オリンピック・ファンファーレとテーマ」。大会が終わってもなお演奏され続け、そのままファンファーレの定番曲として定着した感があります。「スターウォーズ」や「スーパーマン」など、数々の映画音楽で名作を生んできたジョン・ウィリアムズですが、このファンファーレもまた彼の代表作として残る一曲ではないでしょうか。
コープランド作曲の「市民のためのファンファーレ」も同じくアメリカが生んだファンファーレの名曲です。威厳と高揚感にあふれ、この曲自体、オリンピックのファンファーレとして演奏されてもおかしくないような雰囲気を持っていますよね。コープランドは後にこのファンファーレの主題を交響曲第3番の終楽章で再利用して、さらに大規模な音楽に仕立てています。本来ブラスバンド向けのファンファーレを、フル・オーケストラの交響曲にしたらどうなるのか。ご興味のある方はぜひ聴いてみてください。
サッカーの世界では、なんといっても、ヴェルディ作曲のオペラ「アイーダ」に登場する「凱旋行進曲」が有名です。ヴェルディの母国イタリアのみならず、世界中のサポーターたちがスタジアムでこのメロディを歌っています。
「アイーダ」で舞台となるのは古代エジプト。「凱旋行進曲」は第2幕のラダメス将軍率いるエジプト軍の勝利を称える場面で華々しく演奏されます。しかし、その後、ラダメス将軍は祖国の栄光よりも許されざる愛を選び、地下牢に閉じ込められて現世に別れを告げます。華やかだけど、結末は苦い。勝利とはひとときのものだからこそ、「凱旋行進曲」の壮麗さが際立つのかもしれません。
冨田勲の音楽会
今年5月5日、84歳で亡くなった作曲家の冨田勲さん。テレビや映画音楽の作曲家として、またシンセサイザー音楽の先駆者として、音楽界に大きな足跡を残しました。近年もバーチャルシンガーの初音ミクとオーケストラを共演させるなど、衰えることのない旺盛な創作意欲を発揮していました。
テレビ音楽で懐かしかったのは「新日本紀行」の音楽。これは名曲ですよね。尺八の音色が日本の原風景を思い起こさせます。「今日の料理」のテーマ曲はあまりに有名ですが、冨田勲作曲であることをご存じなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。急遽、番組のテーマ曲を作らなければならなくなり、たまたまそこに居合わせたのがマリンバ奏者とパーカッション奏者だったので、それに合わせて曲を書いたという逸話が知られています。あの軽快なマリンバのサウンドは偶然の産物でもあったんですね。
シンセサイザー音楽家としての冨田さんは日本よりも先にまずアメリカで高い評価を受けました。「月の光」「惑星」「火の鳥」など、クラシックの名曲をシンセサイザーで再創造し、だれも聴いたことがない音の世界を切り拓きました。最初期のシンセサイザーは楽器というよりは機材といったイメージが近いでしょうか。冨田さんがアメリカにシンセサイザーを発注したところ、電話の交換台のような装置が送られてきて、税関に楽器だと認めてもらえずに引き取るまでに苦労をしたといいます。
番組では初音ミクとオーケストラの共演が実現しました。初音ミクの歌唱部分は、あらかじめ録音した歌を再生してそれにオーケストラが合わせたのではありません。指揮者の棒に初音ミクの側が合わせています(もちろん人間の操作を介在してではありますが)。指揮台の横に2次元バーコードのような物が配置されていたのは、CGを合成させるためのマーカーなのだとか。こんなふうに舞台とCGの合成ができるんですね。可能性の広がりを感じます。
若き俊英たちの音楽会
今、日本の音楽界からは若くて優秀なアーティストが次々と登場しています。今週の「若き俊英たちの音楽会」では、3組のアーティストがそれぞれの個性を発揮してくれました。
ピアノの實川風(じつかわ・かおる)さんは昨年のロン=ティボー=クレスパン国際コンクールで第3位(1位なし)に入賞した新鋭です。ベートーヴェンの「ワルトシュタイン」、本当にすばらしい演奏でしたよね。細部まで彫琢された緻密な演奏でありながら、音楽全体に勢いが感じられる堂々たる本格派のベートーヴェンでした。
実は収録より前に、東京・渋谷で實川風さんのリサイタルが開かれまして、そちらでも「ワルトシュタイン」が演奏されていました。プログラムにはほかにショパン、リスト、ドビュッシー、現代のピアニスト兼作曲家のヌーブルジェらの作品も並べられ、実に多彩。音楽的な視野の広さも感じさせます。将来が、というよりは、すでに次のリサイタルが楽しみなピアニストといってよいかもしれません。
篠笛の佐藤和哉さんは、佐賀県の「唐津くんち」のお囃子が最初の笛との出会いだったそうです。NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」主題歌のモチーフとなった佐藤さんの「さくら色のワルツ」には、日本人の琴線に触れるようなノスタルジックな手触りと、今風の洗練されたテイストがともに感じられたのではないでしょうか。
驚きの打楽器アンサンブルを披露してくれたのは Ki-Do-Ai-Raku のみなさん。4人全員がスネアドラム(小太鼓)を叩くと聞いて、「うーん、なんだか変化に乏しい地味なアンサンブルになりそうだな」と思っていたら、まさかあんなにはじけたパフォーマンスを見せてくれるとは! スネアドラムにいろんな種類の奏法があるということにもびっくり。スネアドラムをササッと裏返す場面がありましたが、あんなふうに直接スネア(響き線)をスティックで叩くこともできるんですね。想像以上に表現力に富んだ楽器であることを再認識しました。
ボサノヴァを愛する音楽家たち
今週は「ボサノヴァを愛する音楽家たち」。ボサノヴァって、聴いていて本当にさわやかな気分になりますね。ボサノヴァにはぜんぜんなじみがないという方も、「イパネマの娘」や「マシュ・ケ・ナダ」といった名曲は必ずどこかで耳にしているのではないでしょうか。小野リサさんのささやくような歌声に、龍さんのヴァイオリンが加わった「イパネマの娘」がとても新鮮でした。
新鮮といえば、津軽三味線奏者の上妻宏光さんと小野リサさんの共演にも驚きました。もともとは武器だったという素朴な民族楽器「ビリンバウ」と三味線に共通点が多いということからコラボレーションが実現したそうですが、不思議なほど違和感がありません。
ボサノヴァの発声法について、小野リサさんは「恋人に語りかけるように」と説明してくれました。ボサノヴァに特徴的な軽くやさしい発声は、たとえばオペラのような強靭で輝かしい発声とは正反対といってよいでしょう。でも、オペラ・アリアの名曲も多くは恋人に向けて愛を歌っているんですよね。同じことを目的にしているのに、表現の方法がまるで違うところがなんともおもしろいと感じました。
ポルトガル語のbossa nova をそのまま直訳すれば「新しいこぶ」。この言葉が生まれた当時のニュアンスを汲むと、「新しい天性、しゃれた癖」といった意味を表すそうです。ボサノヴァとは「ブラジルの踊りサンバに都会的なジャズの感覚をとりいれ、ジャズ・サンバともいわれる」(「新編音楽中辞典」より)。この音楽が誕生した20世紀前半のブラジルでは、おしゃれで都会的な音楽とみなされていたようです。ボサノヴァのおしゃれで都会的といったイメージは、21世紀の日本でもほとんど同じように共有されていますよね。これってスゴいことだと思いませんか。
リズム歌謡の音楽会
「東京ブギウギ」が発表されたのは昭和22年のこと。自分が生まれるよりもはるかに昔の流行歌です。でも、聴くと知っているんですよね。本日の「リズム歌謡の音楽会」では、エリック・ミヤシロさんの編曲したバージョンでお聴きいただきましたが、古いのに古びていないといいましょうか、とてもカッコいい曲だと感じました。いま昭和歌謡に注目する動きがあるというのもわかるような気がします。
それにしても「リズム歌謡」の変遷をたどった輪島裕介さんの解説には目からウロコが落ちっぱなしでした。日本でブームを作ったマンボ、カリプソ、ツイスト、ドドンパに、そんな背景があったとは。昭和31年のマンボブームは、ペレス・プラード楽団の来日がきっかけだったといいますから、本場のマンボに触れたおかげだったわけですね。たまたまですが、同じ昭和31年に第1回のイタリア歌劇団来日があり、日本にオペラ文化を定着させる契機となったと言われます。やはり本物との出会いが、新たな文化を生み出すものなのでしょう。
もうひとつおもしろかったのは、ドドンパが日本で生まれたリズムだという点。マンボはキューバ、カリプソはカリブ、ツイストはアメリカ由来のダンスですが、ドドンパはなんと日本製なんですね。「ドドン、パッ! ドドン、パッ!」というコンガのリズムが、盆踊りに通じているという解説がありましたが、言われてみるとすごく納得できます。マンボとかカリプソはどんなに練習してもサマになりそうにないですが、ドドンパだったらカッコよく踊れるかも! 一瞬、そんな気の迷いを起こしました。
ところで「マンボNo.5」で知られるペレス・プラードは1916年12月11日に生まれています。つまり、今年生誕100年。もしかすると世界的にマンボ・イヤーになるのではと期待しているのですが、どうなんでしょうね。
ニュースタンダードの音楽会
ポピュラー音楽の世界で使われる用語に「スタンダード」という言葉があります。辞書をひくと「恒久的なレパートリーとして広く親しまれる名曲のこと、特にポピュラー・ソングで使われる」といった説明が乗っています。ジャズでいえば「A列車で行こう」とか「枯葉」「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」といった曲名がまっさきに挙がるでしょうか。
本日の「ニュースタンダードの音楽会」では、新しいスタンダード、つまり70年代から80年代の洋楽ヒットナンバーを最新のアレンジでお聴きいただきました。マイケル・ジャクソンやプリンスのヒットナンバーもすでに30年の時を経ているのですから、もはや「スタンダード」になっているんですね。
時代を代表するヒット・ナンバーがスタンダードになるということは、いいかえれば本人以外のアーティストたちによって演奏され続けているということ。だれかが楽曲に新しい命を吹き込まなければ、「スタンダード」は誕生しません。今回は時代の最先端を行くアレンジャーたちが、「今のマイケル・ジャクソン」や「今のプリンス」を聴かせてくれました。「ビート・イット」がゴージャスに生まれ変わっていたり、「パープル・レイン」に繊細で抒情的な彩りが添えられていたり……。懐かしくて、しかも新鮮であるというのが、「ニュースタンダード」を聴く楽しさでしょうか。
エリック・ミヤシロ EMバンドの演奏もカッコよかったですね。あのスカッと抜けるようなトランペットの高音はどうやったら出せるんでしょう。サックスやトロンボーン、ハーモニカなど、ソロの聴きどころも満載でした。
同じ曲をいろんなアーティストがくりかえし演奏して、スタンダードになる。このプロセスはクラシック音楽が生まれるプロセスとまったく同じです。今スタンダードと呼ばれる名曲が、さらにあと100年演奏され続けると、クラシックと呼ばれるようになるのかもしれません。
山田和樹と日本一の合唱団の音楽会
今週は「山田和樹と日本一の合唱団の音楽会」。
社会人から高校生まで、それぞれの世代で輝かしいコンクール歴を誇る合唱団を、世界的指揮者の山田和樹さんが指揮したらどうなるのか。そんな興味深い試みが実現しました。
山田和樹さんといえば、モンテカルロ・フィル芸術監督(9月~)、スイス・ロマンド管弦楽団首席客演指揮者、日本フィル正指揮者など、各地のオーケストラで要職に就く一方で、東京混声合唱団音楽監督も務めています。トップレベルの指揮者によるリハーサル風景を見られるという意味でも貴重な機会でした。
山田さんがどんな指導をするのか、事前にまったく予想がつかなかったのですが、いざ始まってみると短時間のなかで次々とリクエストを出して、作品に命を吹き込んでいきます。ほんの一言だけの指示でも、一気に音楽の表情が変わるのには驚かされました。山田さんの指導には「もっと花の香りがするように」といった比喩的な示唆もあれば、具体的な歌い方を指示するものもありました。そして、これらをただちに音楽に反映できてしまうのも、合唱団の実力があってこそ。教える側と教わる側がぴたりとかみ合って、密度の濃い練習になっていたと思います。
以前、山田さんにインタビューをしたときに「オーケストラの音は指揮者によってまったく変わる。不思議なことに、指揮台に立っただけでもその人の音が出てくる」といったお話をうかがいました。もしかすると、同じことが合唱団についても言えるのかもしれません。山田さんが合唱団の前に立った時点で、すでになにか化学反応が始まっているような気がするんですよね。
豊島岡女子学園コーラス部、東京フラウエン・カンマーコール、コンビーニ・ディ・コリスタ、どの団体にも劇的な変化が感じられました。特に印象的だったのが豊島岡女子学園コーラス部による木下牧子作曲「おんがく」。十代ならではの鋭敏な感受性がそのまま曲に直結しているようで、胸に迫るものがありました。
久石譲が語る歴史を彩る6人の作曲家たち 後編
今週は先週に続いて作曲家・久石譲さんにクラシック音楽の歴史をガイドしていただきました。ペンデレツキ、スティーヴ・ライヒ、ジョン・アダムズといった現代の作曲家たちの作品が演奏されましたが、いかがでしたか。先週のベートーヴェンやワーグナーとはまったく違った発想で作品が書かれているのを感じていただけたかと思います。
特にペンデレツキの「広島の犠牲者に捧げる哀歌」には、「うーん」と腕組みをしてしまった方も多いかもしれません。龍さんと久石さんの会話にあったように、まるでホラー映画に出てくるような不気味な音楽と感じてもおかしくはないでしょう。事実、ペンデレツキのみならず、20世紀の前衛音楽がホラー映画に使用されることは珍しくありません。
「広島の犠牲者にささげる哀歌」はトーン・クラスターと呼ばれる新しい表現方法を使った作品として知られています。一定の音域の間にある密集した音の群をいっせいに鳴らすのがトーン・クラスター。美しいハーモニーとは別世界の斬新な音が出てきます。作曲家たちは「これまでに聴いたことのない音」を追い求め、このようなかつてない表現方法を次々と生み出してきました。
そういった知的な音の探求は今もずっと続いてはいるのですが、一方で技法があまりに先鋭化すると、一般の聴衆の共感を得られなくなるという大きな問題が出てきます。新しいけれども、多くの人が楽しめる明快な音楽はないものか。そんな疑問もわきますよね。そこで人気を獲得したのがライヒらのミニマル・ミュージック。1960年代から70年代に一世を風靡し、その後、ジョン・アダムズら次世代の作曲家たちがこの手法を独自に発展させています。
まさに今、2010年代にも作曲家たちは次々と新作を発表しています。そのなかには前衛的な作風の延長上にある人もいれば、ミニマル・ミュージック的なスタイルの人もいますし、民族音楽の要素を取り入れる人、伝統回帰を唱える人、ポスト・モダンと呼ばれる潮流に属する人などがいて、多種多様の音楽が同時に生み出されています。その意味では現代を「○○主義音楽の時代」と一言で表すことは困難です。たぶん、今がどんな時代なのかは、これから何十年も経った後にわかることなのでしょう。
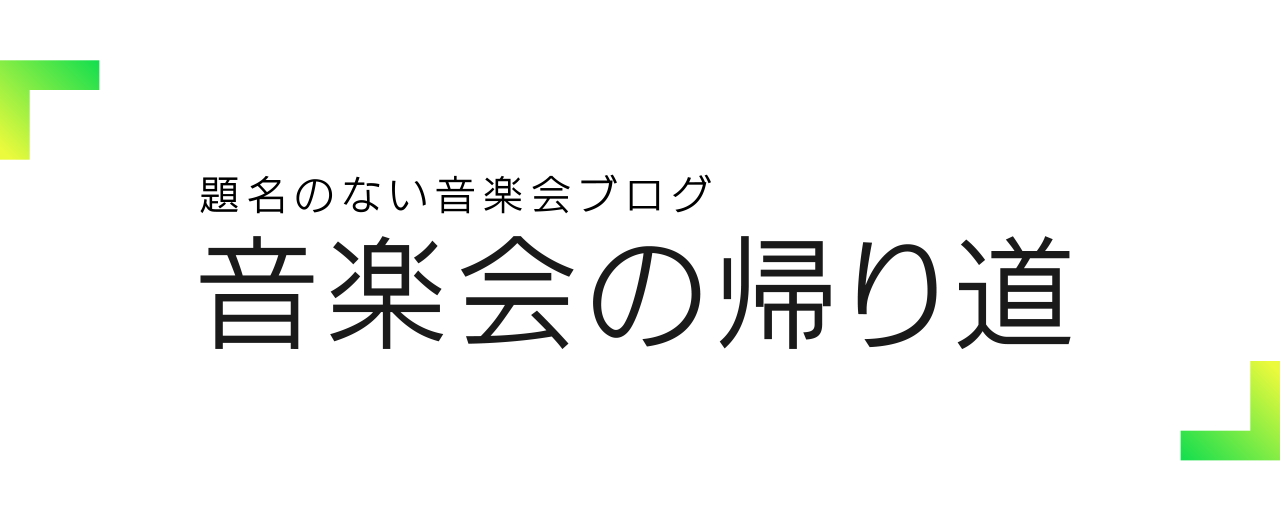
 公式サイト
公式サイト