今週は世界水泳選手権2023福岡大会の応援企画として、元競泳日本代表の松田丈志さんをお招きし、音楽と水泳における呼吸(ブレス)の大切さについて迫ってみました。
まずは松田丈志さんとフルート奏者の多久潤一朗さんが、どちらの息が長く続くか、コップにストローを入れて対決したところ、多久さんがよもやの勝利……というか、反則勝ちとでもいうべきでしょうか。管楽器奏者ならではのテクニック、「循環呼吸」を用いて悠々と息を吐き続けてくれました。「鼻で吸った息を頬にためて、頬の筋肉で空気を押し出す」というのですが、説明を聞いてもできる気がしません。
一曲目の「ultra soul」では、その多久さんのフルートが多彩な奏法をくりだします。突風のような音を出すのは「ジェットホイッスル」。いろいろな曲で使われますが、たとえばブラジルの作曲家ヴィラ=ロボスには、その名も「ジェットホイッスル」という作品があります。音が連なる長いフレーズでは「循環呼吸」を活用。息を吸う音は聞こえましたが、音楽は実に滑らかで、つなぎ目が感じられません。さらには楊琴(ヤンチン)風、尺八風、ビートボックス風など、驚きの奏法のオンパレード。フルートって、こんなにいろいろな音が出せるんですね。
現在大活躍中のバリトン、大西宇宙さんは、「オー・ソレ・ミオ」でたっぷりとしたロングトーンを披露してくれました。深くまろやかな美声を聴くと、この歌声にいつまでも浸っていたいと思ってしまいます。オペラでもしばしばこういったロングトーンが客席を沸かせます。
おしまいは林周雅ストリングスによるモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」。弦楽器のアンサンブルであっても、こんなにも呼吸が大切な役割を果たしていたんですね。タイミングを合わせるだけではなく、音色や音量など、音楽のニュアンスまで息で伝えているとは。驚きました。
飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)
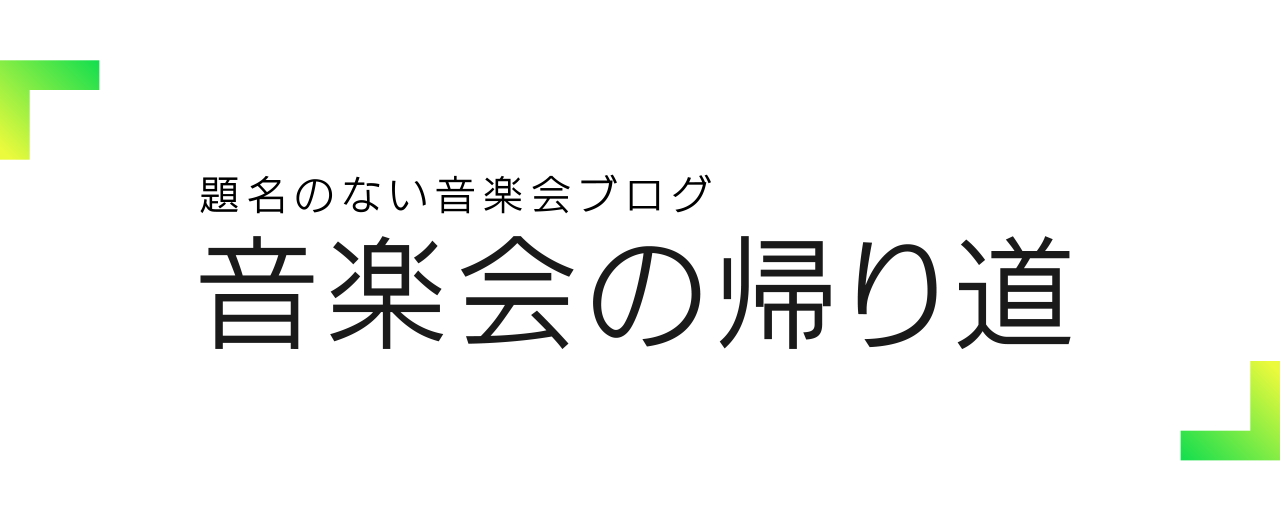
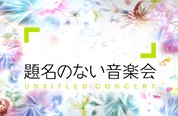 公式サイト
公式サイト