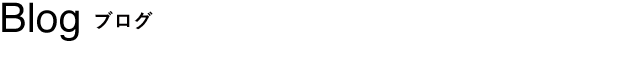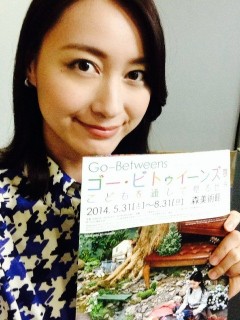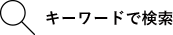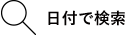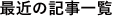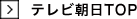- トップ
- ブログ
- 扉を開けて
- 2014年08月28日
子どもの頃、好んで見聞きしていたもの、親しんでいたものを、
大人になってから振り返ると「あれ?こんなだっけ?」と
意外な発見をしたり拍子抜けしたりぞっとしたり、
全く違ったものに見えることってありますよね。
私の場合、アーティストの「大黒摩季さん」もそのひとつ。
小学生の頃流行していた大黒摩季さんの力強い歌声と熱を帯びた楽曲、
大好きでした。
カラオケでも歌ったし、「熱くなれ」は運動会の応援歌にもなって、
みんなで大合唱もしていましたね。
そんな大黒摩季さんのかつての曲たちが不意に懐かしくなって聴いてみたんです。
中でも好きだった、「夏が来る」。
やっぱり小さいころに覚えた曲ってイントロを聴けばにょきにょき記憶が蘇って
歌詞も思い出してくるんですよね。CDに合わせて口ずさんでいたんですが・・・
むむむ・・・ これは・・・。
改めて聴いていると、
何とも生々しいんです。歌詞。
歌われているのは、同年代の友人が結婚したり、
家族からのプレッシャーも感じる中で覚える
女性の焦り、諦め、皮肉、それでも花を咲かせたい女心、ロマンチズム・・・。
恐らく当時アラサーだった大黒さんが綴る等身大のむき出しのホンネが
溢れに溢れているわけです。
あんなに爽やかだと思っていた「ら・ら・ら」も、
よくよく歌詞を聴くとアラサー女子の現実を見事に表現していて
リアルに目に浮かぶようで・・・。
よくもまぁこんな歌詞を、小学生が喜々として歌い上げていたなと。
もうあの時のようには歌えなくなっちゃったよ。
そんな何とも言えない思いをぶら下げながら、先日見に行ってきました。
「ゴー・ビトゥイーンズ展 こどもを通して見る世界」。
森美術館で、今月末まで開催中。
Go between.=行き来する。ということ。
「ゴー・ビトゥイーンズ」というのは、
英語が不自由な両親の代わりに様々な用事をこなす子どもたちをさすものとして
ニューヨークの移民を取材した写真家の方が創った言葉だそう。
文化の間、現実と想像の世界の間など、様々な境界を行き来する「媒介者」として子どもたちを捉え、
現代の子どもたちを取り巻く問題や、子どもの本質的な創造性など、
様々な角度から「子ども」を切り取るアートを集めた展覧会なんです。
これはそのうちのひとつ、
山本高之さんの「東京、どんなじごくにいくのかな」という作品なんですが、
子どもたちがいろんな「地獄」を想像して、段ボールやセロファンで具現化し、
それをプレゼンする、というもの。

「好きなひとのことばかり考えてる人が行く地獄。
ペラペラになってアイスクリームのトッピングになって鬼に食べられ続ける」とか、
「寝てばっかりいる人が行く地獄。
上から伸びてくる手にずっとこちょこちょをされ続ける」とか・・・。
思い当たる節があるものもいっぱいありドキッとしましたが(笑)、
なんとも可愛らしくて、笑みがこぼれます。
リネカ・ダイクストラさんの作品は、パブロ・ピカソの「泣く女」を見て
子どもたちが何で彼女は泣いているのかを口々に議論するという映像。
「彼女は幽霊でたった今それに気づいた」「手に持っているティッシュのようなものはラブレター」・・・
予想だにしない方向にイマジネーションは膨らんでいきます。
子どもって本当に、どこまでも転がっていく想像力と発想を持っていますよね。
一方で子どもたちは、
時代や環境に翻弄される中で、思いもよらぬ大人の顔や孤独を抱えていることもあって。
展示されていた写真や映像作品の数々に捉えられた子どもたちの瞳の奥の表情に
なんどもハッとさせられます。
それを無邪気に乗り越えようとする姿に、果てしない子どもの世界を再確認し、
同時に大人の責任についても考えさせられました。
昔は自由に行き来していたのに、
扉の前に本やらガラクタやらがどんどん積み上がって中に入れない、
それどころか存在すら忘れてしまっている「開かずの部屋」。
そんなスペースが、きっと心の中にはたくさんあるんでしょうね。
年齢を重ねれば重ねるほど人生経験は増えるけど、
それだけで大人は子どもより豊かで偉いなんて、言えないんだろうな。
いつか自分に子どもができたら、親子でありながら
ひとりの人間として対等に尊重して学びあう、
そんな関係であれたらいいな、なんて感じました。
そしたらいつか、積み上げてあるものがちょっとずつ片付いて、
埃まみれの扉が開いて、
大黒摩季さんの曲もあの時の感覚で聴けるようになるかもしれません、ね。
- 2017年12月 (1)
- 2017年2月 (2)
- 2016年12月 (2)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (4)
- 2016年8月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (5)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (3)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (2)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (4)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (3)
- 2014年12月 (5)
- 2014年11月 (3)
- 2014年10月 (6)
- 2014年9月 (4)
- 2014年8月 (6)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (4)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (2)
- 2014年3月 (5)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (6)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (5)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (8)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (2)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (3)
- 2012年9月 (3)
- 2012年8月 (4)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (3)
- 2012年5月 (3)
- 2012年4月 (3)
- 2012年3月 (5)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (6)
- 2011年12月 (4)
- 2011年11月 (4)
- 2011年10月 (7)
- 2011年9月 (8)
- 2011年8月 (3)
- 2011年7月 (2)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (3)
- 2011年4月 (1)