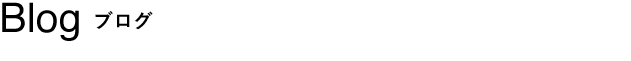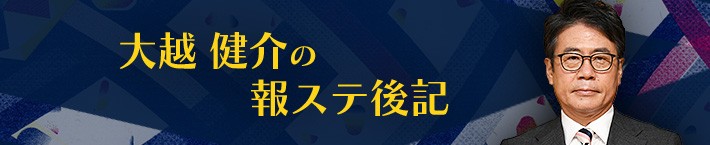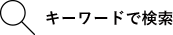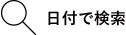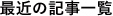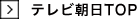- トップ
- ブログ
- 多感な春
- 2025年03月23日
妻はしばしば衝動的に断捨離を敢行するのだが、ヨガに凝っていた時に使っていたピンク色のマットを捨てるのは思い止まったらしく、今は部屋の真ん中に敷きっぱなしになっている。おかげで、僕がストレッチングをするときに役に立ってくれるのだが、それ以上にコタローが重宝している。どうやらその感触が好きなようで、好きなあまりツメを研いだりもするので、せっかくのマットはあちこちボロボロで無残なことになっている。
この土日は、ポカポカを越えて汗ばむほどの陽気になった。お気に入りのマットで横になり、日光にお腹を向けるコタローは、スマホのカメラを向ける僕に向かって「文句ある?」とでも言いたげだ。わが世の春、コタローの春。
お天気に誘われて僕も散歩の脚が軽くなる。寒い冬の間は、「無理してもし風邪をひいたら皆に迷惑がかかる」などと都合よく理由をつけ、家でゴロゴロしていたのに、家の外に一歩を踏み出すのが楽しくなる。そうなると1時間では足りなくて、2時間程度は平気で歩く。距離にして10キロくらいを一気に歩く。生まれてから一度も花粉症に悩まされたことのない幸運を噛みしめながら。
ソメイヨシノが開花する季節になった。僕の散歩コースには、自分なりの各種の「標準木」というのがあって、その開花で僕は季節を測る。1月に黄色い蝋梅(ろうばい)が咲き出すのを経て、やがて2月から3月にかけて紅白の梅が咲く。そして、桜の季節に入るまでの短いバトンをつなぐのが、僕の場合、近くの公園にあるコブシの木である。
そのコブシの「マイ標準木」の枝には、まだ蕾(つぼみ)の状態のものと、白い花びらがすっかり開いたものが混在していた。桜ほどの「満開」感には乏しいが、それでも、この花の趣もなかなかのものだと思う。青空に大きく張り出した枝ぶりは見事で、その元に吸い寄せられるようにして人が集まっていた。
歩きながら季節を感じるのは楽しい。そして長い時間を歩いていると、頭の中にはさまざまなことが駆け巡る。
この週は、メジャーリーグの開幕シリーズが東京ドームで行われた。日本できっとホームランを打ってくれるだろうという期待に、まるで約束したかのように応えてくれる大谷翔平という男は、やはり怪物としか言いようがない。そしてアジア最終予選を戦っているサッカー日本代表は、史上最速でワールドカップ出場を決めた。有言実行の彼らは、ベスト8の壁などたやすく飛び越えて、本当に世界の頂上の戦いを見せてくれるのかもしれない。
人間が持つ可能性を限界まで見せてくれるスポーツは、僕にとって、とてつもない魅力に溢れた世界だ。「いつも難しそうな顔をしているくせに、スポーツコーナーになると表情が一変しますね」とよく言われるが、こればかりは隠しようがない。
だが、希望に満ちたニュースは多くないのが現実だ。むしろ、深く堀れば掘るほど暗い気持ちになるニュースが目立つ。
ウクライナはどうなる?侵略をした側のロシアの、いやプーチン大統領のひとり勝ちとなってしまうのか。いま進んでいる停戦交渉は、侵略された側のウクライナに屈辱と我慢を強いるだけのものにならないか。
ガザはどうなる?2か月に及んだ停戦は事実上破綻してしまった。イスラエル軍が空と地上の両方から、再び爆弾の雨を降らせている。ハマスのテロリストを掃討するという大義名分は、罪のない子どもの命を奪うことすら正当化するのか。まだその蛮行を繰り返すというのか。
ウクライナにしてもガザにしても、勇んで仲介に入ったアメリカ・トランプ大統領はすっかり手を焼いている。いや、本人は手を焼いていると感じてはいないのかもしれない。そもそも仲介の労を取るにふさわしい公平さを、彼は持ち合わせていないように見える。現状を追認してとりあえず「落ち着かせる」ことが彼のできる限界であり、それをもって、ノーベル平和賞に値すると自画自賛するのだろうか。
確かに弱肉強食は生き物の常だろう。だが、せめて生き物の中でも飛びぬけて高度に進化した人間だけは、本能のみにとどまらない、互いに助け合う「平和」という物語を紡いでいくべきではないのか。少なくとも日本の決定的敗北で幕を閉じた第二次世界大戦以降の世界秩序は、そうして作られてきたはずだ。それなのに、ウクライナとガザの惨状は、そうした最後の一線すら、簡単に破られてしまうことを示しているかのようだ。
季節を感じ、軽やかに散歩に出たはずが、帰るころにはすっかり考えごとだらけになってしまった。
息子が子どもたちを連れて遊びに来た。6歳の女児と2歳の男児。ケタケタとよく笑う。2歳の男児は食欲旺盛な子で、お椀に盛ったうどんを美味しそうに、文字通り「頬張る」ように食べる。しかも手づかみで(じいじ注・この年頃では無理もありません)。
横で世話を焼くばあば(妻)は、うどん以外にもおかずを食べさせようと、あれこれ口元に持っていくが、6歳のお姉ちゃんは「もうお口がいっぱいだから無理だよね!」と言いながら、さらにケタケタケタケタと笑う。
この平和な時間が永遠に続くことを願う。だが、徳永有美アナウンサーがインタビューした歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏の話を聞くと、それは楽観的過ぎる気がする。
ハラリ氏によると、トランプ氏のような型破りの指導者はこれまで歴史上に何人も現れたという。それでも世界がこうして存在しているのは、人間社会がその混乱を克服してきたからだが、本当の混乱はこれからだ。その主役は、ほかならぬ人間が作り出してきたAIであり、AIの高度な発達は、すでに人間のコミュニケーションの主導権を奪いつつあるという。だが、コミュニケーションによって信頼を築き上げる人間特有の能力は極めて大きいとも、ハラリ氏は指摘する。その力を最大限発揮すれば、人間はこれからも人間らしくいられると信じたい。
コタローの「我が世の春」に始まって、人類とAIの共存まで考える、何とも忙しい1日となってしまった。だが、僕らはそれほど振れ幅の大きな時代を生きている。小さな日常を大事に、しかし大局的な世界観も失わずに、確かに日々を生き、仕事をしていくしかない。
(2025年3月23日)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)