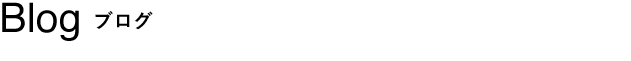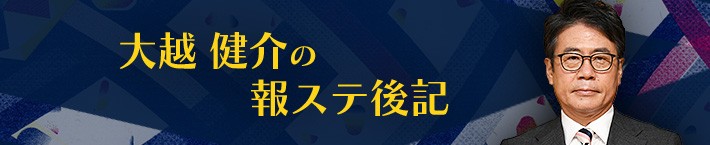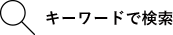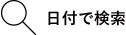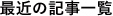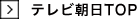- トップ
- ブログ
- 政治の底が抜けないために
- 2025年03月17日
この気持ちをどう表現したらいいかと、問題の発覚以来ずっと考えてきたのだが、今の時点でしっくり来るのは、「ドン引きしてしまった」という言い方かもしれない。燃えるような怒り、というのもオーバーな気がする。悲しい、というのもちょっと違う。裏切られた、というのは近い感じがするが、ぴったりではない。少なくとも僕の感覚としては。
「ドン引きしてしまった」のは、石破首相の商品券配布の問題である。3月3日、当選1回の自民党議員を公邸に招いての食事会の際、10万円分の商品券をおみやげとして配ったというものだ。商品券は石破事務所が事前に議員会館の各部屋を回って配布したそうで、多くの議員はのちに気付いて返却したと話している。
僕は石破茂さんという政治家と、打ち解けてじっくりと話したことはない。だが、インタビューという公式の場で何度も向かい合っていると、おのずとその人柄は分かる。少々こだわりの強い所があるが、正直な人ではある。言語明瞭・意味不明燎な発言に慣れていくのが政治家の常だが、この人はそれが比較的少ないと感じる。
それは時に永田町のムラ社会(特に自民党)からは異端視されることもあったし、実際、仲間を集めて群れを作り、派閥の領袖として勢力を拡大するというこの世界の習いに、石破さんは馴染まなかった。その石破さんが総理総裁になったのは、自民党の変革の象徴としての出来事だったかもしれないし、党の生存本能が発するぎりぎりの防衛本能のなせる業だったかもしれない。
政治資金規正法のグレーゾーンだ。政治活動にあたって議員個人に寄付をすることは法律上、禁じられている。しかし、石破首相はあくまで、夏の衆議院議員選挙のねぎらいの意味であり、政治活動ではないと主張している。先輩のポケットマネーで後輩たちに夕食をご馳走し、ついでにおみやげもはずんじゃった、そういう会食ならよくある話でしょ、というわけである。
これに対して、公費で維持管理される首相公邸という場所で開かれたことや、石破さんが図らずも認めている通り、「党総裁」として新人議員を集めた事実に鑑みれば、政治活動以外の何ものでもないという見方は当然成り立つ。
しかも、商品券の10万円相当という金額は、果たして社会通念上、おみやげで済むかという根本的な問題がある。普通はないだろ、それは。
このニュースの一報が入ってきたのは、13日木曜日の放送1時間半前くらいの時間帯だった。他社のスクープである。番組スタッフの誰もが、これはトップで扱わなければならないニュースだと直感した。特ダネを抜かれて悔しがる前に、しっかり取材をして追いかけなければならない。
デスクの指示が飛び交い、あちこちから取材報告が入る。番組開始が刻々と迫る中、ようやく事実関係の確認が取れ、ニュース冒頭に突っ込むことになった。そして、「こんばんは。報道ステーションです」という挨拶に続いて、僕は「政権を大きく揺るがすようなニュースが入ってきました」と、自身の言葉でリードを切り出した。
「政権を大きく揺るがす」という言葉が間違っていたとは、決して思わない。事実、翌日には連立を組む友党の公明党から「耳を疑った」(斉藤鉄夫代表)という声が上がったし、野党からは当然のことながら総スカンを食らった。足元の自民党からも、公然と「石破首相は退陣すべきだ」との声が上がった。
だが何と言うのだろう。石破批判の声は、文字にすれば勇ましいが、いまひとつ熱量が小さいと感じるのは僕だけだろうか。政権を確かに揺るがしてはいるのだが、なんだか、揺れをそのまま放置しておこうという空気までも、同時に存在しているような。
この不思議な空気はどこから来るのか。ひとつに、これがはっきりと合法とも違法とも言えないグレーゾーンの問題であるという扱いづらさがある。もうひとつの側面、それは独特の永田町の綱引きだ。これについては、テレビ朝日報道局の藤川みな代政治部長が、翌金曜日の報道ステーションで明快に解説してくれた。かいつまんで言うとこういうことになる。
まず野党側だが、審議中の新年度予算案を人質に取る形で、その成立と引き換えに退陣に追い込むという手段が考えられるものの、予算の成立を遅らせたという批判が自らに向くことは避けたい。さらに、夏に行われる参議院選挙を考えると、自民党には弱くあってほしい。だから、傷ついた石破首相で戦ってくれた方がやりやすいのであって、いますぐ内閣打倒という機運にはなりにくい。なるほど。
そして足元の自民党にも、石破降ろしが一気に始まる雰囲気にはない。それは、ひとつにはポスト石破の「コマ不足」であり(すみません、これは僕の意訳です)、もうひとつは、党の看板(総裁)を代えても選挙に勝てないのは去年秋の衆議院選挙で皮肉にも実証済みだから、下手に動けないというものだ。
いずれも納得のいく説明だ。政権を大きく揺さぶる出来事には違いないが、瞬間的に大きなエネルギーが出ない理由がよく分かる。だが、世の中のフラストレーションはかなりたまっているようだ。週末にかけて行われた各社の世論調査では、内閣支持率が軒並み10ポイント前後の下落となった。この数字をどう見るべきか。
立憲民主党の野田代表は、「私は簡単に辞めさせない。それこそ自民党が喜ぶことだ」と述べた。先ほどの藤川部長の指摘の通りだ。政治倫理審査会(せいりんしん、という言葉を去年から何回聞いたことだろう)で説明責任を果たすよう強く求めていくとしている。それはそれで常道だろう。
しかし、僕は一方で漠然とした、しかしぞっとする不安のようなものを感じている。
政治は時として近視眼的になりがちだ。政府与党としては、まずは予算の年度内成立を図るという使命がある。そして、夏には参議院選挙が控え、与野党ともに選挙に向けた戦略と駆け引きに明け暮れる。先ほどの野田さんの言葉もまさにその一環であり、そのこと自体は否定できない。
しかし、僕の不安は、そうした日々の永田町の営みのはるか外側で、もっと長期的な「政治離れ」、言い換えれば「永田町離れ」が進んでいることにある。
首相官邸で取材している記者に聞くと、石破さんは商品券問題で、自分がいかに国民感情とずれていたかを後悔しているという。これだけ世の中の批判を浴びたのだから、大いに反省して真摯に職務に取り組んでもらうのは当然だ。一方で、これは野党も含めて、政治と国民との乖離をどう埋めるかを真剣に考え、一つずつ実行に移す時に来ていると言っていい。それはもはや待ったなしなのではないか。
政治が国民から見放され、政治と国民世論と乖離が埋めがたいほど広がったとき、そこに広がるのはどのような荒野だろう。そして、荒野の支配権を握るのは誰か。それは今まで見たこともない化け物かもしれない。
(2025年3月17日)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)