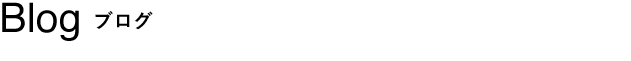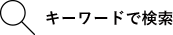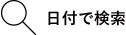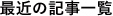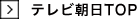- トップ
- ブログ
- 投手生命をかける
- 2025年10月08日
ストライクゾーンのはるか外側、しかもホームベースのはるか手前でワンバウンドしたボールはバックネット裏まで転がり、慶応の吉開鉄朗捕手が機敏にボールを拾いに走った。大暴投の張本人である僕が「やっちまった!」と天を仰いでまもなく、その吉開捕手がマウンドに駆け付けてきた。「ボール、捕れなくて申し訳ありませんでした!」と、笑顔とともに記念のボールを手渡してくれた。
一気に救われた気持ちになった僕は、マスクとヘルメットを取った吉開捕手の長い髪がさらりと秋風に揺れるのを見てそのカッコよさに驚きを覚え、次の瞬間、スタンドからありがたい拍手が続いているのに気づき、ペコリペコリと何度も頭を下げながらベンチ裏に引き返したのだった。
何の話かというと、10月5日の日曜日に行われた神宮球場での東京六大学野球秋季リーグ戦、慶応対東大の2回戦の冒頭に行われた始球式でのひとコマである。東京六大学野球連盟100周年の今年、カードごとに「レジェンド始球式」と銘打って、各校のOBがマウンドに上がっている。その呼び名にふさわしく、後にプロ野球などで偉大な活躍を成し遂げた往年の名選手が名を連ねる中、僕ごときがそこに加わるのはおこがましいのだが、そこは図々しくお誘いに応じることにしたのである。
ちなみに、僕は東大野球部時代、投手としてリーグ戦通算8勝27敗。この通算成績を人に伝えると、どう評価していいかわからないというふうに、だいたいが戸惑った表情を浮かべる。だが振り返ってみると、先発にしてもリリーフにしても、それこそ最後はヒジがまっすぐ伸びなくなるほど、来る日も来る日もよく投げたなあという充足感が、いまだに自分の誇りではある。
始球式に臨むことは光栄なことである一方、「まあセレモニーなのだから」と僕は気楽に構えていた。ところが当日の朝、僕は5時にぱっちりと目が覚めると、二度寝などとうてい無理であることを悟った。明らかに緊張していたのである。
東大は前日、慶応との1回戦で今季初勝利を飾っていた。この日勝てば久々の勝ち点となる(六大学リーグはひとつのカードで先に2勝した方が勝ち点を挙げる勝ち点制)。選手たちは気合が入っているはずだ。自分の現役時代を思い出し、その緊迫した空気を想像しただけでも胸がドキドキする。
横になっているのももどかしく、肩を回したり、手首をコキコキと動かしてみる。よし、異常はない。ついには起き上がってシャドーピッチングを始めた。
実は僕には秘策があった。これまで、球速130キロに挑戦するという無謀な企画を番組で何度か放送させてもらい、100キロ少々しか出ないことに行き詰まりを感じていたが、ドジャースの山本由伸投手のフォームを見ていてひらめくものがあったのだ。山本投手のフォームは、踏み出した左足が「つっかえ棒」のような形になり、その足を起点にそれまでため込んだ力が一気に上半身へと集中、ボールのリリースへとつながっているように見える。これに対し僕は、左足を挙げて踏み出す際に下半身が沈み込みすぎた結果、そこで力が逃げてしまい、投球のパワーがそがれてしまっていた。
えっ?そんな素人の野球理論に興味はない?偉大な山本投手と比較するのはけしからん?
おっしゃる通りです。ともかく僕という人間は、根拠のない楽観論が突然舞い降りる癖があり、山本投手を参考に、踏み出し脚の幅を小さくし、「つっかえ棒」の役割を果たすようにすることで、奇跡のような球速を出せると信じ込んでいた。
始球式で剛速球を披露し、後輩たちを鼓舞する自分の姿を夢想しながら、ふと現実に戻ってテレビをつけると、地区シリーズの第1戦に二刀流で先発登板した大谷翔平選手が躍動している。「おお、オレを励ましてくれているのか!(そんなわけない)」と大谷選手に画面越しに感謝の敬礼をし、いそいそと神宮球場に向かった。
球場で、東大野球部のマネジャーが用意してくれた母校のユニフォームに着替えて出番を待つ。その間も、控室のテレビではフィリーズ対ドジャースの試合を映し続けていた。最終回、佐々木朗希投手がマウンドに上がる。とてつもない緊張感に違いない。しかし、彼は見事に相手打線を封じてリードを守り切り、ドジャースのクローザーとしての役割を果たして見せた。
「おお、佐々木投手までオレを鼓舞してくれている!(そんなわけもない)」と意気に感じた僕は、自分を支えてくれている3人のドジャースのサムライたちの恩に報いるためにもと、気力をみなぎらせながらマウンドに向かったのだった。
それなのに、投球の結果は冒頭申し上げた通りである。すっかり舞い上がってしまった僕は、左足の踏み出し幅を小さくすることなど完全にどこかへ吹き飛んでしまい、ひたすら力んで大暴投を演じた。にわか仕込みで人の真似をしたところで、フォームなど改良されるはずもないのだ。
しかし、久々に立った神宮のマウンドからの景色はあの時のままだった。ミットを構える捕手とその後ろに立つ主審、さらにその奥のバックネット裏には熱心な大学野球ファンが陣取り、上に目をやれば真っ青な秋空が広がっていた。僕は緊張感に震えながらも、胸がいっぱいになっていた。
この神宮球場で繰り広げられる東京六大学野球。100年の歴史の中には、あの戦争で学徒出陣していった選手たちの名も刻まれている。ふだんは意識せずとも、選手たちにはそうした伝統の重みが脈々と引き継がれている。
それでも現役選手たちはあくまで若く、颯爽としていた。東大のベンチ裏でメンバーたちと話す機会があったのだが、みな礼儀正しく、そしてどこかダサかった僕らのころと違って、やはり髪型がすてきだ。憧れの六大学野球だもの、そうでなくちゃ。
試合は、アンダースローの東大エース・渡辺向輝投手が先発登板し、序盤、慶応打線相手に凡打の山を築いた。だが連打を浴び、連勝はならなかった。
スタンドで試合を見守った僕は、秋の神宮を、わずかな感傷と共に堪能した。4年生にとっては最後のリーグ戦である。野球少年でいられるのもあとわずかだ。彼らは間もなく社会の荒波に漕ぎ出していく。野球を通じて培った人間力によって、しっかりと生き抜いていってほしいと願う。そして彼らが社会に貢献しようと懸命に取り組む限り、物言わぬ神宮の歴史がその背中を静かに押してくれることだろう。
その2日後の7日、報道ステーションのスポーツコーナーでは、東京六大学野球100周年というメモリアルな今年、リーグ戦で様々なレジェンドたちが始球式に立っていることを伝えた。恥ずかしながら僕の映像も紹介されたのだが、コロコロと小太りの自分の体形に落胆すると同じくらい、渾身のストレートの球速が「90キロ」と表示されていることに口惜しさを覚えた。130キロはどこに行った?このままでは130キロ挑戦企画など笑止千万ということになってしまう。
本気でダイエットに取り組まなければ。そして、山本由伸投手のような理想的な投球フォームを身につけなければ。神宮を巣立って40年余り。今になって投手生命をかける自分がいる。不思議な話だ。
(2025年10月8日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)