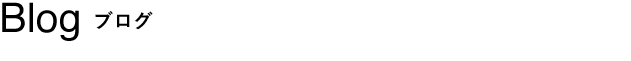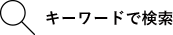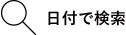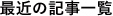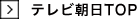- トップ
- ブログ
- 沖縄の80年
- 2025年06月25日
「この臭いを少し体験してみませんか」。
ディレクターの勧めに応じた僕は、学芸員の保久盛さんが差し出してくれた小さな瓶に、少し怖気づきながら鼻を近づけた。そして強烈な臭気に思わず顔をしかめてしまった。当てはめるべき言葉が見つからない。あえて言えば、この世の悲惨を閉じ込めた臭いとでもいうべきか。
ここは沖縄県中部、南風原(はえばる)町の高台にある「沖縄陸軍病院 南風原壕群20号」である。人の手によって掘られた、幅、高さともに180cm、長さ約70mの横穴である。少し背が高い人なら注意をしていないと岩肌にすぐ頭をぶつけてしまう空間だ。この密閉された空間が「病院」だったのだ。
入口から進んだほぼ中央付近に、この壕と他の壕が交差する十字路があり、そこには手術台が置かれていたそうだ。麻酔が行われないまま手足を切断する手術も行われたという。その場所に立って、交差するもうひとつの壕に目をやると、その先の土砂は崩れていた。戦争遺構は、懸命に保存する努力とそれを支える資金があって、初めて我々の目に触れるのであり、そうでなければ、時間の経過とともに崩れ去っていく運命にある。
さらに第20号壕を進む。学芸員の保久盛さんによると、ここから先、壕の半分のスペースには二段ベッドが並べられ、傷病兵たちが寝かされていた。つまり、わずか横幅90cmの病床ということになる。残りの90cmの通路を、看護要員たちが忙しく立ち働いていた。10代にして動員された女子の学徒隊こそがその主力だった。彼女たちは患者の手当てや食料の調達だけでなく、死者の埋葬も日常業務だったという。
お願いして、足元を照らす懐中電灯を含め、すべての明かりを消してもらった。まったく何も見えない。これこそが漆黒の闇だ。震えがきた。
そして僕は臭いを想像してみた。あれから80年が経った今、この壕には不思議と鼻腔を刺激するものを感じなかった。あえて言えば、草木のない岩肌が放つ無機質な空気を感じるだけだ。しかし、この壕が病院として使われた時、この空間には傷病兵の傷口が発する臭い、汗にまみれたすべての人の体臭、そして死臭に至るまで、あらゆる臭いが充満していたに違いない。
見学を終え、悄然とした僕に差し出された瓶こそ、この臭いを凝縮したものだった。生き延びた人たちの証言をもとに、化学成分を調合して再現した小さな臭いの粒。そう、それはやはり、この世の悲惨を閉じ込めた臭いとしか、僕には表現のしようがない。
上陸したアメリカ軍の攻勢にさらされ、南風原の陸軍病院は南部への撤退を余儀なくされた。歩ける患者はともかく、そうでない患者は取り残されるか、青酸カリが入ったミルクを飲まされたそうだ。第20号壕の壁には、アメリカ軍の火炎放射によって焼け焦げた青黒い跡がいたるところにあった。その中に留まった人の運命は想像に難くない。
ひめゆり学徒隊は、こうした野戦病院で奉仕した女子の学徒隊の中でも、最もよく知られた存在である。沖縄戦を生き延びた元学徒隊員も、90代の半ばを超え、多くがこの世を去った。
去年96歳で亡くなった与那覇百子さんは、沖縄師範学校女子部の生徒だった時、ひめゆり学徒隊に動員された。戦後、東京に移り住み、その後埼玉県の桶川市に居を構えた。だが1972年の沖縄の日本返還後、百子さんは思うところがあり郷里に戻った。長男の満さんによると、返還後、沖縄国際海洋博覧会(海洋博)が開催されるなど、沖縄は美しい自然に恵まれた南の楽園としてのイメージが日本中に広がった。その一方で、日本で唯一の、絶望的な地上戦が繰り広げられた地であるという事実が、驚くほど知られていないことに、百子さんは強い違和感を覚えていたという。
沖縄に戻った百子さんは、糸満市の「ひめゆり平和祈念資料館」を中心に、語り部としての活動に奔走した。
百子さんの語りが映像に残っている。壕の病院で苦労を共にした大好きな先輩学徒が爆風に飛ばされ、人の形をとどめない姿になって岩肌に打ち付けられていた。その記憶を語るとき、さすがに百子さんも感情をこらえきれない様子だった。
ただ、長男の満さんによると、百子さんが戦争体験を語るときの口調はむしろ淡々とした印象だという。避難を続けていた父親が、自分が働く壕を訪ねて来て奇跡のような再会を果たしたこと。ところが、「軍の施設」だからと親と娘の双方が遠慮した結果、かくまう機会を逃し、結局二度と会うことがかなわなかったこと。
そうした悲劇を振り返りながらも、百子さんは自分を制しながら語ったそうだ。満さんは、「ものすごいショックがあっただろうし、もっと感情を出して『こんなにひどかったんだよ』と言うこともできたかもしれないのに」と振り返る。あえて淡々と語ることで、百子さんは、事実を事実として脚色なく伝えたかったのかもしれない。
実は百子さんの夫、つまり満さんの父の政昌さんも学徒隊だった。沖縄師範学校男子部で構成される「鉄血勤皇隊」として動員され、かろうじて生き延びた。満さんは小学生のころ、最後の激戦地である「摩文仁(まぶに)の丘」に近い海岸を歩きながら、政昌さんから壮絶な体験を聞いたことがある。まさにその海岸でのことだ。一緒にいた友人とともに爆撃に遭った。その瞬間、友人の顔面が吹き飛んだ。政昌さん自身は腹部に破片が刺さったが致命傷に至らずに済んだ。
亡くなったその友人は、「名も知らぬ遠き島より…」という詞で始まる「椰子の実」の歌を、朗々と愛唱する人だったそうだ。歌の上手な友人が突然、絶命した瞬間の消えない記憶を、海辺を歩きながら伝える父。それを聞く幼い息子。ふたりのやり取りの様子を思いながら、「椰子の実」の旋律が僕の脳内で重なった。
戦争には無数の事実がある。それぞれの人にそれぞれの戦争があったのだ。
軍が南部への撤退に追い込まれる中、動けずに南風原の病院壕に取り残された傷病兵にも。絶望的な状況の中で敵兵に切りかかり、殺されてしまった人にも。万策尽きて集団自決を迫られた人たちにも。生き残り、語り部として経験を語り継いだ人にも。あえて人前で語らずとも、息子にそれを語り継いだ人にも。
どれだけ沖縄戦のことを学んでも、我々が知ることができるのは無数の事実のほんの一端だ。知れば知るほど、知らないことがいかに多いかを知る。そのことを強く認識させられるのが、物言わぬ沖縄の戦跡であり、語り継がれた人々の記憶の数々なのだ。
私たちは事実に謙虚でなければならない。膨大な事実のほんの一部であっても、まずはその重さに頭を垂れるべきだ。事実の記憶と記録を軽んじ、ましてや素通りして身勝手な戦争観を語ることを、厳に慎まなければならない。
沖縄戦の組織的な終結から80年という月日を経ながら、僕は今回、沖縄戦を身近に感じた。ウクライナやガザで罪なき市民が今も命を奪われている現実がそうさせるのか。敵対するイランへの攻撃に踏み切り、勇ましくその戦果を誇る超大国アメリカの大統領に、民主主義国家のリーダーと言うより、ロシアなどと重なる独善と強権性を感じるからだろうか。
このざわりとした危機感に慣れてしまってはならない。人間は戦争を避けられない生き物だなどと、したり顔で語ることだけはしたくない。80年目の「沖縄慰霊の日」は、戦争を知らない世代である自分たちが受け継ぐべきバトンの重さを知る一日でもあった。
(2025年6月25日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)