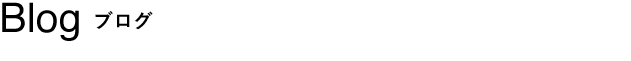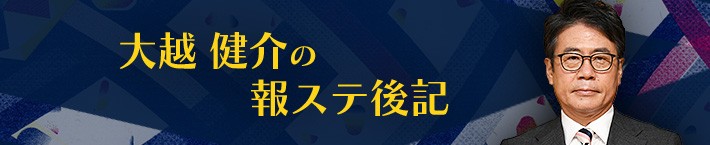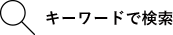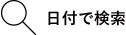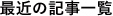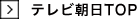- トップ
- ブログ
- 巨大会場の一隅で
- 2025年04月12日

そのブースは、小国などが参加する「COMMONS(コモンズ)」と呼ばれる共同館の一隅にあった。大阪・関西万博の開幕を2日後に控え、共同館では関係者があわただしく準備にあたっていたが、鮮やかな黄色と青で統一されたブースはひときわ目立った。それはウクライナの国旗の色である。ここが戦禍にあるウクライナ館だ。
さっそく担当者に取材を申し込んだ。いきなりのことなので、カメラを向けてのインタビューまで無理は言わないが、今まさに準備中のブースの様子を撮影させてほしいと。ウクライナからやってきた、おそらく広報を担当していると思われる女性は、即座に「OK!」と快諾してくれた。
郊外型の商業施設(モール)でよく見かけるような、ちょっとした小物を扱うショップに似ていて、間口、奥行きとも10メートルに満たないといったところか。側面には品物を売るようにして棚があるのだが、並べられつつあったのはちょっと不思議なものばかりだ。そしてブースの奥には大きく「NOT FOR SALE」と書かれた看板が掲げられていた。ショップのような外観とは裏腹の、「売り物ではありません」という意味である。
不思議な感覚でもう一度見つめると、展示されているのはいくつもの拡声器のレプリカだった。そして「M」という文字を表すアイテムもずらりと並んでいた。いずれも青で統一されている。
「拡声器の意味するところは何ですか」と聞くと、彼女は「言論の自由です」と答えた。なるほど、この意味するところは、今も侵攻をやめようとしないロシアへの強い抵抗姿勢だ。強権国家として知られ、政権に不都合な野党政治家やジャーナリストがしばしば消息を絶つロシアに対する、痛烈な皮肉とも言える。そして、「M」のアイテムの意味は、僕にも思い当たるところがあった。これはメトロ、つまり地下鉄を意味するマークではないのか。
「そうです。これは地下鉄のことです。ご存じかもしれませんが、ウクライナでは、地下鉄は空爆から逃れるシェルターであり、時には学校にもなるのです」と彼女は話した。
小さなブースだが、この場所はウクライナの強固な意志が込められていると感じた。「売り物ではない」。そう、ウクライナという国は、トランプとプーチンという、米ロふたりの首脳の「ディール」によって、頭越しに切り刻まれたり、売り渡されたりするつもりなど、毛頭ないということなのだ。日本間にして10畳ほどの広さのウクライナのブースは、強烈なメッセージを放っていた。
「いのち輝く未来社会のデザイン」が、大阪・関西万博のテーマである。一周約2キロある世界最大の木造建築物「リング(大屋根)」に包み込まれるようにして、「万博の華」と言われる各国のパビリオンが、そのユニークな姿を競っている。準備に余念がない開幕直前の様子を、番組の中で中継リポートすることになり、リングのてっぺんから会場を見下ろすと、それは巨大な円形の宝石箱のように見えた。
資材の高騰や人手不足などによる工事の遅れが頻発し、関西はともかく、それ以外の地域ではあまり盛り上がっていないと言われるこの万博だが、やはりその意義は小さくないと僕は思う。パビリオンを取材すると、それぞれの国がこの万博にかける強い思いに、驚かされることも少なくなかった。
特に、ぐんぐん存在感を増す新興国の熱の入れ方は相当なものだ。次回2030年の万博のホスト国であるサウジアラビアは熱かった。砂漠にあるイスラム教の産油国というイメージだけでは語ることのできない、巨大なポテンシャルを秘めていることを知った。いや、秘めているどころか、みなぎっていた。
国の中の広大な一つの地域を、まるごと環境とデジタルがマッチした未来都市に作り変えようという試みが、巨大なスクリーンで紹介される。日本ではおよそ考えられないほどの規模感だ。その街では2029年の冬季アジア大会が開かれる予定だ。なんと、中東のサウジアラビアで、スキーやスケート、スノボーなどの一線のアスリートが躍動することになるのだ。
「我々の国にも高い山はあるんですよ」と、わざわざ案内役を買って出てくれた在日サウジアラビア大使は笑みを浮かべるが、冬のスポーツとは縁が薄いはずのこの国には、一から大規模な大会のインフラを立ち上げる力がある。しかも、巨大な半島をなすこの国は、実は豊かな海洋資源の国でもあり、その活用にも意欲的に取り組んでいる。
広い万博会場を回ると、歩数はかなりのものとなる。今回、現地での番組クルーのとりまとめ役となった総合デスクは、調整のために会場内を行き来するうちに、歩数計は一日で3万5千歩を記録したそうだ。彼に比べ座ってコメント作成に当たる時間の多かった僕でさえ、2万歩を数えていた。
ただ、肉体的な疲れと引き換えに、この万博では、知的な刺激を大いに受ける。僕は少年時代、世界地図を広げてあれこれと想像をめぐらすのが大好きな子どもだった。それは我が三男にも受け継がれ、小中学生だった頃のこの息子は、アフリカの「サントメ・プリンシペ」という小さな島国にご執心だった。2005年の「愛・地球博」に連れて行ったのだが、アフリカ諸国の共同館で、熱心に展示に見入っていたのが忘れられない。親子してそういうわけだから、僕にとってこの万博会場は、まさに宝石箱なのだった。
だが、この万博に強い批判があるのもまた事実である。財政的に厳しい今の日本で、半年の開催期間が終われば更地に戻さざるを得ない万博会場で、巨額の税金を投入してお祭りをするのはいかがなものか。しかも、大阪万博が開かれた55年前の成長期の日本ならともかく、すっかり成熟国家となった今の日本では、世界に目を向けようという気力も減衰気味だというのに。
それに今は空前の物価高だ。期間中、万博の入場チケットは大人一人あたり7500円がかかる。日帰りできる関西圏内ならまだしも、遠方に住む人たちにとっては、旅費を含めてずいぶんと高嶺の花である。ただでさえ生活が苦しいというのに。「万博なんて知らない」とそっけない気持ちになるのは十分に理解できる。
しかしそれでも、僕はこの万博に、ポジティブな意味を見出したいと思っている。
米中の貿易戦争に象徴されるように、世界の大国同士が角を突き合わせる殺伐とした現実。各地で戦争は続き、人間がもたらした温暖化は確実に地球をむしばんでいる。そして今度は、その人間を凌駕しそうな存在としてAIが急速に存在感を増し、われわれの存在意義さえ自問せざるを得ない社会になっている。
だが、人間にはつながる力がある。豊かな情感をもって互いを理解し、共通の目標へと向かう力がある。互いの良さを認め、共に高めあうことができる。「人間って悪くない。生きていくというのは素敵なことだ」と感じることは、ともすると砂漠化しそうな僕たちの心に、みずみずしいオアシスをもたらしてくれそうだ。
特に、これからを生きる子どもたちには、そうした経験をしてほしい。ウクライナや、国連など国際機関のブースを訪れることで、厳しい世界の現実を感じるかもしれない。先進国の巨大なパビリオンで、テクノロジーの現在地や、持続可能な世界への模索について、素直な感性で学び取ることができるかもしれない。その先にあるのは無限の可能性だ。
なんとか、日本中の子どもたちが、経済的な負担の極力少ない形で、この万博会場を訪れるような機会が増えないものか。少なくとも、目をキラキラさせている子どもたちを相手に、「万博なんて知らない」とにべもなく言い放つことは、大人として決してすべきではないと思っている。
(2025年4月12日)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)