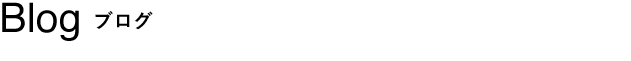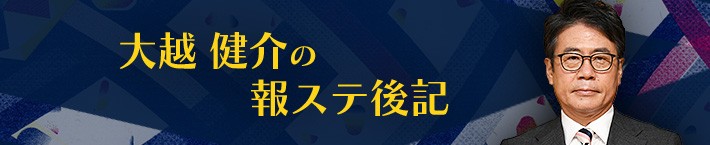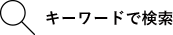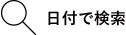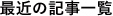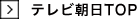- トップ
- ブログ
- ビジネスマンに失礼だ
- 2025年02月24日
自分の仕事は「ニュースの水先案内人」だと僕は考えている。こうして週末に様々な出来事をいったんせき止め、コラムにして綴るのは、報道空間という港の中で、ニュースも視聴者も、あさっての方向に誘導してはならないという気持ちからだ。今を賑わすニュースの本質について、自分なりに考えを整理するのは、良き水先案内人に求められる責任であり、このコラムを書くのはその鍛錬のひとつだと思っている。
だからできるだけ幅広く題材を拾おうとするのだが、自分の心に忠実にあろうとすると、今週もやはりこの人についての考察となる。アメリカ第47代大統領、ドナルド・トランプ氏である。またもや、の感はあるが少々お付き合い願いたい。
妻が、「今さら聞けない、の部類かもしれないけど」と、こんなことを言った。『トランプは1対1のディールを好む』とかマスコミは言うけど、それってどういう意味?」
はっと、一番身近な視聴者を置いてきぼりにしていたと反省した。こちらも分かったように使っていたが、十分理解していたかどうか点検が必要だ。そこで少しこの「ディール」について考えてみたい、
この場合の「ディール」とは「取引」を指す。実際、トランプ氏の発言の中にはこの単語が頻出する。商取引の場合、互いにとって利益が最大化されるのが何よりめでたいことではあるが、残念ながらそれは多くの場合、力関係によって左右される。取引とは、力の強い方に有利に働きやすいのが世の常である。
トランプ氏の「ディール」は、超大国アメリカの力を背景にした、たちの良くない「圧迫ディール」が目立つ。例えば、太平洋と大西洋を結ぶ海上輸送の要衝・パナマ運河をアメリカが支配下に置くべきだとするトランプ氏の発言は、運河の使用料を大きな収入源とする小国パナマを震え上がらせた。同国が関係を深める中国船の航行に横やりを入れている。中南米諸国が中国と関係を強めると、こうなるぞという「見せしめ」とも言えた。
トランプ氏の発言で急にアメリカに支配権が移ることは考えにくいが、彼の口先だけで多少なりとも成果を上げたとすれば(彼が「ぼったくりだ」と言うアメリカ船舶の使用料を引下げさせるような)、トランプ氏にとっては元手のかからない良い「ディール」となる。「どうだ、うまいもんだろう」と笑みを浮かべ、妙なダンスを披露するトランプ氏の姿が目に浮かぶようだ。
どう考えても公平とは思えないものも含め、こうしたディールを得意とするトランプ氏にはビジネスマン特有のやり方と評されることが多い。しかし、よくよく考えると、これはビジネスマンにとって失礼な言い方ではないか。ビジネスとは、損得勘定だけで物ごとを見ることとイコールではないはずだ。僕が甘いのだろうか。
僕は取材先をこまめに訪ねて回っていた記者時代、ある人から「営業の仕事と一緒だよ」と言われて納得したことがある。記者は足で稼いでネタを集める。営業マンは足で稼いで契約を勝ち取る。刑事が足で稼いで犯罪の証拠を集めるのと一緒である。
それらに共通するのは、誠意を積み重ねた者たちだけが築くことのできる仕事上の信頼関係のはずだ。あるいは、立場を越えて(たとえば政治記者と政治家のように)相手と分かち合うリスペクトの感情であるはずだ。
残念ながら、もっぱら圧迫ディールを繰り返す政治家としてのトランプ氏には、それが感じられない。3年前、経済団体の賀詞交歓会で取材した伊藤忠商事の岡藤正広会長が、「ひとりの商人、無数の使命」という会社のキャッチフレーズを教えてくれたとき、僕はビジネスマンの矜持を知った。無数の使命の中には売り上げを伸ばすことも当然含まれるが、取引先にも利益をもたらすことや、ひいては社会的貢献といったものも含まれるだろう。「ビジネスマン」であるはずのトランプ氏には欠落しているものが多い。
そのトランプ氏は、いま盛んにウクライナのゼレンスキー大統領をこき下ろしている。彼の支持率は4%に過ぎないとでたらめな数字を持ち出したかと思えば、選挙を経ない独裁者だと曲解も甚だしい言い方で非難する。一方で侵略を引き起こした側のロシアのプーチン大統領については、「心から停戦を望んでいる」と同情して見せる。なにやら、戦争を始めたのも終わらせることができないのも、全てがゼレンスキー氏側の責任でもあるような言いぶりである。
「コメディアン出身の男が」などと、ゼレンスキー氏の前歴をあてこするような言い方もする。ちなみに、コメディアンは面白い人だからなれるというような単純な仕事ではない。お笑いの文化が盛んな日本人ならわかる。彼らが笑いを取ることに対していかに真摯であるかを。辛酸をなめることの方が多い世界で、いかに苦労を重ねて舞台に立っているかを。
ここにきて、トランプ氏がゼレンスキー氏を攻撃している理由が見えてきた。22日に開かれた保守派の集会でトランプ氏は「われわれは資金を取り戻す。不公平だからだ。レアアース(希少金属)であれ、石油であれ、得られるものは何でも求めている!」と吠えた。この「得られるものは何でも(anything we can get)」という演説のくだりでは、まるで演歌のような不思議なこぶし(演歌に申し訳ないか)をきかせていた。例のダンスに次ぐ珍妙なトランプ節の披露だった。
ゼレンスキー氏をけなし、プーチン氏を持ち上げる。これはじっと黙って攻撃を続ける残忍なプーチン氏を、何とか停戦交渉に引っ張り出すための巧みな交渉術なのかもしれない。アメリカに鉱物資源の一定の利権を渡すことは、そもそもウクライナが昨年発表した「大勝利計画」に含まれていた内容でもあり、外交の強化によって事態打開を図りたいというゼレンスキー氏の方針に決して反したものではないという見方もある。だからトランプ流の過激な言葉づかいに左右されず、冷静に情勢を見極めるべきなのかもしれない。
しかし、ウクライナ側の屈辱感は想像に難くない。主権の一方的な侵害や力による現状変更を許さないという決意のもと、自由と民主主義の価値を守るために各国が納得の上で拠出してきたはずの資金を、今になって、「あれはお前にとっての借金だから、これからのしを付けて返せ」と言われているようなものなのだから。将来の安全保障(もうロシアが攻め込むことはないという仕組み)の担保なしに、資源というカードを、ゼレンスキー氏が切るわけにはいかないのは当然のことだ。
強者による恫喝がまかり通る世界はまっぴらごめんだ。しかし、超大国の大統領は、そのやり方をよりによって札付きのプーチン大統領を模範に推し進めているかのように見える。結局はその操り人形になってしまうのではないかという懸念は消えない。
世界のビジネスマンたちはもっと声を上げていい。「大統領よ、どうかディールの王道に戻ってくれ」と。
そして、何より今はウクライナの国民の悲痛な叫びにこそ、もう一度しっかりと耳を傾けたい。24日で、ロシアによるウクライナ全面侵攻からまる3年である。
(2025年2月24日)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)