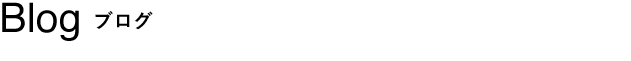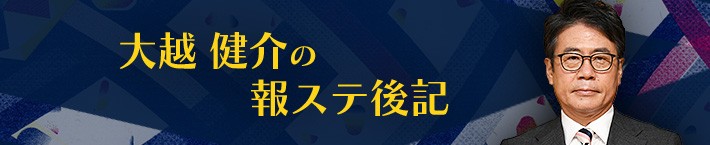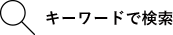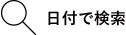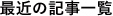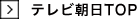- トップ
- ブログ
- オフレコ取材
- 2025年12月21日
「ことの発端は、発言を公にしない、いわゆる『オフレコ』を前提にした記者団の取材での発言ですが、非核三原則は日本の安全保障政策の根幹にかかわる問題であり、その内容を報道すべきだと判断しました。核兵器の保有について、個人として意見を持つのは自由ですが、高市総理に安全保障政策についてアドバイスする立場にある公人としての発言だけに、重大であり、内外に大きな波紋を呼んでいます」
これは、19日の「報道ステーション」で、総理官邸関係者の発言をめぐる波紋のニュースを締めくくった、僕のコメントである。視聴者の皆さんには、それでも少々分かりにくい内容と思われる。そして、いまや取材の過程についても可能な限り透明性を持つべき時代であり、その意味でも様々な取材形態を知ってもらう機会だと考え、このコラムで取り上げることにした。
今回の問題は、官邸関係者と各社の記者団との「オフレコ」の取材の場で飛び出した発言だ。東アジアをはじめとする安全保障環境が厳しくなる中で、この人物は「日本も核(兵器)を持つべきだ」と発言した。想定している時期などは不明だが、発言の前後の文脈から、その発言がジョークのようなものではなく、真意に根差していると現場は判断した。
これは、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」といういわゆる「非核三原則」に明らかに反している。「非核三原則」は、日本政府が堅持してきた大方針であり、唯一の被爆国として、核兵器に依存しない決意を内外に宣言したものだ。それとは異なる考え方を述べる人物が、ほかならぬ日本政府の中枢にいるということになる。
多くのメディアがこの発言を伝えた。これを受け、立憲民主党や公明党などの野党に加え、身内の自民党からも発言に批判の声が上がった。中国外務省も反応し、発言は騒動となった。
僕は、この発言を報道した経緯を、番組内で明らかにする必要があると考えた。そして、担当デスクとともにその内容を練ったのが、冒頭に紹介したコメントである。
このコメントにある通り、ことの発端は、いわゆる「オフレコ」を前提にした各社の取材の場だった。政治記者の間ではよく「懇談」という言葉が使われる。カメラのある記者会見ではなく、より非公式な形で、ざっくばらんなやり取りをしようという意図で設けられる。
取材対象となる当局にとっては、政策の意図や背景を記者たちに理解してもらう良い機会となる。一方、記者の側にとっても、思い込みを防ぎ、ニュースの内容をミスリードしないために有益である。ただ、悪く言えば「相手のペースに乗せられる」可能性もあり、突っ込むべきところは突っ込むという、プロとしての姿勢も求められる。
そうした、双方の思惑が重なって、政治取材における「懇談」の形式は定着してきたと考えられる。
そうして得られた情報をどう扱うか。実名と匿名、オンレコとオフレコ。政治取材の場では、その何とも言えないバランスの中に身を置くことになる。ちなみに僕が総理官邸を初めて取材したのは、平成の最初の頃だ。もう明らかにしていいと思うので、当時のルールの一端について書く。
あるレベル以上の官邸の高官の発言を扱う場合、それが記者会見なら、氏名も当然、公表が前提だ。そして、それが非公式な場での発言であっても、取材者が相当数いる場合(たとえば歩きながらの囲み取材など)で、公人としての発言であると判断されるケースについては、「政府筋」という匿名に準じた主語で発言を報道するという暗黙のルールがあった。
同じような状況で、取材対象が、たとえば官房長官以上の場合、しばしば「政府首脳」という主語で発言を報道することがあった。ただ、いずれも取材対象が「ここはオフレコだ」という場合は報道せず、情報の蓄積にとどめるという紳士協定は存在した。
今、総理官邸で具体的なルールや慣例がどうなっているか、正確なところを僕は知らない。僕が政治記者だった頃とは違う点もあるだろう。だが、人間がすることだ。30年以上前とそれほど大きな違いはないと思われる。
今回のケースはそういう独特の空間で起きた。そこで、こんな疑問も聞こえてきそうだ。「いかなる発言にせよオフレコが前提だったのだから、メディアの側によるルール破りではないのか」。
それについては、妥当な指摘だと言うほかない。当の官邸関係者も、公にしないという前提での発言であり、オフレコのルールを逸脱したのはメディアの側だ。
だが、オフレコの約束とはいえ、高市総理に安全保障政策についてアドバイスする立場にある官邸関係者が、「核(兵器)を持つべきだ」と、従来の政府方針と180度異なる発言をした場合に、座して黙することは逆に許されるのだろうか。僕は、個人としての思想信条の自由を決して否定するものではない。だが、今回の発言の主は、公人としての立場を踏まえながら、記者団に対して発言しているのであり、その事実は重い。
一方で、こんな声があってもおかしくない。「オフレコのルールを破れば相手との信頼関係を損なう。安全保障をめぐるセンシティブな情報を得る手段を記者は失うことになり、つまりは自分の首を絞めるだけでは?」。
これも至極もっともだ。今回の件で官邸は一層、脇をしめるはずだ。記者たちとの間で相互理解を深めるという行為に限界を感じるかもしれない。公式な記者会見はするが、非公式に考えを述べる場を持つことに抵抗を覚えるかもしれない。
しかし、僕は現場の記者の取材力を信じる。取材は「懇談」の場だけではない。取材の基本は「1対1」での勝負であり、さまざまな取材手法によって、「事実」というものは必ず表に出てくる。戦後の日本社会が培ってきた大切な価値を大きく踏み越えた思想や言動は、決して隠しきれるものではない。
僕は、日本も核兵器を持つべきだとは思わない。平和国家としての歩みがそれによって棄損されることはあってはならない。核を持つことによる抑止力が存在することは、世界のパワーバランスの現状を見れば理解はするが、後世に生きる人たちのために、核兵器の廃絶を目指す姿勢を失ってはならないと考える。
オフレコであることを知りつつも発言を公にした今回の判断を、視聴者の皆さんはどう思うだろうか。今回は発言の重みを踏まえ、これを公にすることを優先したが、もちろん我々とて100点満点の答えはない。
丁寧に事実を積み上げるという原点を忘れず、真摯に悩み続けたいと考えている。
(2025年12月21日)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)