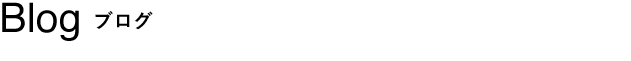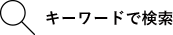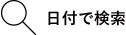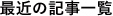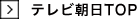- トップ
- ブログ
- 柏崎で考えた
- 2025年11月16日
通学で新潟駅をよく使っていた高校時代、西と東の真逆の方向に、同じ「柏崎行き」の列車が出発していくのが面白かった。西方向は、日本海沿いの越後線というローカル線を通って柏崎に至る。東方向に発車するのは信越本線の電車で、三条や長岡といった都市を経由し、少し遠回りをしてやはり柏崎に至る。
そんな原体験もあり、僕は「かしわざき」と聞くと、交通の要衝にある主要都市というイメージが強い。だが、先日実際に降り立った柏崎の駅前は閑散としていた。駅舎を出てすぐのところには県外にも知られた食品会社のビルがあり、市役所も近い。それなのに市の中心部は生活臭が薄く、これは近年の地方都市にほぼ共通する特徴かもしれない。
町を少し歩くと、東京電力の新社屋の建設現場に行き当たった。完成予想図によれば、社屋には市民のための広い交流スペースが設けられる予定になっている。そこに東京電力が描くのは、市民生活に原発原子力発電所が共存する地域の姿ということなのだろう。
東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働の是非が、いよいよ最終判断の時を迎えている。2011年3月の巨大津波で引き起こされた福島第一原発の重大事故により、同じく東電が運営するこの柏崎刈羽原発も安全性の確認が最優先となり、稼働は停止したままだ。
原発の「地元」とはどこを指すのか。福島の事故で、放射性物質が立地自治体以外にも拡散した現実を考えれば、「地元」の定義は実は難しいのだが、いま現在、柏崎刈羽原発の「地元自治体」とされるのが、立地する柏崎市と刈羽村、そして新潟県の3者だ。このうち柏崎市と刈羽村は、自治体として再稼働に賛成することを表明済みで、残る新潟県の花角(はなずみ)知事が、今月(11月)中に最終的な判断を示す運びとなり、判断の行方が注目されている。
僕が柏崎を訪れたのは、この日開かれた「地域の会」の会議を取材するためだ。この会議体は、柏崎市と刈羽村の住民たちが、柏崎刈羽原発の透明性を高め、安全性を市民目線でチェックできるようにするために設けられた。福島の事故の前である2003年から、東電の担当者なども交えて続けられてきたもので、この日で269回目の開催だと言うから歴史は長い。
「地域の会」のメンバーは、域内の幅広い団体の代表が代々受け継いできており、そこには原発賛成派もいれば反対派もいて、スタンスはそれぞれ明確だ。この日は、再稼働の最終判断近しということもあり、当の花角知事をはじめ柏崎市長や刈羽村長、そして東電の小早川社長もオブザーバーとして顔をそろえた。
最終局面にあってこれだけの関係者が一堂に集まる会議である。そこには当然のことながら緊張感が漂う。だが同時に、議論の進行を見守るうちに、誤解を恐れずに言えば、僕はその空気の中にある種の「調和」のようなものを感じた。
それは再稼働をめぐって、ひとつの方向に議論が収れんしていくというものでは決してない。出席者の意見を聞く限り、こと再稼働への賛否は分かれたままで、交わるところはないからだ。実際、万一の際の避難手順が会議で取り上げられた時も、社会的弱者への配慮は十分か、大雪などとの多重災害となった場合の備えが甘くはないかなど、手厳しい質問が相次いでいた。
それなのに、ある種のチームワークが生まれているように感じるのはなぜか。僕は会議の開始前に「地域の会」の品田会長にインタビューした際の言葉を思い出した。「賛否は分かれているが、私たちの目標はひとつ。地域が、そして新潟県が良い方向へと発展していくことを願っています」。
再稼働、それどころか原発の存在そのものへの賛否は分かれながら、原発の透明性と安全を監視するという大事な役割を共有する中で、それぞれの意見を尊重する土壌が出来上がっているようにも感じられる。
一方で、議論の中ではある男性委員から、「実はわれわれが使う電気も、宮城県にある東北電力の女川原発で作られたものが含まれている。それなのに、首都圏への電力供給の責任を放棄していいのだろうか」という、非常に考えさせられる意見も出ていた。
これには少し説明が必要となる。柏崎刈羽原発は、廃炉が決まった福島第一、第二原発と同様、東京電力による首都圏への電力供給という重要な役割を果たしてきた。一方で、新潟県自体は(福島県もそうだが)東北電力の管轄内にあり、市民生活に必要な電気は東北電力から供給を受けている。
「自分たちもまた原発による電力の受益者なのだ」とするこの男性の意見を聞きながら、僕は自問した。首都圏に住み、当たり前のように電力を消費している僕たちは、電源地帯に住む人々の痛みや悩みを、一体どれくらい理解してきただろうか。
福島の事故直後、東電に頼る首都圏は節電を余儀なくされ、自分たちの電気が福島からやってきている事実を初めて知ったという人は多かった。しかしあれから15年近くが過ぎ、再びその事実は記憶の彼方へ遠のいていないだろうか。だとすればその忘却は、原発の再稼働の是非という極めてセンシティブな問題を、「地元」の人たちに丸投げする、罪深い行為に他ならない。
会議では、再稼働に賛成の立場からこんな意見も出ていた。
自分たち立地自治体の住民は、これまで誰よりも原発のことを勉強して知識を深めてきた。それを原発について何も知らない人が、軽々しく賛否を論じることに強い違和感を覚える…趣旨をかいつまんで言うとそうなる。
この気持ちは、再稼働賛成派のみならず、反対派の人たちにも共通する思いなのではないかと思った。会議の中で僕が感じた一種の「調和」の空気は、原発への賛否とは別のところにある、冷淡で無関心な電力受益者たちへの、不満や諦めのなせる業かもしれない。
僕が生まれた新潟県旧寺泊町(現在は長岡市に編入)は、同じ日本海側に面した港町だ。Googleマップで柏崎刈羽原発からの距離を測ると、僕が産声を上げた場所は、ほぼ30キロちょうどであった。
国は、原発から概ね半径5キロ圏内を「予防的防護措置を準備する区域(PAZ)」、5キロから30キロ圏内を「緊急防護措置を準備する区域(UPZ)」と定め、原子力災害が発生した際の速やかな行動の指針を示している。その意味で僕のふるさとは、原発の「地元」なのかどうかのギリギリのところに位置していることになる。
だが、距離的な概念だけで、「地元」とそうでない側を線引きするのは無理がある。むしろ、この問題を考える際の「地元」とは、電力の受益者が住むところ、つまり首都圏全域がそうであるとも考えられる。「地元」という言い方に違和感があるならば、受益者全員が「当事者」であると自覚すべきだろう。
少なくとも、新潟県のある特定の地域にすべてを負わせてしまっていい問題ではない。「フクシマ以前」と「フクシマ以後」で、日本社会は原発へ向き合い方をどう変えてきたか。また、同じ「フクシマ以後」でも、エネルギー情勢の変化が目まぐるしい中で、社会は原発と向き合うべきなのか。真剣に悩むべきはわれわれ一人ひとりなのだ。
(2025年11月16日)
- 2026年3月 (1)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)