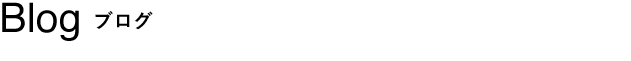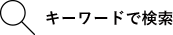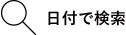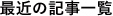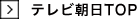- トップ
- ブログ
- 63歳の父と僕と
- 2024年08月25日
63歳になった。63年も生きた。21×3=63である。21歳だった大学生の頃を思い起こすと、自分ではもう十分に大人だと思っていたが、もうその3倍である。そして63歳の誕生日は、僕にとっては特別な節目となる。というのも、父が63歳の誕生日を迎えて1か月も経たないうちに他界したからだ。
父は、生まれ故郷の山に小さな土地を所有していた。週末に通いながら、幼なじみの建設業者の力を借り、手作りのログハウスを建てていた。そこで突然倒れ、この世を去った。その年齢に自分も届いたことになる。
不思議な巡り合わせだった。それは春分の日を挟んだ3月の連休のこと。東京に住む兄と僕、仙台の大学に通う弟が、申し合わせたわけでもなく、偶然新潟の実家に帰省していた。父だけが泊りがけでログハウス(を作るための準備小屋)に出かけており、3兄弟が揃った久々の夕飯の席で、母は「こんな時に限ってお父さんたら…」と苦笑いしていた。
翌朝、警察から連絡があり、父が死んだことを知った。資材の相談に行った幼なじみが見つけてくれたそうだ。作業用の掘っ立て小屋は、父にとっての小さな城だった。その日の作業を終えた父は、自分の城でひとり石油ストーブを炊き、一升瓶を片手にほろ酔いになり、ログハウスの完成形を夢見るうちに、心臓が発作を起こしたらしい。3月の新潟はまだ寒かったはずだ。悲報に接した母がこんなに狼狽し、涙したのを初めて見た。
日本人の平均寿命を考えれば、自分がまだまだ若いのは重々承知しているし、もっと短い命しか生きられなかった人は無数にいる。だが、不遜であることを承知で言えば、父の寿命と同じ満63歳を迎えた僕の胸には、「何とか責任回数をこなしたのかな」という思いがよぎったりする。自分の人生行路をプロ野球の先発投手に例えれば、5回と3分の2を2失点程度で抑え、四球を出したところでコーチがマウンドに駆け寄るタイミングとでも言うべきか。
とはいえ、63歳になった僕の肩は、まだまだボールを投げたがっているらしい。世の中で起きることに憤慨してみたり、悲しんでみたり、喜んでみたり。それが僕という一個人の感情を越えて、スタッフと共有できる思いであるという確認作業を経て、それを言葉にし、視聴者に伝えていく。かっこよく言えば時代の証言者でありたいと願い、人々の心に届く言葉の職人でありたいと願う。
上手に枯れていくことができる人間もいる。ただ僕の場合、世間様に喰ってかかりたいやんちゃな心がまだ旺盛なようだ。
自民党の総裁選挙に向けて、10人前後の議員たちが立候補に名乗りを上げ、推薦人の確保に血道をあげている。競い合うのは結構なことだと思う。でも、へそ曲がりの僕は、ここでいったん待ったをかけたくなる。
そもそも、皆さんにはなぜいま立候補のチャンスが巡って来たのか。それは、政治資金を裏金で賄っていた不埒(ふらち)な議員があまりにも多すぎて、岸田総裁が万事休したからだ。政治への信頼が地に堕ちたからだ。経済も外交も安保も大事なのは誰だって知っている。でもその前に明らかにしてほしいことがある。国民と乖離した永田町文化をどう変えるのか。それこそが一丁目一番地の課題なのだと思う。
推薦人の確保のために党内に頭を下げ続けるうちに、大勢のマスコミを引き連れて思わせぶりな言葉を吐くうちに、いつしかレースにのみ没頭してはいないか。足元にある結党以来の危機という現実の認識が薄れてしまっていないか。僕はそこに釘を刺したい。
それはわれわれマスコミ自身にも言える。総裁選挙の行方に気をとられ、ほぼ解散してしまったはずの派閥を単位にして旧来型の票読みに頼ってしまうような思考停止に陥っていないか。「趣向を変えて、きょうはこの候補の庶民的な一面をのぞいてみましょう」などとありがちな企画を立てるのもウンザリだ。我々が問わなければならないのは、「あなたはちゃんと自民党を、そして政治への信頼を立て直すことができますか」、という一点である。
時をほぼ同じくして行われるのが野党・立憲民主党の代表選だ。こちらも、党存続の危機だというつもりで臨んだ方がいい。自民党の傲慢を許してきたのはライバルの不在である。「自民党もダメだけど、立憲民主党じゃ任せられない」という言葉は、議員たちの胸に痛いほど胸に刺さっているはずだ。
自民党への批判一辺倒でメシを食う野党はもう期待されていない。小さな党の党内抗争よりも、有権者が見たいのは政権のもうひとつの選択肢なのである。
それぞれの党の命運をかけた、大切な選択。その過程を可能な限りこの目で見て回ろうと思う。アメリカの大統領選挙のような派手な演出は、日本人の指向するところとはちょっと違う。アナログな街頭演説や討論会にやはり真実が宿る。僕もせっせと足を運び、市民の疑問と期待をできるだけ共有し、集約し、それを言葉にして問いを発していこう。
父が死んだ年齢である63歳になり、しんみりとした気持ちで書き始めた今回のコラムだが、書き進むうちに元気いっぱいの選手宣誓みたいになってきた。夏の甲子園の余韻が心身に残っているのかもしれない。
父は、戦争を挟んだ貧しい時代、長男として幼い弟や妹たちの面倒を見ながら、苦学して県庁に職を得た人だ。ログハウスを建てようと夢を馳せた小さな土地も、元々はきょうだいと共に懸命に肥やしをまき、耕した畑だった。高度成長期にのほほんと育ち、当たり前のように大学に進学し、仕事にも恵まれてきた自分とは、生きてきた苦労のレベルが違う。
父が63年かけて全力で100球を投げ込んだのだとしたら、僕はまだ50球くらいしか投げていない。老け込んで達観している場合ではない。まだまだマウンドを降りるわけにはいかない。
(2024年8月25日)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)