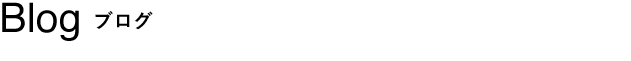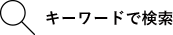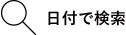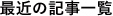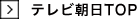- トップ
- ブログ
- 豊かさとは何か
- 2023年06月12日
新潟県の浦佐という山あいの町でイタリアン・レストランを営む、知人の男性が亡くなった。満59歳の早すぎる死だった。
最後に話をしたのは2か月ほど前のこと。しばらく病院で療養し、退院したと聞き、電話を入れたときには、「病気と言っても、別に何てことないですよ」と努めて明るく答えていたが、その声はかすれ気味で、心配していた。そこに訃報が飛び込んできたのが今月5日のことだった。10日の土曜日に営まれた葬儀に参列し、出棺を見送った。
振り返れば、僕は彼と出会ってから「豊かさとは何か」を自問自答するようになっていた。
小さな町の葬儀場だが、会場に入りきれないほどの人が葬送の列に並んだ。皆、泣いていた。彼がどれほど人々に慕われていたかが身に沁みてわかった。
身内のように親しくしていたという人と立ち話となり、彼の闘病の様子を聞いた。実は4年半前に大腸がんが見つかったそうだ。この厄介な敵を、これまでは何とかやり過ごしてきたが、肺や骨にも転移してしまったという。
4年半前から闘病していたとは、恥ずかしながら僕は全く知らなかった。彼との付き合いは、かれこれ10年ほどになる。その半分近い期間、彼は闘病していたことになる。
浦佐周辺の若い農業者が集まるというので、別の知人に誘われて顔を出したのが最初の出会いだった。机上ではない、実際の「町おこし」の議論をのぞいてみたかったのだ。その拠点となっていたのが、彼がシェフを務めるレストランだった。
遠くに住む僕には、遠慮があったのかもしれない。単に闘病を伝える機会がなかっただけなのかもしれない。ただ、僕はあまりに鈍感だった。彼の病気を知らずに、僕は彼に一方的に励まされてばかりだった。
浦佐は新潟県の南魚沼地方にある。なにせ、米どころ、酒どころである。地元食材を使った彼の料理は、ときにイタリアンの範ちゅうを越えていた。白米のおにぎりなども平気で出てきた。春先には山菜を、夏にはどっしり重いスイカを送ってくれた。「いやあ、近くの人が持ってくるものだから」と、屈託がなかった。
彼はいつも言っていた。
「食べ物はおいしいし、自然はすばらしい。スキー場はいくらでもある。東京からなら新幹線で1時間ちょっとで来ることができる。それだけの条件が揃っているわけだから、ここはもっと栄えてもいいはずなんだけどねえ」。
そして彼はこんなふうにも話していた。「この辺の人は売り込みが下手。引っ込み思案で、お人好しで・・・」。
でも、そう言うときの彼は、どこか嬉しそうでもあった。それを聞く周りの人も、なぜか笑顔だった。
そんなとき、僕はいつも「豊かさとは何か」と考えた。
東京の暮らしと地方の暮らし。加工食品と新鮮な食材。街の夜景と山々の豊かな緑。比較して、そのどちらが豊かなのかと考えても、答えらしきものが出てきたためしがない。
新鮮な食材はこの上なくありがたいが、それはそれとして、カップラーメンだっておいしく食べたりするのが現代人だ。都会と田舎といった比較は、豊かさの尺度としては、あまり意味がない。
だが、豊かさをもたらしてくれる「人」が存在するのは間違いない事実だ。
亡くなった彼は、間違いなくそのひとりだった。たまに浦佐を訪ねると、ため息が出そうなごちそうを振る舞ってくれたし、地元の温泉に連れて行ってくれたこともある。それらはいずれもとても豊かな体験だったが、同時に、彼がいてこその体験だった。
つまり、彼こそが豊かさの正体だったのかもしれない。
取材の仕事をしていて気づくことなのだが、何ごとかを成し遂げた人に成功の秘訣を聞くと、よく「人に恵まれたことです」という答えが返ってくる。謙遜でも何でもなく、本心からそう話す人が多い。
だが、周りが良い人ばかりという偶然など、本当にあるのだろうか。実は、その人が、周囲の人たちの良い面を引き出し、良い人に変えてしまうからではないか。だから、その人の目には、「人に恵まれた」景色しか映らない。そういうふうに周りの人を変えてしまうことこそ、その人の魅力、さらには成功の秘訣である。
亡くなった知人もそういう人だった。
彼を中心として輪ができる。そこは共感に満ち、時に建設的な議論の場にもなる。そこで感じられる豊かさこそ、本当の豊かさなのではないか。笑顔が反響しあう、合わせ鏡の空間こそ、幸せな空間と呼ぶのかもしれない。
自分もいつかそんな人間になりたいと思ってきた。そのせいか、彼は僕よりもずいぶん年上だと思っていた。
だが、葬儀の時になって、初めて僕より2歳年下であることを知った。しかも、誕生日が同じだった。何ということか。あれだけ良くしてもらいながら、僕は彼について何も知らなかったのだ。
去り際、彼の生前の様子を教えてくれた女性が最後に言った。
「レストランは、甥っ子が後を継ぎますよ。また来てくださいね」。
その一言に救われ、改めて彼の冥福を祈った。
(2023年6月12日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)