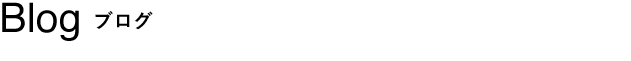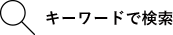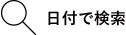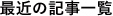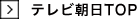- トップ
- ブログ
- 日常
- 2022年04月18日
日曜日に長男と一緒に東京六大学野球を観戦してきた。
ちなみに、僕は東京大学野球部OB、長男は明治大学野球部のOBである。17日の東大対明治の2回戦。どちら側で観戦するかについては息子に譲歩し、3塁、明治側の内野席に陣取った。やわらかい日差しが心地よい。日が傾くにつれて肌寒さを感じるが、それでも、グラウンドで躍動する選手たちにつられるように、こちらの心も浮き立ってくる。
試合は明治が大差をつけてリードしている。東大の選手たちも体格はしっかりしているし、プレーぶりも堂々としたものだが、さすがに強豪・明治のレギュラー陣にはなかなか通用しない。
観戦しながら、それにしても日常が戻りつつあるなと思う。コロナ禍の前に比べると観客の数は減っているが、熱心なファンがスタンドから注ぐ視線は熱い。各校の応援団は、学生が密集して声を張り上げる事態を避けるためか、無観客の外野席に陣取って応援歌とともにエールを切る。それでも東京六大学野球の伝統をしっかり感じることができる。
そろそろ身体も冷えてきた。
信濃町駅からJRの電車に乗って帰宅する。春と秋のシーズンに何度か経験するこの週末のルーティーンは2年間封印されてきたのだが、戻るときには、実に当たり前のように以前に戻るものだ。街では桜の花がほぼ散り、ハナミズキが美しい季節になった。
帰宅したら小さな家庭菜園に肥料をまいて耕さなければならない。大型連休前には畝を作り、夏野菜の種をまいたり、苗を植えたりしなければならない。ことしもミニトマトとキュウリとモロヘイヤは必須だな。春は本当に楽しい。
そんなことを考えながら、電車の中でスマホのニュースを眺めていたら、プロ野球ロッテの佐々木朗希投手が、前週の完全試合に続いてまたも8回まで「完全」投球をし、マウンドを降りたという。球数が100球を超えてベンチは大事をとったのだろう、9回はリリーフにマウンドを譲ったが、とんでもない快挙である。
この日はメジャーリーグの大谷翔平選手も2試合連続のホームランを打ち、スポーツシーンは早くも佳境に入った感がある。ワクワクしてきた。今夜はスポーツニュースをはしごだな。寝酒を飲みながらゆっくりと。
そんな気分で家に帰ると、妻が暗い表情をしながら言う。「日本時間の7時だって。最後通告みたいだね。マリウポリ」
地球は広く、平和な日本で春を寿ぐ僕のような市民がいる一方、ウクライナの戦況はいよいよ厳しくなっている。南東部の要衝・港湾都市のマリウポリは、ロシア軍にとっては是が非でも「取りたい」場所なのだと言う。ロシア軍はマリウポリをいよいよ包囲し、日本時間の午後7時に時間を切って降伏を迫っているという。
暴君と化したプーチン大統領の野望をくじき、力による現状変更という悪しきモデルを作らせないようにするためには、鉄鋼コンビナートを拠点にして防御に努めるウクライナ軍の踏ん張りに期待するしかない。しかし、踏ん張れば踏ん張るほど街は破壊しつくされ、人命が失われる。なんと悲しきジレンマか。
考えてばかりいても始まらないと、外に出て小さな庭に回る。数十キロ分の堆肥をまき、石灰をまく。鍬で丹念に土を掘り起こし、混ぜ込んでいく。駐車場1台分ほどの小さな菜園だが、それでも還暦を迎えた都市労働者にとっては重労働である。休み休みではあるが、無心に土を掘り起こす。古くなった鍬の柄が折れてしまい、スコップで代用し作業を続ける。
日はとっぷりと暮れ、体が重い。でも、戦場の人々のことを思い、避難せざるを得なかった市民の苦悩を思えば、自分の体の疲労なんて比較すべくもない。むしろ、自分も多少の痛みを共有したいとでもいうような愚かな欲求に突き動かされ、ひたすらスコップをふるい続けた。
家では愛犬のおじゃると、愛猫のコタローがいつも通りにじゃれついてくる。そんな日常がありがたい。しかし、日常とは決して当たり前ではないことを、僕たち日本人も肝に銘ずる必要があるとつくづく思う。
戦争は決して、「異常事態」ではないのかもしれない。「普通」の延長線上に、いくつかの誤解と、独裁者の罪深き思い込みが重なれば、戦争は十分に起こりうるものなのだ。実際、それは歴史が証明しているし、今もウクライナのみならず、ミャンマーなどでも現在進行形の出来事である。我々が知りうるだけでもこれだけの悲劇が起きているということは、人間とは往々にして戦争という罠に陥るものなのだということを心しなければならない。そして、壊れやすいからこそ、平和を保つ努力を怠らないようにしなければならないのだろう。
週末が終わった。報道の仕事という、もうひとつの日常がまた始まる。しっかりとしたファクト(事実)を厳選し、視聴者に丁寧に伝えること。世の中にはびこる不条理に敢然と物申すこと。時にはスタジオを離れ、視聴者に代わって自分自身で現場に立ち、五感を働かせること。それが僕の仕事だ。
ウクライナでの戦争というニュースを連日伝えながら、それを決して「日常」としないために、ニュースの小さな変化を決して見逃すことなく、全力で仕事に当たらなければならないと思う。
(2022年4月18日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)