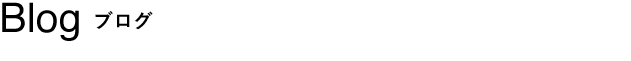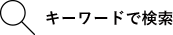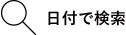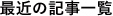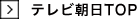- トップ
- ブログ
- 怖いもの
- 2024年08月12日
「地震、雷」ときて、次は「火事、親父」と続く。怖いものと言えば…という文脈で昔からよく使われてきた言葉だ。「じしん・かみなり・かじ・おやじ」と、文字数で3・4・2・3のリズムが小気味よい。「母をたずねて三千里」もリズムが似ている。
それはともかく、ふざけている場合ではない。怖いものの中でも極めつけの大きな地震が相次いだのだ。
8月8日夕方、九州の東、日向灘を震源とする地震が発生した。局内のモニター画面に映し出された、震源を意味する大きなバッテンが書かれた場所を見て、ちょうど打合せ中だったスタッフが「この場所はまずい」とつぶやいた。そう、ぎりぎりではあるが、震源は南海トラフ地震の震源域の、南西の端に位置している。
気象庁は専門家の会議を招集、南海トラフ巨大地震へと連動する可能性について検討した結果、初めての「南海トラフ地震臨時情報・巨大地震注意」を発表した。
番組では、宮崎市などでの被害を検証しつつ、この聞きなれない「臨時情報」についても重点を置いて伝えた。この日の「巨大地震注意」は「警戒」よりは一段下の発表ではあるが、決して侮るわけにはいかない。実際、西日本を中心に、行事を中止したり、防災物資の買い出しに走る動きが相次いだ。
そして事態は息つく間もなく東へと展開した。翌9日の夜、今度は関東など東日本を大きな地震が襲った。脳裏をよぎったのが、前日の地震との関連だった。いよいよ南海トラフ地震の連動が起きたのかと身を硬くした。だが、この地震の震源である神奈川県西部は、南海トラフ地震の震源域からわずかに東に外れている。専門家の見立ても「関係性は考えにくい」とのことであり、幸い人命にかかわる被害も出なかった。
このように日本を、そしてわれわれテレビ報道に携わる者を緊張させる南海トラフ地震とはいかなるものか。
東は駿河湾から西は日向灘にかけて、海底では巨大なプレートどうしが接しており、たまったひずみが限界に達し、プレートが跳ね上がることで巨大地震と津波が発生するというものだ。過去にもほぼ100年から150年に一回の割合で発生している。内閣府の想定によると、次の巨大地震では静岡県から宮崎県まで10県で最大震度7を記録し、太平洋沿岸の広い地域で10メートルを超えると大津波が押し寄せ、最悪32万人余りが犠牲になるとされている。
こう書いているだけでも恐怖が湧いてくる。だが、この地震大国で生きる以上、目を背けてはならない問題であり、「注意」の臨時情報が出されている今はなおのことである。同時に、日常生活を維持していくことも求められている。
少し話題を変えたい。地震よりも序列(?)で言えば4番目にひっそりと位置する、それほど怖くはないひとりの「親父」の話をしよう。すなわち僕のことである。
被爆地・長崎市での平和祈念式典に、米欧の主要国の大使が参列しないことを決めたという情報が駆け巡った。僕は大いに義憤にかられ、9日の式典当日、僕は朝一番の飛行機で長崎に飛んだ。
原爆が投下された11時2分。犠牲者の霊に黙とうをささげる。じっとしているだけで汗がにじむ。この暑さの中で、罪のないおびただしい数の人たちが炎暑に焼かれ、放射線を浴びて命を落としたのだ。だが、この厳粛な式典に、米欧の大使は参列を拒んだ。
彼らの理屈はこうだ。主催者の鈴木長崎市長は、ウクライナを侵攻したロシアと、その同盟国ベラルーシを式典に招いていない。そこに加えて市長は、パレスチナに対する執拗な攻撃を繰り返すイスラエルの招待を見送った。静かに式典を開きたいからだと言う。彼らはそれが認められないと主張する。侵略者のロシアと、ハマスからの攻撃の被害者であるイスラエルを同列に置くのは筋違いだというのだ。
理屈は分からないでもない。彼らは一連のガザ地区への攻撃でも、イスラエルの自衛権の行使だという建前を支持している。しかし、原爆犠牲者を悼み、恒久平和を祈る厳粛な場所に来ることを拒み、イスラエルとの連携を優先させる行為とは、いかなるものなのか。
大使の参列を見送った各国は、その代理に、次席の公使などが式典に参列していた。このうち、フランスの若き公使が、短時間、われわれのインタビューに答えるという。
「これは政治問題なのでしょうか?」。僕は英語でそう質問を投げた。被爆者のひとりが、「式典が政治利用された。残念だ」と話していたことが頭にあった。
公使は答えを言いよどんだように見えた。もう少し突っ込みたかった。本当は「厳粛な慰霊の行為は、あらゆる問題に優先されるべき。心静かに式典を取り行うためにイスラエルを招待しなかったという長崎市長の意見を尊重すべきではないか」と伝えるべきだった。
だが、僕は質問に詰まり、「市長は安全上の問題と言っていますが?」と聞くのがせいぜい。質問は明らかに尻切れトンボだった。公使は、「安全上の問題ならオリンピックだってありますよ」と、フランスの外交官らしい答でかわした。現にイスラエルも参加して無事開催しているパリ五輪を引き合いに出し、その場を後にしたのである。
英語力の不足もあるが、取材者である自分の迫力が、言い換えれば「怖さ」が足りなかったと反省した。
達成感がないままに帰宅すると、コタローは背を向けたままである。このオヤジは怖いどころか、ネコにも完全になめられているようである。
そこでもう一度今回の出来事を振り返ると、そこには日本政府の不在ぶりも浮かび上がる。米欧が大使のボイコットという行動に出たことに対し、政府は「長崎市主催の式典であり、政府がコメントすべき立場にない」という、なんとも無味乾燥な態度を貫いた。果たしてそれでいいのだろうか。長崎市というひとつの地方自治体だけが引き受けるべき問題とはとても思えないのだ。政府はもっと血の通った対応をとるべきではないのか。
この問題は、機会をとらえて政府幹部にもぶつけていきたい。真っ当な疑問には忠実に向き合い、追及し続ける。その姿勢が取材者としての迫力を生む。
地震のような無慈悲な「怖さ」ではない。人間社会ができるだけ正しく回っていくための、正義をまとった「怖さ」を身に着けたい。十分すぎるほどのオヤジになった僕の、静かな決意である。
(2024年8月12日)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)