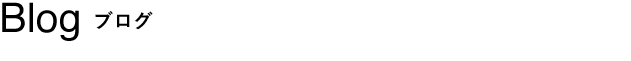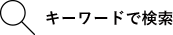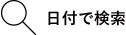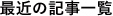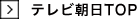- トップ
- ブログ
- ポリティカル・コレクトネス
- 2024年11月18日
「メインストリーム・メディアを信用しますか?」
こんな質問を、大統領選挙前のアメリカ中西部で何度、発したことだろう。その答えは多くが否定的なものだった。「全く信用しない」と答えたのは、オハイオ州の保守系ラジオ局のパーソナリティである。「彼ら(メインストリーム・メディア)は事実を公平に伝えるより、自らの目標達成のため、ニュースに角度をつけ、ゆがめて伝えることに余念がない」と断じた。トランプ氏への支持を明確にしながら。
アメリカの「メインストリーム・メディア」、つまり主流メディアとは、ABCなどテレビの3大ネットワーク、ニュースチャンネルのCNN、新聞ならニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストといった大どころを指す。僕は特派員としてワシントンに4年間赴任したことがあるが、ホワイトハウスなどで見かけるそれら主流メディアのエース級記者たちは、政府高官ともファースト・ネームで呼び合う仲だった。
記者たちは権力を厳しく監視し、批判も容赦ないが、ホワイトハウス側とのある種の連帯も感じさせた。その連帯は、癒着とは異なる「ポリティカル・コレクトネス」と呼ばれる共通の価値観と言える。直訳すれば「政治的な正しさ」となる。自由と民主主義を大切にし、人種や性別による差別をなくす取り組みを重んじる、アメリカの政治史の中で培われてきた気風だと僕は認識している。
ところが8年前の大統領選挙で、この「ポリティカル・コレクトネス」は横っ面を思い切り引っぱたかれた形になった。それがトランプ現象の正体だ。
あの時、民主党は世論調査では想定できなかった大敗を喫し、主流メディアは大いに反省した。ある記者は涙ながらに語った。「自分たちは何も見ていなかった。ワシントンやニューヨークにとどまったまま、机の上で記事を書いていた。取り残された地方に目を向けることができていなかった」と。
それ以後、彼らは日ごろの取材の中で、より地方の声に耳を傾けるよう注意を払うようになったかもしれない。世論調査の精度を上げる努力も一定の実を結んだはずだ。
しかし、今回の大統領選挙の結果を見ると、主要メディアの反省にもかかわらず、分断は一層深まった感がある。ご紹介した保守系のローカルラジオ局のパーソナリティ氏は、いわば確信犯だ。
例えば、対立候補であるハリス氏とのテレビ討論でトランプ氏が「中米のハイチからの不法移民がイヌやネコなどのペットを食べている」と発言し、司会者から「市の当局に確認したがそのような事実はない」と注意された一幕。このことについてパーソナリティ氏に意見を聞くと、「トランプ氏が強調しようとしたのは、不法移民が大挙して小さな町に流れ込んでくる問題だった。しかし主流メディアはイヌやネコといった些末な話に固執したのです」と言う。「主流メディアは論点をすり替えた」と彼は言いたいのだろうが、彼のすり替えもかなり露骨である。
彼のラジオ番組は地元で大人気で、リスナーの多くがトランプ氏を支持している。これはオハイオ州の一例だが、激戦州と言われる他の州などでも同様の潮流が渦巻いていた。こうして、かつては激戦州の代表格と言われたオハイオ州はレッドステート(共和党支持が強い州)へと変わり、激戦州ながらどちらかと言えばブルーステート(民主党支持が強い州)のイメージがあったミシガン州、ペンシルベニア州などもトランプ氏が制した。
「ポリティカル・コレクトネス」を大事にする政治家や主流メディアは、これで2度も横っ面を引っぱたかれたことになる。冒頭から紹介しているラジオパーソナリティ氏から見れば、ハリス氏寄りに見える主流派メディアの方こそ「ニュースに角度をつけ、ゆがめて伝えることに余念がない」のであって、主流派メディアが権力の監視と批判を行っても、しょせん内輪の出来レースにしか見えないということになる。詭弁に近いが、彼らなりの理屈は通っている。
トランプ氏支持者にとって(全員とは言わないが)、今回の選挙結果は「ポリティカル・コレクトネス」を振りかざすいけ好かない連中を、まとめて葬り去ったということなのだ。
アメリカへの出張取材から2週間が過ぎた今、このことがしきりに思い出されたのは、日曜の兵庫県知事選挙の結果に驚いてしまったからだ。パワハラ問題などをめぐる一連の対応について、県議会の不信任決議を受けて知事を失職した斎藤元彦氏が、出直し選挙で当選した。
不信任決議では斎藤氏ついて、知事としての「資質を欠いている」と厳しく指摘。全会一致の決議となった。この事案は百条委員会で今も調査を継続中であり、本人も「県政に対する不安を与えた」ことについては認め、陳謝を繰り返してきた。しかし、民意は斎藤氏に退場を求める声を退け、再び知事の座に迎えたのである。
この選挙戦で優勢が伝えられたのは、前尼崎市長の稲村和美氏だった。選挙戦では、県内の29市のうち22市の市長の支持を得た。稲村氏は結果的に、議会から不信任を突き付けられた斎藤氏の対極にある「ポリティカル・コレクトネス」の代弁者としての位置に立ったと言える。
だが、稲村氏は後半に逆転を許した。稲村氏は敗戦の弁の中で、「何を信じるかが非常に大きなテーマになった。斎藤候補と争ったというより、何と向かい合っているのかなという違和感があったのは事実」と語っている。
その違和感の正体は何か。今の選挙戦では、SNSを盛んに取り入れるのは当然の手法だ。しかし、今回そのフィールドには、斎藤氏には落ち度はなく、むしろ腐敗した県政の中で孤軍奮闘する勇士なのだとする言説が盛んに語られた。しかも稲村氏にとって足かせになったのは、稲村氏が外国人参政権を導入するという、公約に掲げていない情報がネット上に飛び交ったことだ。それを打ち消すのは難しかった。
選挙結果はあくまで斎藤氏の勝利なのであり、その民意は尊重されなければならない。ただ、斎藤氏に対する内部告発文書が県民に動揺を与え、県民によって正当に選ばれた議会が全員一致で不信任を突きつけた事実は重い。その事実にフタをした検証不能な情報がネット上にあふれ、民意が大きく左右された選挙は、果たして公正な選挙と言えるのだろうか。「ポリティカル・コレクトネス」を無視した言論が正しい着地点を見つけることなど可能なのだろうか。
その問いは、常に持ち続けなければならないと思う。特に、主要メディアの一員である僕にとっては、死ぬまで続く葛藤になる気がしてならない。
(2024年11月18日)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)