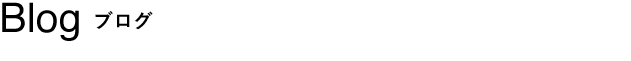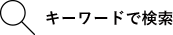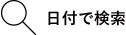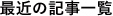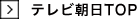- トップ
- ブログ
- ここで昔ばなしをひとつ
- 2024年10月29日
自分の経験ばかりを滔々と語る人が、僕は好きではない。
NHK政治部の記者として永田町を取材していたころ、大先輩たちが(同業他社を含めて)自らの取材経験を誇らしげに語ることが多かった。
もちろん、有意義な話がなかったわけではない。ただ、彼らが語る経験談は、示唆に富んではいても、現状にそのまま当てはまるものとは限らない。政治は変化し続けているからだ。それを、自分の経験則だけに基づいて、あーだこーだと分析したがる。想定とは違う取材結果を先輩記者に報告すると、「そんなはずはない」と聞く耳を持ってもらえないケースもあった。
そんなわけで、僕はかつての自分の政治記者時代の経験を、あまり話すまいと思っている。うるさがられるのが怖いからだ。でも、報道ステーションのスタッフから、「その頃のことを教えてくださいよ」などとヨイショされようものなら、ホイホイと喜んで語り倒してしまう。いやはや、若い頃どこか敬遠していた先輩記者なるものに、自分がすっかりなってしまっている。人間とは困ったものだ。
さてと、十分に言い訳をしたところで、平成の政治改革の頃の昔ばなしをさせていただこう。結局話したいんだな、オレ。
当時、僕はまだ30歳を超えたばかりのころで、若さ爆発、仕事が面白くなってきた頃だった。その時、われわれ取材者たちの視界に否が応でも飛び込んでくる政治家がいた。それが、熱心な政治改革論者だった若き衆議院議員・石破茂氏だった。
石破氏は1986年、自民党公認で衆議院議員に初当選した。だが、自民党はリクルート事件が明らかになり、政治不信は極まった。政治とカネの問題はいつも政権与党を大きく揺るがす。この時の自民党もそうだった。
しかし、党内には今とは異質のエネルギーがあった。若手たちが公然と党執行部に対して政治改革ののろしを上げ、有志の勉強会を開いたり、党の会合でも口角泡を飛ばして自説を展開した。とにかく熱かったのである。石破氏もまた、その熱さを体現する政治家だった。
この時の政治改革論議は、資金の透明化を図るのが本筋だったはずが、選挙制度を変えようという方向に重心が移っていった。結果として、衆議院は、当時の中選挙区制(ひとつの選挙区から複数の候補者が当選する制度)から、小選挙区制(ひとつの選挙区から一人の候補が当選)と比例代表制が並立する制度へと移行した。政治資金の小口化や透明化と引き換えに、税金からの政党交付金の支給も決まった。
この過程で自民党は、主に中選挙区制の維持を訴える勢力(守旧派と呼ばれた)と、小選挙区制を導入し、政権交代を行いやすくすべきだと主張する改革派に大きく分かれていく。そして1993年、改革派を自称した自民党旧竹下派の小沢一郎氏、羽田孜氏らが集団離党して新生党を結成。宮澤喜一内閣の不信任決議を受けて行われた衆議院選挙で自民党は過半数を割り込み、小沢氏の主導で、細川護熙氏を首班とする非自民8党派による連立政権が発足した。自民党は初めて野党に転落したのである。
改革派だった石破氏は、旧来の自民党ではダメだという思いと、自民党に後ろ髪引かれる思いが交錯していたのかもしれない。この時の衆議院選挙には党非公認で無所属として立候補。当選後、自民党を離党し、非自民の連立政権に加わった。
だが、8頭立ての馬車のような連立政権は、足並みを揃えるのは簡単ではなかった。亀裂がすぐに露呈し、細川氏は8か月で政権を投げ出す。その後、羽田孜氏が総理に指名されたものの、連立の一翼を担っていた社会党が直後に離脱、羽田内閣は衆院で過半数を持たない「少数与党内閣」として発足した。石破氏もこの時、少数与党の一員であり、その苦労を肌で感じていたに違いない。
僕は当時、野党だった自民党を担当していた。政権与党しか経験したことのない自民党議員にとって、野党の冷や飯はこの上なく辛かったらしい。ある議員は、「役所に説明を求めると、与党の時は局長が飛んできたものだが、いまや係長か、良くて課長クラスだよ」とこぼしていた。地元の陳情にも十分に応えられず、政権に復帰したいと、彼らは渇望していた。
そんな自民党にとって、少数与党としてよろよろと発足した羽田内閣は、格好のターゲットだった。少数であるがゆえに自力だけでは予算案や法案を国会で通すことができない。結局、遅れに遅れていたこの年度の政府予算の成立と引き換えの形で、羽田内閣はわずか64日間という短命のまま総辞職した。
この間、どうやって政権をわが手に奪い返すかをめぐって、自民党の策士たちが暗躍した。僕が取材で把握していただけで何ルートかあったので、実際はかなり入り組んだ水面下のやり取りが行われたのだろう。結局、自民党は、旧敵の社会党と手を結ぶ。何しろこの頃、社会党は自衛隊の存在すら、違憲だとして認めていなかったのである。
しかも自民党は、その社会党の村山富市委員長を総理大臣に担ぐという、禁じ手とも言える荒わざを使った。これに反発する自民党議員が相次いで造反するなど、それなりに血は流したが、自民党は河野洋平総裁が外務大臣として入閣し、新党さきがけと共に村山総理大臣を支えるという態勢をとった。社会党(のちに社民党と改名)も、自衛隊を認めるなど現実路線に転換し、連立政権はそれなりに安定するに至ったのである。
この時の取材経験は忘れられない。政局の激動の真っただ中にあって、真実を見極める目もそれなりに鍛えられた。何より、取材される側もする側も必死だった。
その後、しばらくして石破氏も自民党に復党した。自民党から見れば「出戻り」の立場であり、それがその後の石破氏の「党内野党」と言われた振る舞いにつながったと見るのはうがちすぎか。
そして、奇しくもいま、衆院選で過半数を割り込んだ与党のトップを務めるのが、その石破氏である。近く召集される特別国会で、総理大臣に指名されるかどうかも覚束ない。政権を維持しようと思ったら、公明党以外の他党と連立を組む選択肢が思い浮かぶが、今のところ日本維新の会や国民民主党の態度はそっけない。せめて、総理大臣指名の決戦投票で「立憲民主党の野田さんと書かないで!」と頼み込むことで、指名は勝ち取ることはできても、少数与党としての苦難の再出発も予想される。
これから与野党間の駆け引きは激しさを増すだろう。
そんなことを考えながら、僕はついさっき、アメリカに到着した。目的は、11月5日に迫った大統領選挙を前に、当地で起きていることを取材し、肌身で感じ、番組でリポートするためだ。
日本の政局が流動化で大変な時にアメリカ?いや、それでいいのだと思う。なんと言っても、トランプ氏が返り咲くかどうかという今回の大統領選挙は、これからの世界を大きく左右する。
そして、もうひとつのささやかな理由がある。それは冒頭に書いた通りだ。
僕のようなベテランが、下手に経験則を語り出すと、かえって正確な現状分析の妨げになる可能性だってある。
そうはなりたくないから、アメリカの今を取材しながら、日本の政治を俯瞰した眼で見ることにしよう。元来、熱血的な政治改革論者だった石破氏が、いかに原点に帰り、新しい改革の道を踏み出せるのかどうかを、海を隔てて見つめつつ、約1週間の取材の旅を進めていこうと思う。
(2024年10月29日)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)