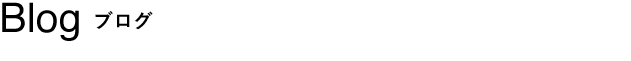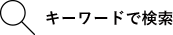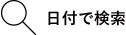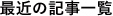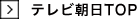- トップ
- ブログ
- 政権の夕暮れに民主主義を考える
- 2024年06月30日
ついこの前のように感じるが、もう16年近くも経っている。
2009年1月、首都ワシントンは初めてのアフリカ系アメリカ人の大統領誕生に沸き返っていた。連邦議会議事堂で行われる就任式には、全米、いや世界中から首都の人口を超える人々が集うことが見込まれていた。ホテル代は高騰し、「民泊」の形で自宅を貸し出すワシントン市民も少なくなかった。
就任式当日は大幅な交通規制が敷かれた。当時、NHKのワシントン支局長を務めていた僕は、日本時間夜9時のニュース番組で、現地からの中継リポートをすることになっていた。アメリカ東部時間の午前7時である。取材・中継ポイントは、議事堂前に広がる広大な緑地帯である。当時のNHKワシントン支局からは5キロくらいのところにあった。
念のため、僕らのクルーが支局を出たのは午前4時過ぎだった。車は案の定、すぐに行き止まりに突き当たり、そこから数キロは徒歩だ。重い機材をかつぎ、白い息を吐きながら黙々と歩く。ようやく目的地にたどり着いた頃には、夜が明け始めていた。
荷物をほどき、安堵してあたりを眺めた。そのときの光景は今でも忘れられない。
朝焼けの中、まるで巨大な磁石に引き付けられているようにして、人々が集ってきていた。四方八方から、人々が列をなしてモールにやってくる。やはりアフリカ系が多いが、肌の色は多様である。
先に到着した人々の間からは、もう「オバマ!オバマ!」、「Yes We Can !」のコールが沸き上がっていた。この場の誰もが心待ちにしていたのだ。まさに大衆に根ざす民主政治の姿であり、そのエネルギーをまざまざと見せつけられた思いだった。
そんな記憶がよみがえったのは、27日に行われたバイデン大統領とトランプ前大統領のテレビ討論会が引き金である。81歳のバイデン氏は、気力、体力とも衰えを隠すことができない。対する78歳のトランプ氏も、質問をはぐらかし、事実をねじ曲げたようなおなじみの一方的な主張を繰り返すだけだった。
討論会後のCNNによる調査では、勝者はトランプ氏であると答えた人が、バイデン氏の2倍に上った。現職の安定した実力で、奔放に過ぎるトランプ氏との差を見せつけようというバイデン陣営の思惑は、音を立てて崩れつつある。
シカゴの弁護士から政治の道に進んだオバマ氏。その名を知らしめたのは、2004年のことだった。同州で行われた民主党大会の弁士として白羽の矢が立った。
「黒人のアメリカも白人のアメリカも存在しない。ラテン系のアメリカもアジア系のアメリカも存在しない。存在するのはアメリカ合衆国だけだ」。
名演説は瞬く間にアメリカ中に広まった。多様性こそ誇りなのであり、それをひとつにまとめ上げていく合衆国のあり方に胸を張るものだった。このときすい星のように現れたオバマ氏が、大統領の座に上り詰めたのはわずか4年後のこと。そのオバマ氏が、その手腕と経験を買って副大統領に起用したのが、民主党の重鎮、当時のバイデン上院議員だったのである。
あの就任式から16年。わずか16年ではあるが、この間にはいろいろなことがあった。オバマ大統領は「核なき世界」を訴えて、就任早々にノーベル平和賞を受賞した。期待を込めての授与と言えた。だが、冷戦時代の旧敵ロシアや、新興の中国の同調は得られなかった。
2期8年大統領を務めたオバマ氏の後継選びは、あっと驚く展開が待っていた。本命視された民主党のヒラリー・クリントン氏が、当初から泡沫と言われながら生き残った共和党のトランプ氏に敗れたことで、世界に衝撃が走った。
型破りのトランプ大統領を生み出したのはこの時も大衆の力のうねりだった。多様性の社会の信奉者だったオバマ氏を押し上げたのが、つらい歴史を歩んだマイノリティ(少数派)の人たちだったのに対し、トランプ氏を押し上げたのは移民の流入を嫌悪する保守的な白人層が中心であり、アメリカ第一主義を声高に叫ぶトリックスターは、にわかに立ち上げられた舞台の上で狂喜乱舞し、群衆もまたそれに熱狂したのだ。
オバマとトランプ。大衆に根ざす民主政治を、良くも悪しくも体現した2人。オバマ氏の選挙でうねりを起こした民主主義の女神は、その揺り戻しのようにして8年後にはトランプ氏に微笑んだ。その結果として、アメリカは分断を極めたままだ。いま、バイデン・トランプ両氏が繰り広げているのは、その延長線上にある消耗戦と言っていい。
この16年の激変の裏にあったものとして、ひとつ確実に言えるのは、メディア環境の変化だ。新聞やテレビといった従来メディアは、世論形成にいまだに大きな力を持つ。とはいえ、それを凌駕する勢いでSNSによる情報伝達と、情報選択が行われるようになった。その負の側面として、自分の見たいものしか見ない、見たくないものは見なくていいという情報空間が形成され、物ごとを俯瞰し、客観的に真実を見極めようとする習慣はすたれていった。
こうした状況はポピュリスト政治家にとっては好都合である。仮に現実性に欠けるものであっても、人々にとって耳に心地よい主張を繰り返す。都合の悪い事実には知らぬ顔をし、政敵をひたすら罵倒して臆することがない。言葉に詰まるバイデン氏を尻目に、涼しい顔をしているトランプ氏の姿はまさにここに重なる。
6月、イタリアで行われたG7サミットはどこか象徴的だった。ウクライナ支援などで結束を確認したが、来年もこのサミットの場に登場する首脳は、果たして何人いるだろう。秋のアメリカ大統領選挙におけるバイデン氏の再選は、完全に黄色信号が灯った。まもなく投票が始まるフランスの総選挙は、マクロン大統領率いる与党連合の旗色は圧倒的に悪く、極右のポピュリズム政党として名をはせた国民連合が第1党の座をうかがう。イギリスの総選挙ではスナク首相率いる保守党の評判が芳しくなく、政権交代の可能性が濃厚だ。そして日本。9月の自民党総裁選挙は、岸田首相の再選ですんなりとまとまる情勢にはない。
先進国と言われる民主主義の国々が、いまいずれも大きな波に襲われている。リーダーを誰に選ぶかはその国の選択にゆだねられるが、民主主義の根幹だけは守られることを願う。でなければ、中国やロシアといった統制国家のリーダーたちが、こんなふうにうそぶくかもしれない。
「それ見たことか。民主主義には時間も手間もかかる。どうだ、我々の方がよほど効率の良いやり方だろう」
いやだ。それはごめんである。
(2024年6月30日)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)