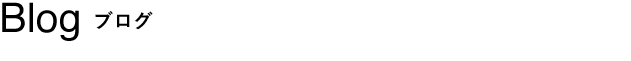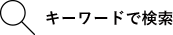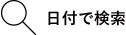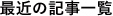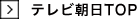- トップ
- ブログ
- 戦争地を歩く
- 2023年12月27日
少しわかりにくいが、これは道路脇に自生するサボテンである。車が停車したところで、同僚がやっとのことで撮ってくれた写真だ。
サボテンは以前にメキシコを訪れた際、あらゆるところで見かけた。そのサボテンをイスラエルで見るとは思っていなかった。商都テルアビブの空港から地中海沿いに南に向かえば向かうほど、サボテンはよく現れる。確かに、冬にして気温が20度にもなるというこのあたりの気候は、メキシコによく似ていると感じる。
南に向かうということは、すなわち、焦土と化しつつあるパレスチナ自治区・ガザ地区に近づくことでもある。果樹園や牧草地が広がる豊かな光景を見ながら走ること1時間半、右に黒煙が見えてきた。ガザは今日も砲弾の嵐の中にあった。
私たち取材クルーが目指したのは、ガザ地区に近い、クファール・アザというキブツである。キブツとはイスラエル特有の、農業を中心とした共同体だ。このクファール・アザは、この10月7日、ガザ地区を実効支配するイスラム組織・ハマスの急襲を受けた。ある者は鉄製の門扉を破壊し、ある者はパラグライダーで境界を越え、住人に銃弾の雨を降らせた。死者は60人に上り、このキブツの人口の、実に6人から7人にひとりが犠牲になったことになる。
果樹園でパイナップルなどを栽培していたアビハイ(42)は、自警のために銃をとって応戦したが、足を射抜かれて動けなくなった。その後、妻と3人の子どもたちがハマスに連れ去られたことを知ったという。
「人生の中で一番幸せな瞬間でした」と、まじめな顔で振り返る。死んではいない、家族は生きていた。それが、皮肉なことに逆接的な「幸せ」という表現となった。もちろん、多くの隣人が殺されるのをその目で見ていたアビハイは、文字どおりの「幸せ」など感じていない。
拉致から51日後、家族は奇跡的に解放されたが、戦争が終わっても、もう家には戻らないつもりだ。家族は今もトラウマに苦しんでいる。武装した男たちが押し入り、無理やり連れていった悪夢の家など、子どもたちには酷というものだ。美しい庭とサウナがある自慢の家だが、アビハイは捨てることにした。
1000人を優に超える死者を出し、第二次世界大戦の際のユダヤ人大虐殺を想起する人も多いという10月7日のハマスの奇襲は、イスラエル国民に激しい怒りと恐怖をもたらした。ネタニヤフ首相は、奇襲を許した失態を挽回しようと、ヒステリックなほどの空爆と地上戦で報復に出た。いま、ガザ地区の死者は、すでに2万人を越え、イスラエル軍はガザ地区北部をほぼ制圧したと言うが、ネタニヤフは手を緩める気配はない。
世論調査上は、多くのイスラエル国民が、ハマスせん滅のための攻撃は今後も支持すると答えている。しかし、実際に市民の声を聞くと、その思いには濃淡がある。テルアビブで会った22歳の女性にマイクを向けると、「政治的な意見は控える」と言った。アビハイも、政治性の強い問いかけには慎重だった。彼は、「人質が全員返ってくることが最優先だ」と答えた。家族が連れ去られた経験を持つアビハイにすれば、同じ境遇の人たちへの思いが強いのは自然である。
ハマスのテロリストは許さないにしても、ガザ地区の一般市民まで犠牲になることを喜ぶ市民はいないと信じたい。「人質の全員返還」は、悩めるイスラエル人がたどり着く、唯一の最大公約数でもあるのだと思う。
一方のパレスチナ人の思いは、より峻烈だ。ガザと同じ(実効支配組織は異なる)パレスチナ自治区であるヨルダン川西岸地区を訪ねた。自治区と言っても、パレスチナ人から支配権を奪い、入植と称してイスラエルが支配を広げているところもあれば、パレスチナ自治政府がにらみを利かせ、一般のイスラエル人が入るのは危険とされる街もある。キリスト生誕の地とされるベツレヘムは後者である。
ベツレヘム市民のイスラエルに対する憎悪の念は、誰に聞いても深かった。「ユダヤ人に追い出された」形で、難民キャンプに押し込まれた人々のそれは、なおさらだ。その生活を分離壁が囲む。「パレスチナ人を寄せ付けたくない」と考えるイスラエル側が立てた壁である。物理的な壁であり、両者を隔てる心理的な壁でもある。
壁は恐怖の象徴でもある。
ベツレヘムに、国連の機関「UNRWA」が運営する学校がある。その隣に住み、卒業生でもある17歳のムハンマドは、外の階段を上って家の屋上に出たところをイスラエル兵に撃たれ、死亡した。キャンプのすぐ近くに立つ壁には、あちこちに監視塔がある。そこでは、狙撃兵が常に銃を手に監視する。反イスラエルの活動家やテロリストを発見すれば狙撃をためらわない。
ムハンマドは果たして危険な人物だったのだろうか。彼の母親は断固として否定した。「息子は屋上にある勉強部屋(確かにテントで囲われ、勉強机とベッドがあった)にものを取りに行っただけ。殺される理由なんてない」と訴えた。
後日、イスラエル兵がやってきて武器を捜索し始めたという。しかし、出てきたものはムハンマドの携帯電話だけだった。
憎しみは恐怖を伴い、過剰な行動へと転化する。殺し合いはそうして続いていく。悲劇の土壌は、常に耕し続けられるのだ。その根深さは、遠く日本で思い描いていたものを大きく越えていた、負の連鎖がそこにはあった。
イスラエルの建国以来続く、この地での激しい対立感情を和らげる解など、容易に出せるはずがないと、あきらめに似た気持ちに襲われた。
旅の終わり、もう一度アビハイのキブツを訪ね、最後の中継リポートを行った。仕事を終えて現場を離脱し、近くのガソリンスタンドに立ち寄ったところで、ガザから砲弾が放たれ、警報が鳴った。スタッフは全員地面に伏せた。そして、イスラエル軍の迎撃ミサイルが相手の砲弾を撃ち落とした。
恐怖を感じたが、「目を覚ませ」と言われたようにも感じた。これからも、この現実から目をそらしてはならないと思った。ジャーナリストとしてこの地を見て、戦争の肌触りを知ることができたひとりとして、伝え続けようと思う。そしていつか、段階的な解決への小さな糸口が見えたら、いち早くそのことに気づき、発信する存在でありたい。
5日間の駆け足の旅を終え、機中の人となった僕は、なかなか眠りにつけない中で、強くそう思った。
(敬称略)
(2023年12月27日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)