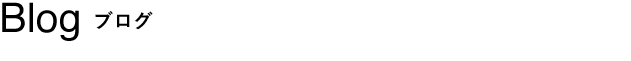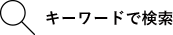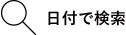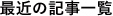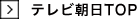- トップ
- ブログ
- 屍を越えて…
- 2023年11月13日
「屍(しかばね)を越えていけ」という言葉は、これまでに戦記物の小説やドラマの中で、何度か目にした。自分の命はここで尽きるが、どうか後に続く者は思いを引き継いで、目的達成のために戦ってほしい。そんな意味だと漠然と捉えてきた。
しかし、あるノンフィクションを読み返してみて、「屍を越えていけ」には、むしろ全く逆の意味も込められているのではないか、と考えるようになった。
読み返したのは、おととし亡くなった、「歴史探偵」こと、先の大戦をめぐる作家の半藤一利さんの代表作「日本のいちばん長い日」である。この作品で半藤さんが着目したのは、昭和20年8月14日の御前会議で、昭和天皇によるポツダム宣言受諾の「ご聖断」が下されてから、翌15日に国民に向けた玉音放送が流されるまでの、極めて危うい1日のタイムラインだった。
自らマイクの前に立ち、降伏を国民に伝えることを厭わないという昭和天皇の言葉に従い、時の鈴木貫太郎内閣の面々や天皇の侍従たち、さらには日本放送協会の「放送員」たちは、翌日の玉音放送の準備に奔走する。
が、ことは簡単には運ばない。降伏に納得できない陸軍将校たちは、「全陸軍が一丸となって最後の一兵まで戦えば、かならずや死中に活をうることが可能だろう」と思い詰める。その精神的支柱は陸軍大臣の阿南惟幾(あなみ・これちか)大将であった。
多くの軍人に慕われ、帝国陸軍を代表して入閣していた阿南陸相だが、戦争末期は、降伏へと傾く鈴木首相や閣僚たちと、戦争継続を訴える軍人たちとの板挟みとなってきた。作中、こんなくだりが出てくる。
陸軍出身の安井藤治国務相が、士官学校同期の陸相の心情と立場を思いやって、人影のないところで、ざっくばらんに聞いた。
「阿南、ずいぶん苦しかろう。陸軍大臣として君みたいに苦労する人はほかにないな」
「けれども安井、オレはこの内閣で辞職なんかせんよ。どうも国を救うのは鈴木内閣だと思う。だからオレは、最後の最後まで、鈴木総理と事を共にしていく」
と阿南陸相はしっかりといった。
阿南陸相は、降伏後の天皇陛下の地位の存続(国体の護持)に不安を覚えながらも、「心配しなくともよい。私には確証がある」との天皇自身の言葉を聞く。そして、聖断が下されればこれに従うのみとの決意を固めた。同時に、血気にはやる若い軍人たちの気持ちも理解できる。陸相はそれを抑えなければならないと覚悟した。
この時、阿南陸相はすでに自決の腹を決めていた。そして、降伏の聖断ののち、陸軍省の将校たちを前に言った。
「聖断は下ったのである。いまはそれにしたがうばかりである。不服のものは自分の屍を越えてゆけ」。
これは、なお戦いを願う者は、自分の屍を踏み越えて、存分に戦いを続けてほしい、という意味だろうか。いや、そのような解釈にはならない。
自分は敗戦の責任と、天皇に苦渋の選択を強いた責任をとることにした。そして、当時としては絶対である天皇の聖断がとうとう下ったのだ。ここに至っては、不服を抱く者も自制すべきである。どうしても蜂起すると言うなら、自分の屍がそこに断固として立ちはだかる。
実はそんな意味が込められていたのではないか。
とはいえ、聖断が下った後、やはり何人かの将校が決起してクーデターを起こした。宮城(きゅうじょう)を支配下に置き、天皇への直談判を試みた。その鬼気迫る緊張は半藤さんの著作に余すところなく描かれている。
しかし、クーデターは鎮圧される。その行く末を、半藤さんはこんな風に描写している。
このころ(中略)、阿南陸相自決の報が伝えられた。省内の空気はみるみる一変していった。陸相の従容たる最期が、士官たちの沈み、荒んだ心に、かすかな灯をともしたようであった。敗戦―この冷厳な事実にたいして、ふっきれない軍人的心情は変わらぬとしても、省内の統制は恢復(かいふく)しつつあった。陸相の死が、武人の義務をひとびとの心によみがえらせた。陸軍省は心に喪章をつけて喪に服した。
僕は自決をもって潔しとする当時の気風に、決して賛同するものではない。それに、半藤さんのこの代表作を読み解いた書評など星の数ほどあるだろうから、その末席に加わろうなどとも思わない。
ただ、僕がこの本を手に取ったのは、パレスチナ自治区ガザやイスラエルで、あるいはウクライナで繰り返される殺戮行為と、残酷に積み上がる死者の数に、どうにもやりきれない思いが募るからだ。戦争の終わらせ方について、少しでも学びたかった。
尊い命は、なぜ失われ続けなければならないのか。イスラエルの高官が述べるような、「ある程度の民間人の犠牲はやむを得ない」というほどの大義とは、果たして何なのか。
それぞれの主張する正義はあるだろう。しかし、これまで積み重なった累々たる屍は、血気にはやった者たちが「乗り越えていく」対象ではない。屍を前に恐れおののき、世界はやはり立ち止まるべきなのだ。
ミサイルの飛んでこない遠い日本にいるわれわれも、同じ時代を生きる当事者でありたい。せめて、悲劇から目を背けることがあってはならない。
(2023年11月13日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)