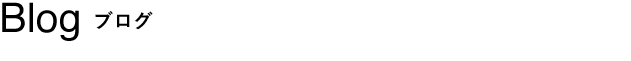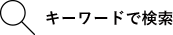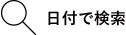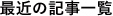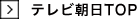- トップ
- ブログ
- 助けられなくて
- 2022年11月05日
ソウルの繁華街・イテウォンで起きた密集事故は、若者を中心に156人もの命を奪った。事故現場で花を手向ける人の中には、「助けられなくて申し訳ありません」とメッセージを残す人も多かったという。
この謝罪の言葉は、8年前、修学旅行の高校生を乗せた客船・セウォル号が沈没した事故でも聞かれた言葉だった。299人が死亡、5人が行方不明となったこの事故は、われ先にと逃げ出した船長の行動とともに、時のパク・クネ政権への強烈な批判となり、政権の土台を揺るがした。
僕も、この事故を取材に行った。港には、行方不明となった子どもたちの帰りを待つ家族がテントを連ね、支援者のグループが慌ただしく活動していた。港のフェンスには数えきれない黄色いリボンが括りつけられていた。そこに書かれていたのが、やはり「助けられなくて申し訳ありません」という言葉だった。韓国じゅうからたくさんの人たちが港を訪れ、リボンを結び付け、海に向かって涙していた。
8年を経て、「申し訳ありません」との文字が、今度はイテウォンの街に現れた。警備体制に万全を欠いた警察当局や政府への怒りの言葉とともに。
デジャブを感じた。そして、現場に飛んだ報ステのスタッフの取材結果を聞くうちに、「申し訳ありません」の意味が、よく分かるようになっていった。それも、対岸のことではなく、我が事として。
イテウォンの事故は、第二のセウォル号事件という人がいた。若者たちは静かにデモを繰り返していた。「こんな社会で死ぬのは嫌だ」と書かれたプラカードを持つ男性もいた。
セウォル号事故の時に高校生だったという女性は、当時、自分の修学旅行が中止になったという。その上、おそらく彼女は、若くて人生で最も活動的な一時期をコロナのパンデミックで封じられた。ようやくコロナの行動制限から逃れ、ハロウィンの賑わいも戻ったというのに、今度は密集での悲惨な事故に社会は沈んだ。彼女のやるせない気持ちが伝わってきた。
多感な青春期の節目に、ことごとく不幸に見舞われる。そうやって社会に出る若者は、社会の安全や安心を信じられるだろうか。「こんな社会で死ぬのは嫌だ」という本音は、そういう社会を「作ってきた」親世代の胸を突く。
事故への怒りを静かなデモで表す若者たちを見ながら、60歳代の女性が言った。「こんなデモをさせる結果になるなんて・・・。大人の無関心がこうさせたのです」彼女は、セウォル号の教訓が生かされなかったことに悔恨の気持ちを隠さなかった。「若い人たちに申し訳ありません」。最後に振り絞ったのはやはり謝罪の言葉だった。
この言葉を聞いて、僕の胸にも強烈に響くものがあった。
僕もまた、今回犠牲となった若者たちの親世代だ。同じことは日本にも当てはまるではないだろうか。
僕たちの世代は、若いころ、いわゆる右肩上がりの時代を生きてきた。きょうよりあすが、あすよりあさってが良い日になると信じることができる時代だったのだ。
ところが、1990年代のバブル崩壊を境に、右肩上がりの日本経済など非現実的となった。その後は「失われた10年」と言われた。それは、我々の自信を喪失させるのに十分な時間だった。失われた10年は20年に延び、いまや「失われた30年」という言葉が飛び交う
その間、富は偏在して格差が広がり、生きづらさを訴える若者が増えた。
地球規模で見ても、温暖化は徐々に地球を蝕み、対策は地球の悲鳴になかなか追いつかない。責任ある大国であるはずのロシアは傍若無人に隣国を侵攻し、巨大国家・中国は唯我独尊。北朝鮮は核弾頭をいつでも打ち込む用意ができているように見える。
閉塞と不安の中にあって、出口がなかなか見つからないのが今の時代だ。
そう。そんな社会に誰がした。僕らの世代、つまり若者たちの親世代がそうしたのだ。素晴らしいスピードでバトンを受け取りながら失速し、ほうほうの体で次の世代にバトンを渡そうとしている。それが僕たちの世代なのだ。
何もそこまで自虐的になる必要はないのかもしれない。我々の世代だって良いものは残したはずだ。戦争を知らない世代として育ち、実際、先人たちの教えを守って、日本が戦争に巻き込まれることのないように丁寧に時間を紡いできた。
優しく、繊細で発想豊かな日本文化の担い手ともなった。今も日本が世界から一目置かれるのは、経済のみならず、こうした文化面での貢献だって大きい。
だから、残された時間は多くなくとも、せめて若い世代の視野が開けるように、まだまだ頑張りたい。若い世代をよっこらしょと肩車して見せるくらいの体力は残っているはずだ。
だが、それでも、なのである。僕たちはリレー走者として責任ある仕事をしたのだろうか、と考えてしまう。いい時代を生き、そのまま逃げ切ってしまいそうな自分を苛む気持ちになる。
イテウォンの事故で亡くなった、2人の日本人女性のご遺体が、相次いで帰国した。
運ばれてきたのは貨物機だった。仕方ないことなのだろう。
だが、無言の帰国をした彼女らを乗せた飛行機に「CARGO」の文字が見えたとき、とても切ない気持ちになった。そして、ソウルで親世代の人たちが発していた言葉が、自分の中でもこだました。
「助けてあげることができなくて申し訳ありません」。
(2022年11月5日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)