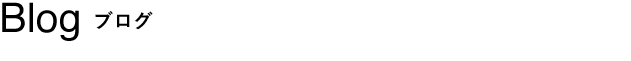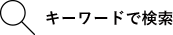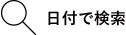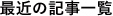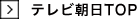- トップ
- ブログ
- 佐賀関にて
- 2025年11月24日
夜8時前だったか。18日の火曜日のことだ。この日の番組総合デスクが僕のところに走って来た。「大分の火事、大変なことになっています。今夜はこのニュースから入ります」。午後9時54分からいつもどおり放送は始まったが、強風注意報が出されている現地では、火勢は激しくなるばかりだ。
現場に急行した大分朝日放送の若手アナウンサーが、中継リポートでたびたび情報を更新してくれた。目に入る光景をはじめ、臭い、風の強さなど、五感をフル稼働してのリポートだ。そして火災は住宅密集地のみならず、背後の山の中腹に至り、そこに建つお寺が激しく燃えていた。番組の最後、この日何回目かの中継リポートでは、遠く海に浮かぶ島にまで飛び火した様子が映し出されていた。
番組を終えてスタジオを出ると、チーフプロデューサーとアイコンタクトをし、翌日の朝から僕自身が大分に飛ぶことを決めた。強風による密集地火災と言えば、2016年に新潟県糸魚川市で起きた大火以来の規模ではないかと思われた。
大分市佐賀関(さがのせき)。古い野球ファンなら、「日鉱佐賀関」という社会人チームの強豪がかつて存在し、後楽園での都市対抗野球などで活躍していたことを知っているはずだ。大学の野球部に所属していた時の僕も、佐賀関という地名は日鉱(当時の日本鉱業)の製錬所とのセットで記憶していた。
この地が、四国との間の急な潮の流れで育まれたブランド魚・「関アジ」や「関サバ」の産地であることは、僕の場合、一人前に舌が肥えてきたころにやっと知った次第ということになる。
大分空港から車で1時間半余り、トンネルを抜けると大きな煙突が現れた。今はJX金属と社名が変わった佐賀関製錬所の象徴である。佐賀関の街は半島のくびれた根元部分に密集していて、市街地の細い道を行くとすぐに佐賀関漁港に到着した。漁港から大規模災害の現場までは数百メートルといったところだが、警察が厳しく立ち入りを規制している。
港の突堤に立つと、湾の向こうに山肌が見え、その上を縫うように墓地がある。墓地の先にはすっかり焼け落ちたような黒い跡があるが、おそらく前日の晩に炎上するのを見たお寺だろう。右手に目をやると、1キロほど離れた無人島(蔦島)から煙が立ち上り、ヘリによる消火活動が続いていた。
車で半島を裏手に回り、高台から市街地を臨む。すると、そこにはあっと息をのむ光景が広がっていた。黒く煤けたコンクリート製の建物が見えた。逆に言えば、そのコンクリート以外はすべてが焼け野原である。なんという残酷か。この時点で被害が及んだ住宅などの建物はおよそ170棟、被害面積は5万平方メートル近くに及んでいたのである。
この位置からは炎こそ見えなかったが、消防隊員が盛んにホースで消火活動を続けていた。火種を完全に消すのが容易でないことが分かる。その光景に驚いた僕だが、しばらくして身体がもうひとつの驚きに反応しているのに気付いた。強烈な焦げ臭さである。
漁港に戻る。漁港は火災現場の風上にあり、僕が来ているコートに染みついたそれ以外、あたりに臭いはない。風上か風下かでこうも違うのだと改めて思い知らされた。
漁港で地元の人たちに話を聞いた。港から火災の広がりに目を凝らしていたという男性は、「あんなに火の回りが早いのは初めて見た。あっという間だった」と語った。
警察の規制線のすぐ向こう側で悄然としている男性に声をかけさせてもらった。家は焼けたそうだ。「火の粉がすごくて、逃げるのに必死でした」というこの男性に、「避難所には行かないのですか」と聞くと、「ペットを連れて逃げたもので…。ペットが他の人の迷惑になるかと、きのうは車中泊をしました。たぶん今日も」と疲れた表情で答えた。
この大規模災害では、残念ながら、火元とみられる住宅から男性ひとりの遺体が見つかっている。だが、それ以外の人たちについては避難が迅速に行われた。
被災した住民たちは、いったん漁港に近い公民館に着の身着のままで避難した人が多かったそうだ。だが、その場所も危ないとの判断から、1キロ弱のところにある大分市の佐賀関市民センターに身を寄せた。夕刻近くになって避難所となった市民センターを訪ねると、すでにおにぎりやうどんなどの炊き出しも始まっていた。避難した人同士、不安混じりの表情であちこちに話の輪ができていた。
88歳の女性に話を聞くことができた。航空写真で自宅が全焼しているのを確認したという。ひとり暮らしだが、すぐ近くに息子家族も住んでいるので心配はないと気丈に語った。「もう起きてしまったことは仕方ない。プレハブでも何でも、住むところがあればこれからだってひとりでやっていきます」。僕は思わず「お強いですね」とつぶやき、相槌を打っていた。
この女性の声にむしろ背中を押される形で、僕はその夜の中継リポートに立った。場所は、まるで取材拠点となったかのような、漁港の突堤である。
僕はその日一日で見たもの、聞いた話を洗いざらい話した。特に、大半の住民が何とか避難できた事実、それを可能にした消防団員たちやご近所の「声かけ」、つまり地域の絆の強さなどを強調した。
だが、中継の途中から、港に煙が漂い始めた。突然風向きが変わったと見られる。それまでは臭いのなかった港に、突如として焦げた臭いが充満し始めた。そればかりでなく、日中ヘリコプターからの消火活動で抑え込んだと見られる無人島からまたも火の手が上がり始めた。
つまり、火災はまだ終わっていないのだ。僕はその現実に、ふた晩目の生放送のさなかに気づかされたことになる。
そして、当然のことながら、住民の苦難もこれからなのだ。
僕より一足早く現地の取材に入っていた下村彩里アナウンサーのクルーは、僕が帰京した後も佐賀関に残り、避難所での取材を続けていた。金曜日の放送では、僕も取材した88歳の女性をインタビューした様子が映し出されていた。
気丈だった彼女だが、その表情には疲れがにじんでいるように見えた。今後の暮らしに不安を抱えていた。今までは玄関も空け放してご近所と語らう生活だった。だが、元の場所での生活が戻ったとしても、以前と全く同じ暮らしはできないのではないかと彼女は言う。
命からがら逃げだすことができた住民たちだが、長い試練は始まったばかりなのだ。街となりわいの再生は容易ではない。この地域の老若男女の前に立ちはだかるのは、元の暮らしに戻るというよりも、新たな暮らしを手に入れるという困難な作業なのである。
また来よう、と思った。仕事であってもプライベートであっても。どの災害もそうだが、地元住民の皆さんの暮らしの再建に寄り添う姿勢を、取材者は忘れてはならない。そして、この街がダメージを乗り越え、新鮮な海の幸をひとりの旅行者として味わえる日が、一日も早く来ることを願っている。
(2025年11月24日)
- 2026年3月 (1)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)