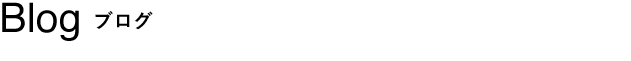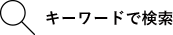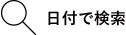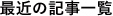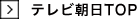- トップ
- ブログ
- お茶っこで復興
- 2024年03月11日
「復興」という言葉を、僕は心の中で消化できずに来た。あの東日本大震災から13年が経つというのに。
宮城県石巻市雄勝(おがつ)町を訪ねた。湾が入り組んだ風光明媚な港町。しかし、巨大津波で住宅の8割が全壊し、街は一変した。いま、人口は震災前から4分の1に減った。
海沿いには高さ10メートル近い防潮堤が全長3キロにわたって建設された。街の中心部だった場所は防潮堤の高さにまでかさ上げされ、道の駅や特産の硯(すずり)の展示館などが整備されている。今は人々の憩いの場となり、僕が訪れた週末には、伝統の獅子舞や太鼓が披露され、高齢の女性が楽しそうにリズムをとっていた。
だが、海と生活を遮断した防潮堤によって、港町はまるで要塞のようでもある。県の大号令のもとに建設されたこの防潮堤の威容もまた、「復興」のひとつの形ということなのか。
阿部晃成さん(35)は、そこに疑問を投げかける。津波で一家7人が海を漂流するという恐怖の末、生き延びた。20代の若さで街の再建のための協議会に参加し、議論を重ねる中で、防潮堤とともに街を高台に移転する案に、強い違和感を覚えたという。
「1000年に一度の津波でも人が死なない街を作ろうということでしたが、結局、人が住めない土地になってしまった。まずは被災者の生活再建をしてから、その中で防災、減災を高めていくステップが大事だった」と言う。しかし、「ゼロリスクでありたい」という声の中で、阿部さんの意見が通ることはなかった。
「全部ハードでやりますよ、という復興を進めていけばいくほど、それに合わない人たちは結局、みんな出て行ってしまった。これが復興かと言われると、私はそうは思わない」。
阿部さんはいま、雄勝町内の別の場所に新たに居を構え、公立宮城大学の特任助教として災害復興を研究している。能登半島地震の被災地にも出向き、自らの経験を伝えながら、地域の特性に合った地域の再建を、共に考えていきたいと思っている。
雄勝町内には、道の駅などの施設がある場所からさらに20メートルほど高い場所に、山を切り開いて宅地が造成され、家が建設された。その事業は当初予定の3年を大きく超え、7年近くかかった。阿部さんが指摘するとおり、避難所から仮設住宅などに移り住んでいたかなりの被災者たちが、雄勝で家を再建することを諦めた。
だが、離れた人たちの中にも、前向きに新しい暮らしを作っていこうと努力する人がいる。雄勝から車を走らせること約30分。石巻市内の災害公営住宅「二子(ふたご)団地」で暮らす山下憲一さん(76)はそういう人だ。二子団地にはおよそ130世帯の雄勝出身者が暮らしている。
二子団地を訪ねると、そこはコンクリートの高層住宅ではなく、間隔を広く取った戸建てが並んでいた。家々の間にはフェンスなどの仕切りがない。玄関にスロープを付けた家が多いが、駐車場の配置や家の間取りはさまざまだそうだ。
「設計士や大学の先生とかも含めて25回くらい集まりました」と振り返る山下さんは、二子西町内会の会長でもある。着工以来、入居者の意見調整は大変だったが、山下さんは、それだけの手間暇をかけるだけの意義があったと思っている。あえて仕切りをなくしたのは、高齢者が多い住民同士、孤立を防ぎ、いつでも助け合えるようにするためだ。この団地は総合病院も近いし、買い物も便利だ。
山下さんは、石巻市と合併する前の、旧雄勝町の教育委員長も務めた。「日本一の町だったと自負している。海に行けばなんでも釣れる。山に行けばキノコを採ったり山いもを掘ったり、山菜も自由に採れた。あれだけ恵まれたところはない」と振り返る。だが、行政が計画する高台移転は、自分が望むものではない。だから、二子団地に移り、その団地を住みやすい場所にすると、考えを切り替えた。
「思いが10個あったら、5つか6つくらいを持って、4つくらいは置いて前の方に進まないと。前の思いを背負ったままじゃあ…」。
山下さん流の「復興」の考え方である。
震災から7年と、高台への移転にずいぶん長く時間がかかったが、それでも雄勝に家を再建し、「充実してます」と屈託がないのが、佐藤美千代さん(74)だ。「いいなあって思う、今の生活。お父さんには申し訳ございません、くらいの感じでね」
雄勝を離れなかった理由を聞くと「お父さんが、海が好きで」という言葉が何度も出て来る。だが、共に青果商を営んでいた夫の勝則さんは、新しい家に入居することなく他界した。
一人暮らしになった佐藤さんだが、寂しさを感じることはないという。
「お茶飲みに来ない?って言うと、ここに皆さん集まってくれる。誰それさんがどうのこうのって、話には事欠かない。お茶に誘う時に、きょうはゴマプリンを4つしか作らないから4人だけにしとこう、とか。きょうはなんだかんだあるから6人とか。いつだったか11人に声をかけたこともある」
この地方の「お茶っこ」の文化だ。われわれ取材クルーも恩恵に浴し、お茶を飲みながら、佐藤さん手作りの茎ワカメの佃煮とか大学芋とかを散々ごちそうになった。そのうちに佐藤さんは、雄勝に残った一番の理由を語った。
「やっぱり子や孫に、ふるさとを残しておかなきゃと思って。お盆とかお彼岸の時に来て、ぐるっとお墓を回ってお線香つけて行くっていうのもある程度、教えておかないと」
そう言う佐藤さんの手元には、亡くなった勝則さんが元気だったころの、子どもと孫、総勢14人の家族写真があった。
僕は「復興」という言葉を消化しきれずに来たが、考えてみれば当たり前なのかもしれない。この13年間、愛する人を失い、家や仕事を失った人たちが歩んできたいばらの道は、想像を絶するものだっただろう。復興という言葉がうつろに響くほどに。
だが13年を経て、気力を取り戻した人も少なくない。一番若い阿部さんが話していた言葉が胸に残っていた。そもそも復興とは何ですかという、僕の問いに対する答えだった。
「復興というのはものすごく曖昧なものだと思います。それに対して、被災者たちが、一緒に肩を並べて、そのあいまいな復興とは何かを見つけ出すプロセスそのものが、復興なのだと思っています」
その意味では、能登の復興に貢献したいと考える阿部さんも、二子団地をより住みよい場所にしようと努力している山下さんも、「お茶っこ」でご近所を笑顔にする佐藤さんも、まさに復興を体現する人たちなのだと思う。
(2024年3月11日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)