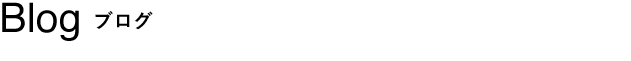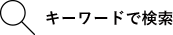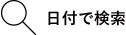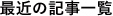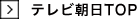- トップ
- ブログ
- あの沢木耕太郎さんに会った
- 2023年09月04日
ノンフィクションの巨匠と言われる人である。
作家の沢木耕太郎さんへのインタビューで、「なるほど」とうなずいたいくつもの言葉があった。以下はそのひとつだ。
「その人の感受性がもし優れていれば、そこのタバコ屋まで行く紀行文の方が、アフリカのサハラ砂漠を横断するより、はるかに面白い紀行文になりうる」。
沢木さんによると、これは小説家・吉行淳之介の言葉からの引用を含むということだが、ボクシングを題材としたルポルタージュなどで知られる沢木さんは、この考え方を発展させて、こんなふうにも語った。
「井上君の素晴らしい試合を書く。すごく素晴らしいスポーツ・ライティングになるかもしれない。一方で、その前座の4回戦の試合に出ている若者のことを、ちゃんと感受性をもって、取材をいっぱいして本当に書ければ、それは井上君の試合と拮抗するもの(ルポルタージュ)になるかもしれない」。
井上君とは、「日本ボクシング史上最高」とも言われる圧倒的実力を備えた、あの井上尚弥選手のことである。超人的なアスリートの物語は輝きを放つ。しかし、無名の4回戦ボーイの人生にだって、魅力的な物語は潜んでいると、沢木さんは言うわけだ。
物語といっても、沢木さんが取る手法は主にノンフィクションである。ある人物への取材を通じて、事実(ファクト)の中から、人生の物語をくっきりと掘り出す。そのためには、取材対象者である人物と深い信頼で結ばれ、真実や本音を語ってもらえるだけの関係を築かなければならない。沢木さんは長年、その仕事を続けてきたのだ。
僕も取材者の端くれとして、そのことにはとても興味がある。実は今回のインタビューは、日本家屋の縁側にふたりで座る形で行ったのだが、その位置関係を示しながら、取材における「沢木流」を語ってくれた。
「こうしてふたりで、ちょっとこっちを向いて、それってすごく話しやすい。むしろ、正面を向くと話しにくくなるじゃないですか」。
なるほど。そして沢木さんは続けた。
「実は、もっと話しやすいのは、何か重い荷物を、ふたりで片方ずつ持ち合って歩いていくとき。ハーハー言いながら、『それでさ、あのさ』などというときが、一番深いです」。
中身もそうだが、僕はなんだか、沢木さんのカッコよさにクラクラしてしまった。
バックパッカーのバイブル的作品となっている「深夜特急」シリーズをはじめ、沢木さんの作品に魅了された人は数知れない。タートルネックにジャケットという若き日の沢木さんの写真は、彼より少し後輩にあたるわれわれ以下の世代には、素晴らしく魅力的で、かつおなじみのアイコンと言っていい。その沢木さんが、写真ではなく実際に僕の前にいて、しびれる言葉を発してくれているのだから、こちらはいつでも脳しんとうを起こす準備はできていた、ということになる。
とはいえ、いつまでもクラクラしていても仕方ないので、「重い荷物をふたりで片方ずつ持ち合う」関係について、もう少し考えてみたい。
この言葉は、自分と家族や友人、恋人といった関係性についても、とても示唆を含むものだと思う。正面切って向き合うという、どこか肩の凝った姿ではなく、さりとて淡泊でもない。互いに重い荷物を持ち合う関係になれたら、とても素敵なことだと思うのだ。夫婦間や、職場の人間関係についてお悩みのご同輩、いかがでしょうか。
そして当然ながら、取材者としての僕たちの仕事についても、大いに刺激となる言葉だった。思えば僕も現場の政治記者時代、ごくわずかだが何人かの政治家と、重い荷物を持ち合うような関係になれたように思っている。口の悪い人には、「政治家と政治記者の癒着」などと言われたこともあるが、冗談じゃない。そんなに安っぽいものではない。
それは、いまの「報道ステーション」の現場、つまり、番組のディレクターや記者、アナウンサーたちについても言える。
ニュースに追われる毎日だ。日々、新たな事態に遭遇し、取材先を探し、限られた時間の中で、最適な報道を目指す、その繰り返しではある。ニュースをかろうじて「消費」しているのだと言われればその通りだ。
しかし、その限りでもない。
誠意をもって取材に当たることで、それが仮につらい現場であったとしても、取材者に信頼を寄せてくれる人は決して少なくない。例えば災害現場では、取材を終えれば文字通り、「重い荷物」を持って片づけを手伝うことだってある。形は様々だが、そうやって取材先との間で信頼関係が培われるようになれば、多くの取材者は、仕事の面でも、そしてひとりの人間としても、測り知れないものを得る。
それはまた別の現場に活かされることもあり、人間同士、生涯の付き合いに発展することも珍しくない。取材という仕事の醍醐味である。
僕は先日、62歳になった。還暦を2年も超えてしまった。それなのに沢木さんと会ってから、僕は取材とは何か、などという青臭いことを本気で考え直している。その沢木さんは、僕よりも10歳以上年上で、そして僕よりずっと青臭い。
そして沢木さんは老境に入った今を語った。
「もう60、70歳になったら、何か目的に向かって、『生き方』というレールを自分に設定して突き進む必要はないんじゃないか。心地よい自分の『あり方』を連ねていけばいいんじゃないか。その集積の向こうに『死』というものがあるとすれば、それが明日であっても文句は言わない」。
ある種の美学と言っていい。枯れた風情を漂わせつつも、このカッコよさは、すなわち沢木さんの「生き方」そのものと言っていい。「生き方」を「あり方」へとさらりと颯爽と置き換えてしまうあたりに、われわれが憧れてやまない「沢木耕太郎の本質」があるような気がする。
沢木さん、ずるいなあ。
(2023年9月4日)
【特集】「楽しめること1個を見つける」“晩年を生きる美学”作家・沢木耕太郎に聞く
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000313800.html
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)