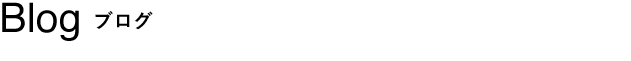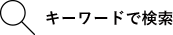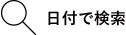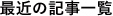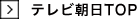- トップ
- ブログ
- 帰り道
- 2023年01月15日
「帰り道、間違うてかわいそうやね」。
大阪湾で息絶えたマッコウクジラを見ながら語った初老の男性の言葉には、万感がこもっていた。男性はこうも言った。
「われわれ(人間)も一緒…」。
動物にとって、戻るべき場所を見失うということは、すなわち死を意味するのだろう。
「淀ちゃん」か「ヨドちゃん」か。どう表記するかは別として、日本中の人たちが目を凝らした存在だった。
全長なんと15メートルのマッコウクジラ。大阪の淀川河口という、大都会の玄関口にやってきた巨大な哺乳類。人間も顔負けかもしれない知性の持ち主。
しかし、生き物である以上、死ぬ時が来る。まさか自分の死にざまを、日本という国に住むたくさんの人間が見守ることになろうとは、本人?もさすがに予想していなかっただろう。
「淀ちゃんという呼び名までついてしまったから、なおのこと切ないニュースですね」と、報道ステーション金曜日担当の板倉朋希アナウンサーは言った。
そうなのだ。それくらいの愛着をもって、人々はその動静を見守った。
現代社会の都市住民は、生き物の生死の場面に遭遇する機会が減ったと言われる。魚の切り身を見て、お頭も尾ひれもある魚の姿を想像できない子どもだって少なくない。
しかし、よくよく考えれば、生きることは死ぬこととセットだ。同じ生き物である人間が、そのことに鈍感であっていいはずがない。
そんな人間の横っ面を張るようにして現れたのが、巨大な迷子クジラだったのだ。
1月9日のことである。法律上は18歳が成人でありながら、慣習として20歳の晴れ着姿が街にあふれるどこか不思議な祝日に、このクジラは現れた。
盛んに潮を吹く姿は壮観だった。映像を見て胸が躍った。大阪湾沿いには、たくさんの見物人が訪れた。
ところが、専門家の見方は楽観的なものではなかった。
マッコウクジラは、400メートルほどの深さの海で、イカなどを捕食して生きるという。群れを作るのが一般的だ。それなのにこのクジラ君は、たった一頭で、干潮時の水深わずか2メートルになる大阪湾に迷い込んだまま、その場にとどまっている。
体調は芳しくないだろう。体内にため込んだ脂肪で、1か月程度食べずに生き抜くことは可能だが、その間に元の深海に戻っていくかどうかは不明。いや、むしろ死期を悟って、浅瀬に身を横たえているのではないか。そんな見立てが相次いでいた。
おもしろうて やがて悲しき 鵜舟かな (松尾芭蕉)
情緒豊かな長良川の鵜飼いを詠んだ一句だ。鵜匠に操られ、魚をくわえてきては吐き出す鵜(う)の悲しさと、そうして獲った魚を食べて生きる人間の悲しさが染み入る句である。
勢いよく潮を吹くマッコウクジラの姿に喝采を送りながら、その行く末を思えば、そこにあるのは悲しさだ。そのクジラを面白がる自分たち人間という存在も、ある種の悲しさを帯びている。芭蕉の句に通ずるのはそれだ。
クジラが淀川河口に迷い込んだ理由は分からない。ただ、番組の取材チームによると、大阪湾はこのところ海水温の上昇が見られ、魚種にも変化があったと地元の漁師が証言しているという。これまではなじみのない魚たちが大阪湾にやってきて、それを獲物にしようと追ううちに、クジラは湾の浅瀬に乗り上げたか。
人間は自然環境を勝手に大きく変えてきた。もし、人間の営みの結果としてクジラの悲劇が生まれたのだとすれば、私たちはそこに何を思うべきなのか。地球の主として君臨する罪深い生き物として。
番組デスクのひとりが、小首をかしげてつぶやいた。
「迷子になったのはクジラなのかな。むしろ人間の方かもしれない」。
ふとした一言。同僚たちは、「ずいぶんしゃれたセリフを…」とはやし立てそうになったが、すぐに同様に考え込む顔つきになった。
確かにその通りだ。帰り道が分からなくなっているのはクジラだけではない。クジラは人間の写し鏡。ひょっとしたら帰り道に迷ってしまったのは、生き物としての原点すら分からなくなってしまった、われわれ人間の方なのかもしれない。
僕の傍らに眠っているのは、小夏という猫である。
神社の床下で見つかった時には首輪の痕があった。もともとは誰かのペットだったのが捨てられたのだろう。この猫も帰り道を失ったわけだ。
縁あってわが家にやって来た。おとなしい猫だから家出することはないと思っているが、仮に旅に出たとしても、帰る場所はここだよ。
(2023年1月15日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)