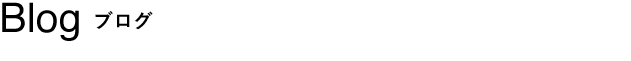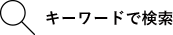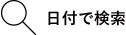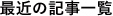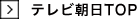- トップ
- ブログ
- 慰霊の日に
- 2022年06月23日
6月23日。太平洋戦争末期・激しい地上戦が繰り広げられた沖縄戦から77年となる「慰霊の日」を、沖縄・糸満市にある平和祈念公園から伝えた。
この平和祈念公園に来たのは何回目だろうか。おそらく、最初はアメリカのビル・クリントン大統領がこの地を訪れた2000年のことだったと思う。もう22年も前か・・・。
大統領のスピーチに先立って、戦争を語り継いでいく決意を述べたひとりの女子高校生の言葉に、大統領が神妙に聞き入っていたのを思い出す。僕は取材者として、傍らでその場面を見つめていた。
平和祈念公園の中に、放射状に位置するいくつもの碑が「平和の礎(いしじ)」である。沖縄戦などで亡くなった24万人を超える人たちの名前が、地区ごとに刻まれている。5人、6人と同じ姓の名前が連なっているのは、ひとつの家族だからだろうか。
「平和の礎」の前に立つと、膨大な数の戦争の犠牲者ひとりひとりに名前があり、大事な日常があったことを認識する。当たり前のことなのに、今さらながらに気づかされるのだ。戦争は、そうしたかけがえのない命と暮らしを奪っていく。
番組本番、中継カメラと向き合いながら、僕は噛みしめていた。ああ、沖縄ではこうして季節が巡っていくのだと。
この6月、僕は2回沖縄を訪れた。1回目は1週間前の6月17日だった。ウクライナ出身で、今は糸満市の喜屋武岬の近くに暮らす女性にインタビューした。彼女は、現在進行形で母国を苛む戦争と、77年前の沖縄の悲劇を重ね合わせるように、その思いを語っていた。
この日は梅雨末期の強い雨が、断続的に降っていた。蒸し暑く、空気までも重苦しい。沖縄戦では、多くの住民がこの雨空の下を逃げ惑ったのだろう。
そして再び沖縄を訪れた23日。梅雨は明け、1週間前とは打って変わって強い日差しが降り注いでいた。慰霊の日の前後は、沖縄ではちょうど季節の変わり目でもあるのだ。
この23日の正午、喜屋武岬でとり行われた、地域住民だけの小さな慰霊式にお邪魔した。そこで、15歳のときに沖縄戦を経験したという91歳の男性に出会った。
「海のところの壕に避難していた。海のところで(人々が)殺された」。
男性は途切れ途切れに言った。15歳と言えば、もう十分記憶に刻まれる年齢だ。
喜屋武岬のあたりは断崖が多く、いくつかの洞窟がある。ある人はこうした洞窟の中に、ある人は根を張った木の間に壕を掘り、上陸した米軍から身を潜めた。そして多くの人が逃げ切れずに命を落とし、限られた人が生き延びた。
「ご両親は戦争で亡くなったのですか」と問うと、
「お父さんは殺された。お母さんは地元で、こっちが(自分が)逃げ回っていた時に探しに来て、やられた」と言う。
話はアメリカ軍が支配した直後のことに及んだ。
「15歳だったから自分は半分大人だった。アメリカ軍が支配してから一緒に働かされた。女も男もみんなテントの中に住んでいた。学校を出るか、仕事をするかと話をしていたが、仕事をした方がいいと(判断した)」。
男性の話を総合すると、アメリカの支配下で、アメリカ兵と一緒にいろいろな仕事をしたのだという。遺骨の収集をしたとも話していたが、それがアメリカ支配後のことだったかどうかは判然としない。仕事はきつくなかったし、食べ物もたくさんあったという。船に乗せられて沖縄各地を移動して仕事をした。
アメリカ軍に両親の命を奪われた15歳の少年は、そのアメリカ軍に身を寄せ、何とか生き延びたのだ。その苦難の青春をどう想像したらいいのだろう。
喜屋武岬での慰霊式には、毎年、お祈りに来ると言う。
梅雨明けの沖縄は暑い。日陰に入って話を聞いたのだが、ご高齢でもあり、長時間は難しい。10分ほどでインタビューを終えた。
「平和の礎」に刻まれた戦争の犠牲者ひとりひとりに大切な生活があったように、生き抜いた人たちにも、その後の大切な生活があった。したたかに傷つき、それでも命をつないできた日々があった。そして、時間の経過とともに証言者は少なくなっていく。
まだまだ知られていないことばかりだ。語りたくないこともあるだろう。しかし、歴史の闇に葬り去ることのできないストーリーは無数にある。ひとつでも多く発掘し、今を生きる世代で共有していくこと。
取材者としての役割の重さを痛感する沖縄取材だった。
2022年6月23日
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)