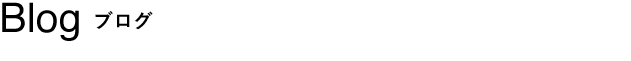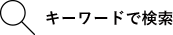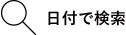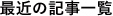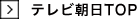- トップ
- ブログ
- みんなでクルリンッパ!
- 2022年05月15日
ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが亡くなったというニュースを知ったのは、11日水曜日の午前中、散歩から帰ってのことだった。若いころの熱湯風呂に始まって、そのギャグには僕もずっと楽しませてもらった人だが、失礼ながら人間国宝級のような大御所ではない。それでもなぜか、この出来事は、大げさに言えば「国民的喪失」のような気がしていた。なんだかとても悲しかったのだ。
だから、この日の報道ステーションの担当デスクから、「今夜は上島さんの訃報をトップニュースで伝えたい」と言われたときには、極めて自然な判断だと思った。
しかし、きょう取り上げたいのはそこではない。
上島さんの死を僕がどうしてこんなに悲しく感じ、実際、僕以外にもそう感じた日本人が多かったという事実(おそらく)についてである。
個人的なことを言えば、上島さんは僕と同じ1961年生まれ。身体を張った芸風を尊敬すらしていた。人間、年齢とともに身体が動かなくなる分、どこか知ったかぶりをすることが増え、理屈っぽくなりがちだ。上島さんは微塵もそんなことを感じさせない。そこがうらやましかった。
悲しみがこんなにも広がったのは、もちろん、多くの人に愛された人ゆえだろう。上島さんを慕う後輩芸人たちが集い、上島さんを囲んで「竜兵会」という集まりをよく開いていたそうだ。テレビカメラというものはうそをつかないもので、その人の人柄をよく映し出す。上島さんなら、後輩たちに時々からかわれたりしながら、笑顔の絶えない集まりだったのだろうなあ、と思う。
でも、悲しみの正体はそれだけではないような気がしている。うまく言えないが、時代性を帯びている、というか。
その人の死に至る胸中など、赤の他人である僕ごときに分かるはずがないし、分かろうとしても無理だろう。しかし、どうしても考えてしまう。そして、今の時代背景がどうしても映り込んでくる。
コロナ禍で、大好きな「竜兵会」も開催は間遠になっていたという。
「熱々おでん」も「仲直りチュー」の芸も、密着とか飛沫を避けられない。披露はかなわず「オレ、何にもできないおじさんになっちゃったよ」と上島さんはこぼしていたそうだ。体当たりの芸風で、笑いをじかに受け取ることで生きてきた上島さんにとって、コロナが大きな心の負荷になっていたことは想像に難くない。
コロナばかりではない。ウクライナでの戦争や、知床沖での海難事故など、命に直接かかわる出来事がこのところ多すぎた。そうした重苦しい時代の風は、ある人たちの心の隙間に入り込み、澱(おり)となってこびりついてしまうことがある。
繰り返すが、上島さんの胸中について何かわかったような顔をするのは僭越だ。しかし、稀代のコメディアンがこの世を去ったのは、そうした風が吹き荒れる中での出来事ではあった。
この日の報道ステーション。訃報のVTRをトップニュースで伝えた後、スタジオのカメラは僕をとらえようとしている。何かを言わなければならないのだが、人の死を軽々しく総括などできない。さて、どんなコメントをするか。
訃報とはいえ、トップに据えたVTRにはおなじみの芸が満載で、僕はつい笑ってしまった。そして僕はそのことを口にした。「わかっていても笑ってしまう。いまも笑ってしまいました。でも、それはある意味、(お笑い芸人である)上島さんへの一番の供養になるのかもしれません」。
言い終えてから、お門違いだったかな、とも思った。お笑いを職業にしていた人とは言え、死についてはもっと厳粛なコメントにすべきだったかもしれない。あるいは短く「謹んでお悔やみ申し上げます」とだけ言うべきだったのかもしれない。
そうして迎えた土曜日。ダチョウ倶楽部の面々のコメントがインスタグラム上に公表された。その中でも、リーダーの肥後克広さんの言葉が印象的だった。一部抜粋させてもらう。
「何をやっても笑いを取る天才芸人上島が最後に誰も1ミリも笑えない、しくじりをしました。でも、それが上島の芸風です。皆で突っ込んでください。(中略)そして、上島の分、3倍笑ってください。皆にツッコまれる、それが上島の芸風です。ダチョウ倶楽部は解散しません」
さすがに仲間だな、同志だな、と思った。悲しむファンの心をやわらげ、亡くなった上島さんも天国で照れ笑いを浮かべていそうなコメントだ。「笑うことも供養」と言った僕まで救ってもらったような気になる。
悲しいことや苦しいことが周りにあふれていても、僕たちはこうして生きているし、生かされている。夜が明ければ朝が来る。肥後さんのコメントの最後は、帽子を回転させて頭に乗っける上島さんのギャグを使って、こんなふうに締めている。
「どんな悲しい事があっても、みんなでクルリンッパ!」。
(2022年5月15日)
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (3)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (3)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (5)
- 2021年10月 (4)