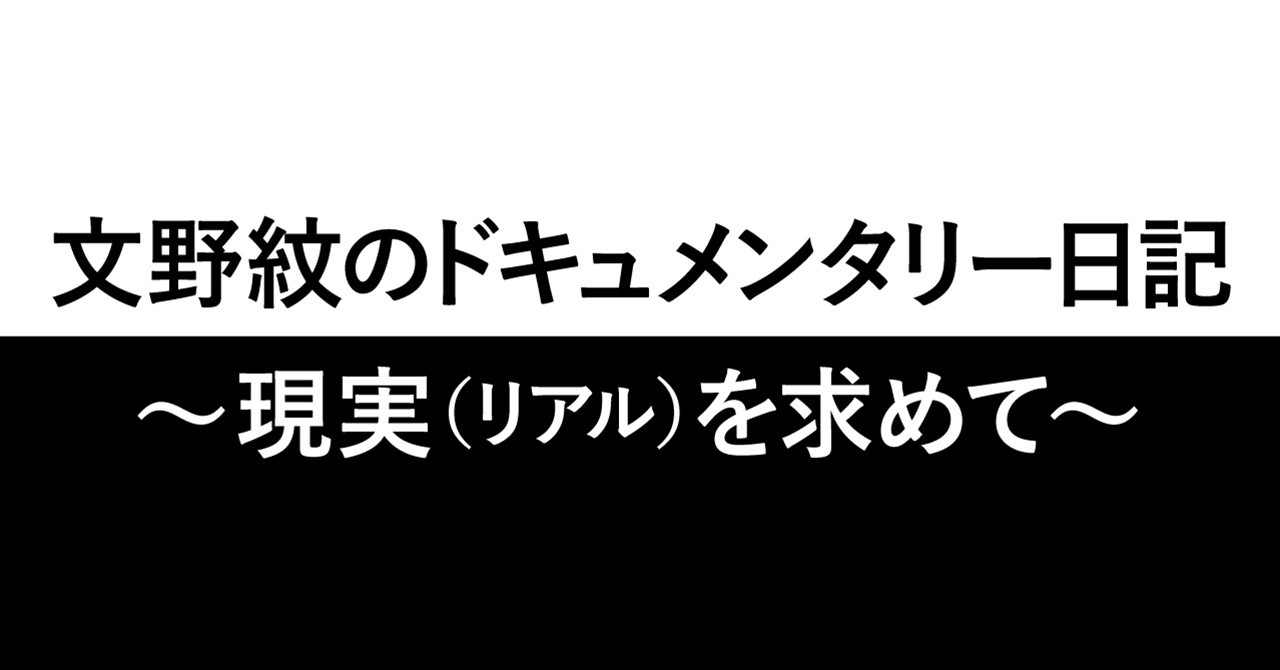20年の歳月をかけて描いた“人間の感情” 6時間超の大作──原一男『水俣曼荼羅』

文野紋のドキュメンタリー日記 ~現実(リアル)を求めて~
人生を変えた一本、退屈な日々に刺激をくれる一本、さまざまな愛に気づく一本など──
漫画家・文野紋によるリアルな視点、世界観で紹介するドキュメンタリー映画日記。
2021年11月27日、撮影15年、編集5年、3部構成で上映時間は合計6時間12分の超大作ドキュメンタリー映画が公開された。監督は破天荒な元陸軍軍人・奥崎謙三を追ったドキュメンタリー映画『ゆきゆきて、神軍』(1987年)などで知られる原一男だ。
私は初めて触れたドキュメンタリー映画が同作であったこともあり、原一男は大好きなドキュメンタリー監督のうちのひとりだ。例に漏れず『水俣曼荼羅』の公開を心待ちにし、もちろん劇場に足を運んで視聴した。
水俣病は日本における高度経済成長期の四大公害病のひとつで、1953年ごろから1960年代にかけて熊本県水俣湾で発生した。その正体は周辺の化学工業(チッソ株式会社)から排出されたメチル水銀化合物に汚染された魚介類を日常的に食べていたことによる水銀中毒である。
2004年10月15日、撮影がスタートした。
この日は最高裁判所関西訴訟、通称「水俣病関西訴訟」の判決日であった。水俣病関西訴訟とは、かつて不知火海(水俣湾を含む内海)周辺地域に居住し、のちに関西に移住した患者59名(控訴審時58名及びその承継人)がチッソ株式会社・国・熊本県に対し、損害賠償を求めたのだ。

第1部では主に、熊本大学医学部教授の浴野成生(えきの・しげお)さんが、水俣病による感覚障害の定説とされていた「末梢神経説」に対し、新病像論「中枢神経説」を主張する様子が描かれている。撮影当時、水俣病は「52年判断条件」というとても厳しい基準を満たさなければ認定されず、ほとんどの患者は水俣病であると認定されない状況が続いていた。この条件は「末梢神経説」を前提としたものであったため、浴野さんが主張する「中枢神経説」はその条件を覆し、認定されない水俣病患者を水俣病であると証明するものだった。
この浴野成生という人物は非常に独特で、魅力的だ。浴野さんは、なにも正義の使命感だけで水俣病を研究しているわけではない。彼は水俣病を学問として捉えており、原も彼が水俣病患者の脳に接するシーンを“オタクっぽい手つき”と評している。映画を観た人の中には彼を“マッド浴野”と言う人までいるという。水俣病にフォーカスした作品で、このようなキャラクターが登場するのは非常に意外でおもしろい。
第2部では主に、小児性水俣病患者の生駒秀夫(いこま・ひでお)さんを中心に水俣病の実情を映していく。彼は原たちを一番歓迎した住民で、さまざまな場所に案内したという。原によると一番仲よくなった住民だそうだ。また第2部の中盤にあたる2009年、水俣病問題の最終解決を旗印に「水俣病特別措置法」が成立する。水俣病に見られる症状を持っている人に一時金210万円と療養費、療養手当が支払われるというものだった。ただし、新たに裁判を起こした場合は手帳が使えなくなるという条件。和解する裁判が相次いだが、反発する者もいた。佐藤英樹(さとう・ひでき/「水俣病被害者互助会」団長)さんは「水俣病は絶対に終わりません」と語る。
第3部では胎児性水俣病患者の坂本しのぶさんが原とともに、これまで好きになった数々の男性を訪ねていくことになる。きっかけは『もやい音楽祭』で、しのぶさんが作詞した曲「これが、わたしの人生」が優秀作品賞を受賞したことだ。
「じっとステージの上にいて、歌を聞いて、自分が作った歌でしょう、何を思ってたの?じっと何か考えているふうに見えたの」
原の問いに、しのぶさんが答える。
「側に大好きな人がおったの」

原はオーディオコメンタリー(『水俣曼荼羅』初回限定版DVD-BOX特典)で、そのときのしのぶさんの表情は、今までの人生の悲喜交々があふれての表情だと思っていたため、驚いて「昔好きだった人を訪ねに行かないか」と提案したのだと語った。おもしろおかしく恋愛トークをするしのぶさんと、その想い人を見て、切なさで涙が出てきたのだと、そう語る原の声も涙ぐんでいるように聞こえる。第3部のオーディオコメンタリーでは、このあとも原の住民たちに対する強い感情がうかがえる。
作家の石牟礼道子(いしむれ・みちこ)さんと渡辺京二(わたなべ・きょうじ)さんを訪ねるシーンがある。そこで原は“悶え神(もだえがみ)”という概念を教わる。
「自分が何の加勢もできんから、せめてね、せめて嘆き悲しみを共にしてやろうということですよね」
「人のことなのにさ、我がことのように悶える人がいるってわけですよ。そのことを悶え神っていうふうに部落で言うんだそうです」

原一男といえば、以前は『さようならCP』(1972年)の横田弘、『極私的エロス・恋歌1974』(1974年)の武田美由紀、『ゆきゆきて、神軍』の奥崎謙三、『全身小説家』(1994年)の井上光晴……と強烈な個人に密着したドキュメンタリーを制作している印象が強かった。中でも『ゆきゆきて、神軍』の奥崎謙三は強烈だ。原は自身の映画を“スーパーヒーローもの”と呼ぶもこともあった。
2018年、キネマ旬報社から発行された『タブーこそを撃て!原一男と疾走する映画たち』で、原は当時のことを振り返り「圧倒的に強い人たちに出逢い、カメラを手に格闘しながら強くなりたい。そう思っていたんです」と語る。
しかし近年は、大阪・泉南アスベスト国賠訴訟を記録した『ニッポン国VS泉南石綿村』(2018年)、そして『水俣曼荼羅』など群衆に目を向けた作品の印象が強い。『水俣曼荼羅』では“曼荼羅”という言葉を用いて、個ではなく群衆を映したことを表現している。
『水俣曼荼羅 製作ノート』(2021年/皓星社)によると、『水俣曼荼羅』の撮影が始まって10年くらい経ったころ、親睦会で浴野さんが「今回の映画は交響楽、シンフォニーみたいな映画になるだろう」と挨拶をしたらしい。しかし、原一男は次第にいろいろな楽器の音をひとつに重ねて作る“シンフォニー”というより“曼荼羅”のほうがしっくりいくと気持ちが変わっていったのだそうだ(“曼荼羅”とは、密教で宇宙の真理を表すために、仏や菩薩の集会を体系的に図示したもののことである。)
第1部の中盤、認定申請を4回棄却され“偽善者”扱いまでされた水俣病患者。緒方正実(おがた・まさみ)さんは、熊本県が提出した棄却理由書に“人格”によって検査結果が信頼できないかのような文言が書かれていることに気づく。指摘を受け、水俣市へ謝罪に来た県の担当者3名は、自分の仕事のやり方が間違っていた旨を率直に認め、公開された場で謝罪するのだ。
このことについて原は「行政の人の中でも水俣病という問題に真っ向から取り組もうとする人がいなくはないんですけども、それが大きな力になって国の方針を変えるというところまでいきませんもんね。どっかでそういう声ってつぶされていくっていいますかね」とコメントしている。
(『水俣曼荼羅』初回限定版DVD-BOX特典オーディオコメンタリーより引用)
“敵側”のこういった人物を映しているところが、シンフォニーというよりむしろ曼荼羅に近いイメージだという理由のひとつなのではないかと思う。
また『水俣曼荼羅』では、52年判断条件を覆す研究をしている浴野さんを、正義感に燃える情に熱い医師という安易なイメージの枠にはめて描いたりはしない。同じく、胎児性水俣病患者のしのぶさんは「恋多き女」という顔を見せてくれる。
本作はひとりの人物にフォーカスするのではなく、水俣病を取り巻くさまざまな人々を映している。しかし、その人々は単に水俣病患者という「群衆」としてではなく、「緒方さん」「生駒さん」「しのぶさん」……として描かれているのだ。

『キネマ旬報』2021年12月上旬号のインタビュー「私は、「私たち」を描く人に変わった」で、原は“前期”、“後期”という言葉を使って説明している。
「前期の私の映画は「個」を撮ったけど今は「私たち」という認識が私の中で強くなっている」
「(『水俣曼荼羅』について)いろんな人間が入り組んで、一つの世界の中で曼荼羅をあやなしている状況をまるごと描いてみたいという気持ちがずっとあった」
このような被写体の変化について、原は時代の影響があるという。昭和から平成、令和と時代が流れていくにつれて奥崎謙三のような人間は生きられなくなった。もし今の時代に奥崎謙三のような人間がいても、インターネットで叩かれるなどして『ゆきゆきて、神軍』に映る彼のようにはいかないのではないか。
原は奥崎謙三のような強烈な個性の人間、撮りたいと思う人間がいない時代になったことで、映画監督としての自分は終わってしまったのではないかと落ち込んでいたという。
そんななか、原に手を差し伸べたのが“水俣病”。普通、民衆には奥崎謙三のような強い感情のほとばしりはなく、むしろ日本の民衆は控えめで権力に逆らうことは少ない。しかし、アスベストの被害者や水俣病の患者たちは、加害側の企業や行政に対し怒るべきであると学習している。奥崎謙三ほど強くはないが、必ず感情が出てくる。原はそれをとにかく丁寧に撮っていこうと決めたのだという。
『水俣曼荼羅 製作ノート』では次のようにも語っている。
「この作品において、私は極力、水俣病の患者である人たちや、その水俣病の解決のために闘っている人たちの感情のディティールを描くことに努めた」
「『水俣曼荼羅』はこれまでの公害運動を描いた作品のように画一的なパターンの運動映画ではない。観るもの=観客の自由な解釈に委ねる「遊び心」にあふれた内容に仕上がっているはずだ」
オーディオコメンタリーで、原は最後、このように映画を締める。
「私たちは映画を作る、ドキュメンタリーを作るっていうことは、石牟礼さんの言葉を借りていえば、私たち自身が悶え神なんだろうなというふうに思いながら、まだまだくたばっていく最後の最後まで悶え神としてドキュメンタリーを作っていかなきゃいけないんじゃなかろうかって、今もそういうふうに思っているんですね」
『水俣曼荼羅』は「第95回キネマ旬報ベスト・テン 文化映画作品賞第1位」「第76回毎日映画コンクール ドキュメンタリー映画賞」など各賞を受賞し、高く評価されている。
公式サイトに、このような一文がある。
“『ゆきゆきて、神軍』の原一男は『水俣曼荼羅』で、鬼才から巨匠になった──”
文野 紋
(ふみの・あや)漫画家。2020年『月刊!スピリッツ』(小学館)にて商業誌デビュー。2021年1月に初単行本『呪いと性春 文野紋短編集』(小学館)を刊行。
同年9月、『月刊コミックビーム』(KADOKAWA)で『ミューズの真髄』を連載スタート。単行本『ミューズの真髄』1巻&2巻は重版が決定しており、3月10日には完結最終3巻が発売された。
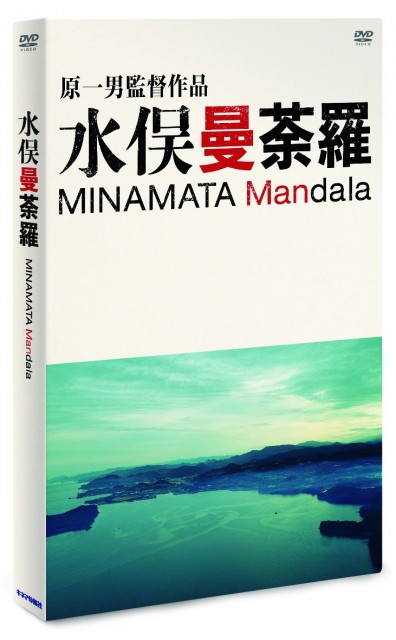
発売元:キネマ旬報社
販売元:ハピネット・メディアマーケティング
(C)疾走プロダクション