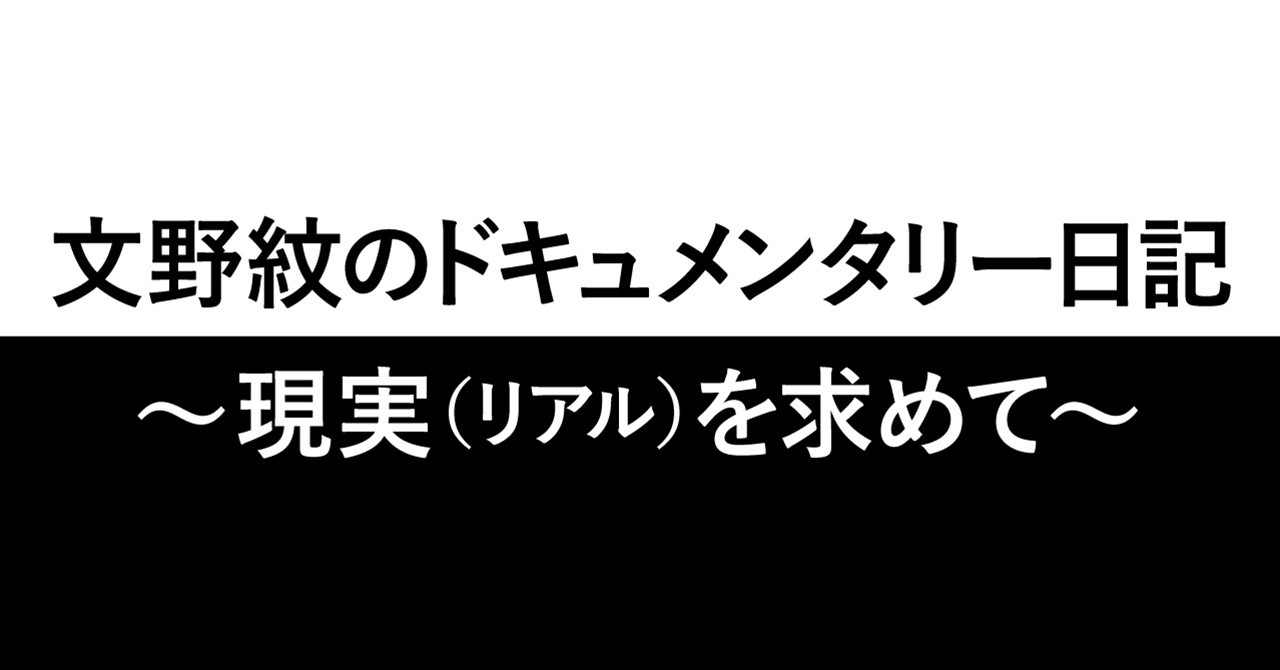生きるために食べる、あたりまえを考え直す授業──前田亜紀『カレーライスを一から作る』

文野紋のドキュメンタリー日記 ~現実(リアル)を求めて~
人生を変えた一本、退屈な日々に刺激をくれる一本、さまざまな愛に気づく一本など──
漫画家・文野紋によるリアルな視点、世界観で紹介するドキュメンタリー映画日記。
2016年公開の本作は、『グレートジャーニー』(フジテレビ)などで知られる探検家・関野吉晴が武蔵野美術大学で行った9カ月にわたる課外ゼミを映したドキュメンタリー映画だ。内容は、学生たちが文字どおり一からカレーライスを作っていくというもの。監督である前田亜紀が「ナマの関野さんに一度会ってみたい」という好奇心から武蔵野美術大学の研究室を訪れたことを発端に制作が始まったという。
4月28日、関野ゼミの説明会に訪れた学生200人ほどに対し、関野は“カレーライスを一から作る”計画について説明した。“一から作る”ということは、器、米、野菜、スパイス、肉、塩、箸にスプーンに至るまで、素材、種、雛から作るということだ。カレーの種類はシーフードカレーにするか、ビーフカレーにするか、と議論が進められた結果、ダチョウカレーに決まった。

「育てたダチョウを殺すのも自分たちでやるんですか?」
「もちろん。誰かがダチョウの首を切ります」
日本では「と畜場法(通称・屠場法)」によって牛、馬、豚、めん羊および山羊は屠畜場以外での屠殺・解体は規制されているが、鶏やダチョウ・あひるなどの家禽(食肉および卵を得るために飼育する鳥の総称)はその対象ではない。家禽類にも検査や指定場所を定める「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」という別の法律が存在するが、と畜場法と違い規制されているのは不特定多数に提供する場合に限られているのだそうだ。つまり、ダチョウであれば学校内で生徒たちの手でしめて肉にすることができる。
生徒たちが静まり返った。
本作は、関野と学生たちが野菜作り、お米作り、器作りや塩作り……とカレーライスに必要なものを作っていく過程を映しているのだが、やはり大きな見どころのひとつは、お肉に関するところだと思う。
6月、まず初めに学生たちはダチョウカレーを作るという目的のため、埼玉のファームに相談しダチョウの雛を3匹売ってもらう。しかし、3匹の雛は1カ月で全滅……3匹とも死んでしまった。9月、次に学生たちは、ほろほろ鳥と烏骨鶏を飼う。世話を続け12月になると、烏骨鶏が卵を産み始める。そのことをきっかけに翌年1月、学生たちの間で「鳥を本当に殺すべきなのか?」という話し合いが行われる。
この話し合いが行われたもうひとつのきっかけとして、12月に行われた「勉強会」の影響があるだろう。関野は特別講師として芝浦屠場の職員3人を招いた。そのうちのひとりである栃木裕さんは30年以上、芝浦屠場で働いているベテランだ。栃木さんは屠畜の仕事の流れについて説明したあと、「自分たちの仕事をみんなに知ってもらいたい」と話した。
「ぼくらの仕事は、動物を殺しているということで、残こくな人だと思われたり、特別な、差別的な目で見られたりすることが多いのです」
(ポプラ社ノンフィクション(29)『カレーライスを一から作る 関野吉晴ゼミ』より引用)
栃木さんの著書に『屠畜のお仕事(シリーズお仕事探検隊)』(解放出版社)がある。映画を通して屠畜に興味を持った方には、この書籍もおすすめしたい。
この本では、豚や牛が我々の食卓に届くまでが解説されている。特に解体について書かれている前半は非常にわかりやすく、屠畜とは高い技術を必要とする職人の仕事であるということがわかる。栃木さんは屠畜は「畜産という農業の一環」であり「世のなかに多くある仕事のなかのひとつ」であると語る。蔑まれるのはもちろんのこと「素晴らしい仕事」「尊敬する仕事」と持ち上げられることへの不愉快についても述べている。
また、屠畜場を舞台にしたドキュメンタリーには、『ある精肉店のはなし』(監督・纐纈あや)が挙げられる。
牛の眉間にハンマーを振り下ろして気絶させるという衝撃的なシーンから始まる今作は、大阪府貝塚市で家業として7代続いた屠畜場が102年の歴史に幕を降ろすまでを描く、「生」の本質を見続けてきた家族の記録である。取材対象である北出精肉店の人々は肥育から屠畜、精肉、小売り、さらには移動販売まですべてを一貫して行っている。
この映画は文化庁映画賞文化記録映画大賞、ニッポンコネクション(フランクフルト)ニッポン・ヴィジョンズ観客賞、第5回辻静雄食文化賞とさまざまな賞を受賞するなど高い評価を得ており、屠畜に携わる一家の魂が感じられる。
近年では、引退した競走馬の現状にカメラを向けた2019年公開のドキュメンタリー映画『今日もどこかで馬は生まれる』も話題になった。
本作によると、国内で競走馬となるために生まれたサラブレッドのうち約9割が屠畜され生涯を終えていると推測されるという。もともと食肉用として生産された家畜と違い、サラブレッドは競走馬として結果を残せるか否かによって行く末が左右される。また、サラブレッドは競走馬という特性上、ほかの経済動物と違い名前がつけられ、多くの人が認識し応援している存在だ。
2008年公開の映画『ブタがいた教室』では6年生を担当する新米教師の主人公が食べることを前提にクラスで豚を飼うが、児童たちが名前をつけてペットのようにかわいがってしまうという内容が描かれている。同作は、1990年から1993年にかけて大阪府の教師により実際に行われた授業をもとにしている。1993年には実際の授業を取材したドキュメンタリーがテレビ放送され、賛否両論を巻き起こしたという。私は実際にドキュメンタリー版を見たことはないが、世間がさまざまな意見を持つのは想像に難くない。
『カレーライスを一から作る』の「鳥を本当に殺すべきなのか?」という話し合いでも、ペットと家畜の違いについて論じられていた。
「(烏骨鶏が)卵を産む間は育てていくべきではないでしょうか?」
多くの学生は「もともとペットとして飼ったわけじゃない。食べるために飼ったのだから、途中で殺すのをやめるというのはちがうんじゃないか」という意見を持っていた。一生懸命鳥たちを育てていた学生らが自らの考えを述べていく。そして話し合いの末、屠(ほふ)るべきだと決めた学生たちが鳥たちの首を捻り、切り落とすシーンは壮絶だ。

この映画は当初の計画どおり、みんなでカレーライスを作り食すところがラストシーンとなる。
中でもゼミを受講していた学生のひとり、髙橋くんのコメントが印象的だ。
「いつも食べている鳥の味がします。もっと泣きながら食べると思っていたけど、やっぱりおいしいですね」
屠畜を扱ったドキュメンタリー作品は何本か視聴したが、カメラに映し出されている屠畜に携わる人々が述べる思想はそれぞれだ。
また、私自身、映像を観て本を読んだところで、ハッキリと主張できるほど価値観がまとまったとは到底言えない。
しかし、屠畜や屠畜に携わる人々を映したドキュメンタリーは我々に考えるための知識と機会を与えてくれる。この文を読んで興味を持った方がいたら、ぜひ機会を探して作品に触れてほしいと思う。知ることはすべての始まりだと思うから……。
文野 紋
(ふみの・あや)漫画家。2020年『月刊!スピリッツ』(小学館)にて商業誌デビュー。2021年1月に初単行本『呪いと性春 文野紋短編集』(小学館)を刊行。
同年9月、『月刊コミックビーム』(KADOKAWA)で『ミューズの真髄』を連載スタート。現在絶賛発売中の単行本『ミューズの真髄』は1巻&2巻ともに重版が決定している。

(C)ネツゲン