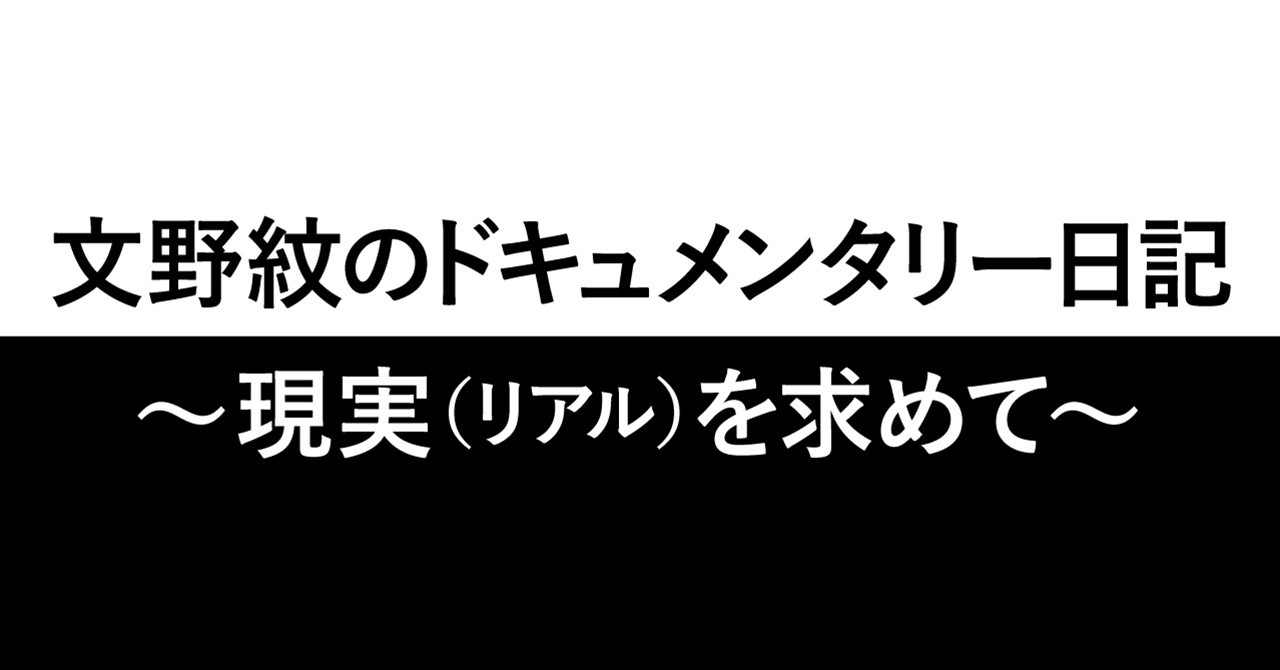生きてる限り続く、大切な人との記録──信友直子『ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえり、お母さん~』

文野紋のドキュメンタリー日記 ~現実(リアル)を求めて~
人生を変えた一本、退屈な日々に刺激をくれる一本、さまざまな愛に気づく一本など──
漫画家・文野紋によるリアルな視点、世界観で紹介するドキュメンタリー映画日記。
『ぼけますから、よろしくお願いします。』は2016年にテレビ番組の企画として始まり、2018年に劇場公開されたドキュメンタリー映画である。認知症であるお母さんと耳の遠いお父さんの老老介護をその娘が映す本作は動員20万人を超えるなど単館映画としては異例の大ヒットとなる。続編となる『ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえり、お母さん~』では、認知症であるお母さんを看取ることが軸として描かれている。
「ただいまぁ」
広島弁訛りの直子(信友直子/本作の監督)の言葉から、信友家3人の物語は始まる。東京で働く直子は広島県呉市にある実家に帰省した。母・文子は85歳、父・良則は93歳。
最近母の様子がおかしい。ちょっと前に話したことも忘れてしまう。2014年1月8日、母はアルツハイマー型認知症と診断された。父は淹れたコーヒーを母に振る舞う。
「まぁ、お互いにがんばりましょうねぇ」
父がそう言うと、母は
「どっちかが、おらんになったら、寂しいけんね」
と返した。
直子が再び帰省したとき、母は87歳。洗濯機の前で寝転がっていた。洗濯物がうまくできなくなっていた。直子が「手伝うよ」と言っても、母は「手伝ってもらったらかなわんけん」と頑なに拒む。
「迷惑かけるねぇ。ごめんねぇ」
母の言葉が、切ない。
大変なのは母だけではない。母に代わって家事を始めたのは95歳の父なのだ。
「まぁ、これも、運命じゃ。定めじゃわい」
男子厨房に入らずで家事は母に任せっきりだった父が、母に代わりゴミを出し、曲がった腰で掃除機をかける。スーパーからの帰り道、両手にスーパー袋を持ち、立ち止まる父。歩くことすらも大変なのだろう。
直子は父に仕事を辞めて広島に帰ってきたほうがいいかと尋ねるが、自分が面倒を見るから大丈夫だと言う。娘には自分の仕事に専念してもらいたい、と。
そんなふたりの老老介護を映した映画、というのが前作(『ぼけますから、よろしくお願いします。』)の内容である。
続編は、映画(前作)公開の直前、母が脳梗塞を発症し入院を余儀なくされることから始まる。幸い命に別状はなかったが、体の右半身が麻痺してしまった。母は家に帰りたい一心でリハビリを始める。
父は毎日毎日、片道1時間かけて歩いて病院に通っていた。
「おっ母、早う良うなってのう」
父が手を握って言うと、母が呼吸器をつけた口を動かして返す。
「手がかかってごめんね」
耳の遠い父のために直子が繰り返すと、
「そんなこたぁないよ」
父はそう言うのだった。その言葉どおり、父がむしろ母に会いに行くのが新しい生き甲斐であるかのようだ。それどころか、いつか帰ってきたら自分が支えられるように、と、筋トレまで始めていた。父はこのとき98歳。なんと凄まじい愛だろう。
しかし、母は二度目の脳梗塞に襲われてしまう。しかも、一度目と反対の脳だったために麻痺は全身へ。呂律もうまく回らなくなってしまう。母は、医師から提案された胃ろうという方法を取ることになった。これは胃に穴を開け直接栄養を流し込むというもので、延命治療(病気の根治ではなく延命を目的とした治療)だ。
「お母さんはどんな気持ちなんかね。いろういうのはね、したときにはわからんかったけど延命治療のひとつなんだって。私らの都合で胃ろうにしたけどえかったんかね」
「そりゃあわからんが、助けてやりたいなぁ、思うがな」
母を胃ろうにしたことが正しかったかは未だにわからない、と直子は語る。
2020年4月。母の病状が一気に悪くなる。6月には危篤状態に。
「わしゃ別れの挨拶なんかせんぞ」
「おっ母、早う帰ってこいよ」
相変わらず頑固な父。
そして、6月13日の夜。
「もうね、がんばらんでもいいんよ。お母さんありがとね」
「ありがとねぇ。わしも良い女房をもろた思うちょります」
前作が認知症や老老介護を描いたドキュメンタリーなら、今作は長年連れ添った夫婦の純愛ストーリーなのではないかと思う。夫婦の、そして娘である直子を含めた家族3人のお互いを愛する心がこれでもかというくらいあふれていて、上映の後半から、私は涙が止まらなかった。右の人も左の人も、おそらく前後の人も皆、涙を流していた。そして上演終了後、ポレポレ東中野(東京都中野区にあるミニシアター)は大きな拍手に包まれた。監督による上映後の舞台挨拶を控えていたことも影響しているかもしれない。
私は、気になる映画は初日や舞台挨拶のついた回を狙って観に行くことも多い。しかし、このときほど人が涙を流し暖かい拍手をしている回は珍しい。というより、私の経験ではなかったかもしれない。それくらい映画館で観ていたすべての人が信友家の3人に心をつかまれていた。
本作は監督・信友直子の語りによって話が進む。信友直子は1961年、広島県呉市生まれ。東京大学文学部を卒業したのち就職した菓子製造会社に在籍中、取材を受けたことをきっかけにテレビ制作に興味を持ち、1986年にはテレビ制作会社に転職をする。
2009年、フジテレビ『ザ・ノンフィクション』にて、自身の乳がんに関するセルフドキュメント『おっぱいと東京タワー~私の乳がん日記~』が放映される。
監督が自身の親の最期を看取るドキュメンタリーと聞くと、私は砂田麻美監督の『エンディングノート』(2011年)が思い浮かぶ。日本製ドキュメンタリーとしては1987年の『ゆきゆきて、神軍』(原一男監督)以来、約24年ぶりに興行収入1億円を突破するなど、異例の大ヒット作で、末期ガンを宣告された男性(麻美監督の実父)が“エンディングノート”を制作しながら“終活”する、というストーリーである。エンディングノートとは、自分の死後について家族に向けて希望などを書き溜める、法的拘束力のない遺書のようなもののことである。
『エンディングノート』では、是枝裕和氏(『万引き家族』などで知られる映画監督)がプロデューサーを務めている。『エンディングノート』を試聴したあと、私は家族の死に際を撮るというのはいったいどういう気持ちなんだろうと気になって、本作に関するインタビュー記事を探した。その中に是枝氏との対談記事があった。
その中で是枝氏は、監督が自身の家族を撮ることについて語っていた。曰く、(家族を対象としたセルフドキュメンタリーが)「正直嫌いだった」「自分が教えている学生たちにも家族を撮るのはやめたほうがいいとアドバイスをしていた」のだと言う。(そう語る是枝氏がプロデューサーを務めているのだから、『エンディングノート』は作品としてとても完成度が高くおもしろいし、対談の中でも是枝氏はエンタテインメント作品として成功していて、かつ、考えさせられる作品になっていると述べている)
私は映画監督でもドキュメンタリー監督でもないので、是枝氏の言葉の重みを真に理解することはできないが、ドキュメンタリーディレクターを経て、『誰も知らない』『そして父になる』『万引き家族』、昨年には『ベイビー・ブローカー』など家族をテーマにした多くの名作を手がけている彼が言うのだから、家族を撮るということはとても危険で難しいことなのだろうと思うし、覚悟が必要なことであるように感じる。家族を映したドキュメンタリーは、そういう難しさの上で成り立っているのだろう。
前作『ぼけますから、よろしくお願いします。』にも、母が「撮らないで」と泣き叫ぶシーンがある。きっかけはヘルパーさんが来る日、母がなかなか起きられなかったことだった。
「助けてよ」
「助けて言うて、何を助けるんだい」
そんななか、ヘルパーさんからの電話。どうやら今から向かいます、という連絡のようだ。父は母を起こそうとするがなかなか起きない。やっとのことで起きた母が語る。
「どんどんバカになってきよる、ね。悲しいやね。まあしょうがないわね。人間じゃけんね。いいときばっかりやない」
ずっと家族の面倒を見てきた自分が、家族に面倒を見られている。母はそれがつらくてたまらないようだ。次の日の朝も、母はなかなか起きられない。この日、ついに母の気持ちが爆発してしまう。
「死ぬ、もう私は死んだほうがええ。死んだほうがええ。包丁持ってきてくれ! 死んじゃる! 死にたい、ジャマになるけん死にたい」
「そがん死にたいなら死ね!」
父も声を張り上げる。びっくりして、胸がキリキリと痛んだ。
「写真ばっかり写さないで!」
やがて母は、直子にも声を張り上げ出す。寝て起きて、父が切ったリンゴを食べながらも、まだ涙が出てしまう母。
「ええことないね。」
この一連のシーンは本当に観ていて胸が痛む。
『BANGER!!!』(映画評論・情報サイト)に掲載されているインタビュー記事の中で信友監督は語っている。「これは私のライフワークというか、生きてる限り続くプロジェクトですね」彼女は父が亡くなるまで、また、祖母も母も認知症であったことから認知症になる(かもしれない)自分自身の老後まで撮ろうと思っていると言うのだ。
『ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえり、お母さん~』では、信友監督の母の葬儀のシーンが映されている。これは信友監督が事前に撮影可能な葬儀所を探していたのだと言う。信友監督は、その自分の行動を「業が深い」と語る……のだが、そのあとに加えて、それとは別として、亡くなったあとにも見返すとき写真より動画のほうが楽しいから親の動画は撮っておくといいですよ、とつけ加える。
今まで認知症の人が自撮りしたドキュメンタリーはないから、もし自分が認知症になったら、それを撮りたい。そう思うと、ぼけるのも怖くないしちょっと楽しみになってきた。そう笑って語る信友直子監督。撮ることの暴力性に向き合いながら、それでも撮ることを前向きに捉える彼女だからこそ、この映画は成立しているのだろうと思った。
そうだ、だからこそ、映画館で皆が涙を流し拍手をしていたように、この映画を観た人は信友家に自分たちを重ね、また、信友家のことが愛しくてたまらなくなってしまうのだろう。
映画館からの帰り道、愛する人を大切にしたくなる。そんな映画だ。
文野 紋
(ふみの・あや)漫画家。2020年『月刊!スピリッツ』(小学館)にて商業誌デビュー。2021年1月に初単行本『呪いと性春 文野紋短編集』(小学館)を刊行。
同年9月、『月刊コミックビーム』(KADOKAWA)で『ミューズの真髄』を連載スタート。現在絶賛発売中の単行本『ミューズの真髄』は1巻&2巻ともに重版が決定している。

『ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえり お母さん~』
全国順次公開中
(C)2022「ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえり お母さん~」製作委員会